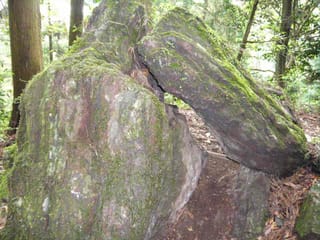あと1日
あと2日
靴下の問題は解決したものの気になることはまだ残っている。左足の太股横の筋肉の張りはずっと残ったままだ。ストレッチを続けてだいぶ柔らかくはなったけど、まだまだ普通の状態ではない。歩いているときには全く影響はないけれど、これが30kmを越えるとどういう影響が出てくるかは分からない。
あと3日
少し前から徳島の天気をお気に入りに登録して毎日週間天気をチェックする。焼山寺越えが曇り時々雨になっている。時々というのがせめてもの救い、山道では軽い雨なら合羽も着けず傘もさすつもりはない。鶴林寺、太龍寺越えは曇り時々晴れ。
レクチャー「蘇るバセット・クラリネット」
クラリネット五重奏曲イ長調 K.581 W・A・モーツァルト
クラリネット五重奏曲変ロ長調 op.34 C・M・v・ウェーバー
バセットクラリネットというのはモーツァルトの時代に使われていた楽器で、現代の楽器の最低音が「ミ」に対し、3度低い「ド」の音まで出るようになっている。五重奏にしろ協奏曲にしろモーツァルトが書いたそのままの楽譜はこの楽器でないと演奏できない。現代の楽器で演奏する場合は音の出ない低い部分をオクターブ上げた楽譜を使う。
クランポンは原曲で演奏できるバセットクラリネット(A管)を発売しているし、その楽器でコンチェルトを演奏するザビーネ・マイアーの映像も見たことがあります。でも今回の演奏会で使われたのはその楽器ではありませんでした。ヒストリカル・クラリネット奏者のロレンツォ・コッポラ氏が4本の楽器を持って舞台に出てきた。その4本のいずれもが楽器博物館でしか見たことのない様なものだった。先ず色が違う。黄色(黄土色)でキイが目立たない。もちろんキイの数も違う。現代の一般的なベーム式のクラリネットは17キイ6リング、最初に紹介されたのは5キイのごく初期の楽器。この楽器では半音階の素早い動きが難しく、音の鳴り方にもでこぼこがあるし、大きな音が出ない。でもちゃんとクラリネットの音はしている、こういう楽器から音が出るだけでもちょっとした感動がある。当時の作曲家は、よく出る音、くすんだ音も分かってその音色をも計算した上で作曲をしたという。その次に紹介されたのは18世紀の後半に改良された10キイ(12キイかもしれない)の楽器、これだと半音階も相当スムーズだし音色音量のばらつきもほとんどなくなった。この楽器でウェーバーを演奏、リングもなく、キイが7つも少ないのに何の不自由もなく楽々吹いているように見える、これ以上の改良が必要だったのだろうかと思えるくらいだった。次に紹介したのが写真のバセットホルン、この非常に不格好な楽器がちゃんと音が出る。ちゃんとクラリネットの音がする。しかも速いパッセージも楽々だ。ラッパの上の四角い部分の中で、管が蛇行していてより低い音が出せるようになっている。高音域、中音域は普通のクラリネットと同じ音色、音程で機動力も同じ。それにプラスして低音域を出せるようにしたのがこの楽器の大きな特徴になっている、普通のクラリネットの音域が3オクターブ半ぐらいなのに対してこの楽器の音域は4オクターブ半はあるという。だからバスクラリネットとは全然違う。モーツァルトの時代には重宝されたようです。最後に取り出したバセットクラリネットは現代のものとかなり違う形状をしていた、ベルがなくて瓢箪の下半分のようなものが一番下についていて少し前に突き出ている、写真の黒い四角い部分に丸く白いものがついているという感じ、そして穴が上についている。現代のバスクラリネットのベルを瓢箪かパイプの先のようにしたといえば分かりやすいかもしれない。でも現代の楽器を見慣れていると、どうにも不格好な楽器というしかない。でも出てくる音は紛れもなく「クラリネット・ダムール」、現代のバセットクラリネット比べても、ほとんどその差はないと言ってもいいくらいだ。音だけ聞いてきっちり区別できる人は半分もいないかもしれない。もちろんこの楽器でモーツァルトを演奏。モーツァルトはこの楽器を見、この楽器の音を聞いてあの名曲を書いた。モーツァルトの聞いていた音を200年後の我々が今聞いている。
躍動する魂~吹奏楽のための 江原大介
カンタベリー・コラール J・V・d・ロースト
オデッセイ~永遠の瞬間へ 真島俊夫
第2部 16世紀のシャンソンによる変奏曲 諏訪雅彦
コミカル★パレード 島田尚美
ネストリアン・モニュメント 平田智暁
マーチ「青空と太陽」 藤代敏裕
第3部 詩のない歌 R・ルディン
宇宙の音楽 P・スパーク
アンコール アルセナール
ダンシング・クイーン
パンフレットの指揮者紹介を見てびっくり。音楽監督:深田哲也・・・・2002年に六甲ヴェルデ吹奏楽団の音楽監督に、2009年から関西大学吹奏楽部の音楽監督に就任した。とある。関大は3年連続で違う指揮者を迎える。昨年、一昨年の指揮者と違うのは、この指揮者はコンクールを知っているということ。コンクールの勝ち方を知っている。明石北高校の指揮者として8年連続関西大会金賞、そのうち2回は全国大会出場を果たしている。どんなに優秀な音楽性と経験に溢れた指揮者でもアマチュアのコンクールでよい成績を残せる指導が行えるとは限らない。そういうことからすれば今回の選択は最高の結果をもたらす可能性を秘めている。でも、合う合わないということもある。高校生と大学生とではずいぶん違うだろうし、指揮者についていけるだけの能力や練習ができるかということもある。理想的な吹奏楽指導者の下でも勝てなかったという例はある。
勝ち抜ける可能性は明らかに上昇したといえるけれど、すぐに勝てるというものでもない。関学は2年生以上だけで65名のメンバーがいる。立命館は3年連続全国大会出場の実績がある。関大は3学年で36名しかいない。どんなに実績のある素晴らしい指導者でも、これだけのハンデを僅か半年ではねのけるのは容易ではないと思われる。今年勝てなくてもそれは指導者のせいではなく、自分たちの実力がなかったにすぎない。もし勝てたとしたらそれは指導者の力によるものである。昨年、一昨年のように1年で結論を出すべきではない。最低でも3年はお願いすべきであろう。3年でメンバーの数を整え実力の養い方を試行錯誤する。結果を見るのはそれからでも遅くない。彼ほどの優れたアマチュアバンド指導者に出会えうことは容易ではない。
あと7日
大阪府の大会は吹田メイシアターと大阪国際会議場で行われる。森ノ宮青少年会館が閉鎖になるというのは本当のようだ。
いよいよ明日、高野山町石道を歩くので、予習として「街道をゆく」のビデオテープを引っ張り出してきた。司馬遼太郎の「街道をゆく」のテレビ版は全部録画して持っている。3倍速で録画してVHS7本になる。
その第27回「高野山みち」は次のようなナレーションで始まる。
『九度山とは町の名で、山ではない。紀伊の国、高野山が北に向かって山々や谷々を重ねようやく紀ノ川に至ろうとする岸辺にある。北方の葛城山脈と南方の高野山を中心とする山塊群の間に挟まって、川がゆうゆうと河原を広げつつ流れている』
司馬さんは町石道に入って数十メートルの所まで行って引き返している。ぼくはそこから20km以上歩き続けることになる。放送では6時間かかるといっていたけれど、ぼくは5時間で踏破したいと思っている。
高野山町石道
高野山町石道は高野七口といわれる高野山の登山道七本のうち、弘法大師空海によって高野山の開創直後に設けられた参詣道で、紀ノ川流域の慈尊院(海抜94m)から高野山壇上伽藍(同815m)を経て高野山奥の院弘法大師御廟に至る高野山への表参道です。
町石道が開かれた当初弘法大師は慈尊院から高野山までの道沿い一町約109mごとに木製の五輪卒塔婆を建立したとされます。文永3年(1266年)以降は、鎌倉幕府の有力御家人、安達泰盛らの尽力で朝廷、貴族、武士などの広範な寄進により朽ちた卒塔婆に代わって石造の五輪卒塔婆が建立され、ほぼ完全な形で今日に遺されています。
町石にはそれぞれ密教の仏尊を示す梵字と高野山に至る残りの町数、そして寄進者の願文が刻んであり、巡礼者や僧侶はこの卒塔婆に礼拝をしながら、全長約23km(うち高野山内4km)、標高差700mの道程を一歩一歩、山上に導かれて行ったのです。
町石道は三十六町一里制にもとづき、古代条里制がほぼ完全な形で遺る遺構であり、聖山・高野山とともに今後も注目を集めることでしょう。
わかやま観光情報、というサイトに分かりやすい解説があったのでそのまま写させて頂きました。
九度山から
四国の巡礼道で一番長い山道は11番藤井寺から12番焼山寺までの12.9km。標高差は660mだけれど、幾度も登り下りを繰り返すので実際はその倍以上は登ることになる。速い人で4時間、遅い人は7時間以上かかることもあるという。
慈尊院から大門までは19.4km、標高差は同じくらいではあるけれど6.5kmも長い。どういう坂があるか、どこに何があるか、分からないことだらけだ。しかも1年前四国から戻って以来一度も山道を歩いていない。太股の裏の筋肉に張りが残っている。靴はおろして5日目、天気は最高によいけれど、不安だらけのまま九度山駅に降り立ったのは10時5分、四国と同じ、ここまで来れば前へ進むしかない。
真田庵
10時12分、真田庵に到着、表通りから少し奥まったところにあった。大きな案内板が出ているので行き過ぎてしまうことはない。写真の長屋門が入り口で、その内部はちょっとしたギャラリーになっていた。その中で目に付いたのは、ずいぶん前のNHKドラマ「真田太平記」のポスターでした。真田幸村役の草刈正雄、その兄の信之役の渡瀬恒彦、女忍者役の遙くらら、そして紺野美沙子(信之正室、本田忠勝の娘)の4人が写っている。ぼくはこのドラマを熱心に見ていたのでとても懐かしい。それにしても直射日光が当たる場所ではないのに、このポスターの色のあせ様は、その月日の長さを思わずにいられないものです。放送されたのは24年前、中村梅之助、中村梅雀親子が、徳川家康、秀忠親子役で出演していました。
慈尊院
先が長いので真田庵の境内には入らなかった。長屋門の中で5分ほどたたずんで庵を後にした。1kmちょっと行くといよいよ町石道の始まりである慈尊院の石垣が見えてくる。先に裏門が見えたのでそちらから入ってしまった。裏門は通用口でその半分は小さな垣根に囲まれたゴールデンワンコの居住地域になっていた。ここから入ってくる参拝者はいないようで、不思議そうにぼくを見上げている。おとなしいワンコで助かった。門をくぐると左手にお大師さんの像、ここはまだ高野山ではない。高野山ではお大師さんは生きておられるから像は一切見当たらない。
弥勒菩薩がまつられた本堂(重要文化財)の手前に深緑色の大きな石碑がある、世界遺産に登録された記念の石碑だ。町石道とともに慈尊院も世界遺産なのだった。写真の鳥居に続く石段が町石道の始まりであり、その途中の右手に180町石が静かにたたずんでいた。いきなりの長い石段に足取りも重い。
柿の里
石段を登りきったところが丹生官省符神社(にゅうかんしょうぶじんじゃ)の境内、慈尊院の守護神が祀られている。境内を抜けて右手の緩い坂を下っていくといよいよ山道が始まる。
『町石というのは一丈一尺の石柱で、山頂まであと何町かを知らせる道しるべなのだが、石柱の頂が五輪の形をなし、石柱の表面に梵字が刻まれ、形は簡素な石の柱ながらも一基ずつがさまざまな菩薩を象徴しているということになっている。
山頂まで180基ある。
旧道を少し辿ってみたが、百歩も行かぬうちに、深山幽谷に紛れ行ってしまいそうで、そのまま引き返して石段の途中に戻った。』
街道をゆく、に記されている旧道の入り口は確かに深山幽谷の趣があった。でも、それはすぐに終わってしまった。舗装された急峻な山道は果樹園に入っていく、背の低い手入れの行き届いた柿の木が一面に植わっている。この時季葉っぱもほとんどつけていないので遠目にははげ山のように見えるかもしれない。日差しが容赦なく照りつける、南へ向かっていた坂道はやがて大きくUターンして北側の尾根の頂を目指す。坂はますます急になる。北に方向を転じると大きく視界が広がってくる、紀ノ川流域の大パノラマが自分だけのものだ。東は橋本あたりから、目の前の高野口町、下流のかつらぎ町までが一望の下にある、もしかしたら笠田のあたりまで見えているかもしれない。笠田というと、釣りきち三平が小鷹網をふるって鮎を捕ったところだ。中州の船岡山が見えているかは確認できなかった。
雨引山分岐
紀ノ川に突き出た山の端の北端をぐるっと巡って南へ転じると右手に展望台が見えた。まだ166町、1.5kmほどしか来ていないので休む訳にはいかない。岬の頂に立っている巨大な電波塔にどんどん近づいていく。この塔は電車の中から見えていた。まさかあんな高いところまでいきなり登ることはないだろうという、希望的観測はいきなり裏切られた。急坂はまっすぐ鉄塔に向かう、少し手前でその右をすり抜けて雨引山の登り口へ向かう、ここまで来ると登りは一段落、そしてようやく林の中へ入って山道らしくなってくる、日差しが遮られて、ようやく歩きに力が入ってくる。分岐点には必ず緑色の標識がある。←慈尊院 大門→、の新しい標識で全く迷う心配はない。四国でおなじみの赤い矢印と遍路人形の遍路シールも見ることができた。まもなく雨引山分岐に到着、153町、展望台から1.4km、登りがほとんどなかったので、あっという間だった。雨引山の標高は477m、ここはまだ300mくらいしかないのかもしれない。舗装道路はここまで、あとは地道が続く。ここまでは柿畑で働く人たちの生活道路なのだろう。
国道を横切って山道に入ってすぐ登ったと思ったら、展望台からは下りになってまた国道により沿う。そこからまた国道を離れ緩い下りになって国道を見上げながら進むことになる。国道はだんだん高くなって、10m以上の高さになっていく。国道が登っているのか町石道が下っているのか、いずれにせよ最終的にはあの高さまで登ることになる。36町石、四里石を過ぎてしばらく行くと有名な鏡石の前に出た。往時は鏡のように光り輝いていたというのだが・・・、ここから緩い登りになっていく。25町石を過ぎると渓流が現れた。そういえばここまで全く水の流れを見ることはなかった。いくつかの木橋を渡る。20町石を過ぎると最後の追い込みで坂はますます急になっていく。10町石を確認、あと300m、9町石も確認したけど、最後の8町石はなかった。大門前の国道を造るときに昔の山道は大きく削られたことだろうから、そのときにどうにかなってしまったものと思われる。国道へ上がってくる階段もそのときに造られたもので往時のものとは違うもののように思われた。大門前の国道に上がってきたのは14時53分、展望台からの3.6kmを43分で来た。この間の平均時速は5.02km、最後の登りは相当こたえた。
慈尊院からの正味の歩行時間は3時間57分、平均時速は4.77km。普通の人は6時間以上かかるというから、いいスピードだとはいえるけれど、あまり納得は行かない。筋肉の痛み、関節の痛みは全くない、靴擦れもなく、足の裏も大丈夫。いうことないといえばいえるけれど、かなり疲れました。もうこれ以上は歩けない、歩きたくないという感じです。九度山から5時間しか経っていない、四国に入るともう2時間以上歩かねばならないから、こんな疲れようではとても安心はできません。
町石道を全部歩くと、これで高野山を全部見たとことになると思いきや、まだまだだということが身にしみました。町石道は中世の表参道と言われている。近世の参詣道が別にある。江戸時代から明治時代にかけての一般的な参道は京・大坂道だといわれる。高野街道が紀見峠を越え、紀ノ川を越える、学文路から九度山へは行かず、そのまま南下して山に入る、河根から桜茶屋を経て紀伊神谷へ、そこから鉄道沿いに極楽橋まで行き不動坂から女人堂へ至る。この道を行くと学文路から壇上伽藍まで14km。町石道は学文路から壇上伽藍まで24km。これだけの近道が開発されると、人気になるのは分からなくもないのですが、昔の人はいつでもどこでも歩きしかないから、京大坂から参詣に来る人も、四国巡りを終えてから来る人でも、最後の10kmの近道がそんなにも魅力的なのだろうかと首を傾げたくもなる。ぼくなら迷わず町石が残っている歴史の道を歩きたいと思う。でも実際はそうならなかったらしい。でも江戸時代以降の道がどれくらい一般的だったのか、そのころでも町石道を歩く人がいたのかどうか、よく分かりません。分からないまま、とりあえず歩いてみなければなりません。まだまだこれで最後ということにはならないみたいです。
1部 ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス D・R・ギリングハム
伝説のアイルランド R・W・スミス
マーチ「青空と太陽」 藤代敏裕
忠臣蔵異聞 天野正道
2部 創作音楽劇
3部 ニホンノミカタ 矢島美容室/山里佐和子
宮崎駿アニメメドレー 久石譲/小島里美・渡部哲哉
マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン J・ホーナー/R・ソースド
メモリー A・L・ウェーバー
ベニー・グッドマン・メドレー 岩井直溥編曲
ギリングハムはあまり好きではないのですが、今回の演奏は今まで聞いた中で最高でした。20本のクラリネットが鳴りまくっている。バックで金管が全員で吹いていてもかき消されることはない。細かい音もきれいに、と言うよりガ~ッと噛みついてくる感じがする。ぼくは自分がクラリネット吹きだから、クラリネットが鳴りまくっていると嬉しくて仕様がない。最後までワクワクが治まることはなかった。85人の編成で20人、これだけの割合のバンドは近頃あまり見られない。この春の近大は78人編成で12人、関学は65人編成で10人だった。ずいぶん前のバンドジャーナルの対談で、井町昭先生(大阪府音楽団指揮者)と鈴木竹男先生が吹奏楽の理想的な編成について話されたことがある。そのときの結論としては、金管が1,クラリネットが1,クラリネット以外の木管が1、の割合が丁度いいということだった。つまりクラリネットは管楽器の3分の1の人数が必要ということになる。近大18%、関学17%に対して姫高は26%、理想の編成からはまだ遠いけれど、近頃の一般的なバンドに比べればれば十分すぎるくらいです。ゆたかでふっくらとした響きが得られるのは当然ということでしょう。