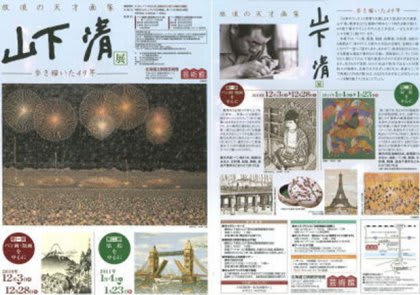日本はどう考えてもデフレの真っただ中です。
デフレというのは、生産力(供給力)のほうが需要よりも高い時に物が売れなくなって価値が下がるということ。
物が売れないという現象は、「物がたくさんあってもういらない」、「買うお金がない」、「買う気にならない」など多様な理由があって、「買うにしても安くなければ買わない」ということからどんどん物の値段=価値が下がるというサイクルになるとこれがデフレなのです。
そんなことを考えている「物を買う=消費」に関する興味深い記事が二本あったのでまずはこれをご紹介します。
---------------≪ 以下引用 ≫--------------
【消費を悪と考える「嫌消費」世代が市場で台頭!】田島 薫 Diamond Online
~景気を低迷させかねない“買わない心理”とは~
http://bit.ly/e3JqtN
経済や歴史、世代論などあらゆる観点から「嫌消費」世代を論じた『「嫌消費」世代の研究』(東洋経済新報社・定価1575円)。バブル期に青春を謳歌したビジネスマンにとっては、まさに隔世の感がある 若者がモノを買わなくなった――。最近、時折耳にするフレーズである。ファッションも食も極力節約し、自動車も買わず、旅行にも行かず、せっせと貯金に励む……そんな若い世代が、消費市場の新しい主役となりつつある。
そんな現象を裏付けるような書籍が、2009年11月に発表されている。「クルマ買うなんて バカじゃないの?」――帯文のそんな刺激的な惹句が話題となった『「嫌消費」世代の研究』(東洋経済新報社)がそれだ。発売以来、順調に版を重ねている。
著者は、ジェイ・エム・アール生活総合研究所の代表である松田久一氏。長年、情報家電産業や食品などの業界で、リサーチやマーケティング、経営戦略などに携わってきた人物だ。
本書によれば、「嫌消費」現象とは、「収入があっても、何らかの嗜好によって消費しない傾向」のこと。80年前後生まれ、現在20代後半の「バブル後世代」が「嫌消費」世代に該当するとされる。興味深いのは、彼らの中には低収入層の非正規雇用者だけではなく、しっかりした収入もあり、正規雇用者が多く含まれることが特色であるという。
その普通の若者たちの「嫌消費」ぶりは、我々の想像をはるかに上回る。たとえば、インポートブランドよりも服はインターネット通販で買う、クーポンがないとカラオケやレストランには行かない、外食よりは1人でも家で鍋がいい、身体に悪いアルコールはいらない、といった具合だ。
彼らはいかにして、このような消費性向を育んできたのか? それは彼らが成育した時代背景に密接な関係があるという、松田氏の指摘が興味深い。
精神の自立の時期として重要な10代で、「阪神・淡路大震災」「地下鉄サリン事件」「いじめ自殺」「金融ビッグバン」などを経験。とりわけ「いじめ問題」は彼らに深刻な影を落とし、「目立たず、空気を読んで、できるだけ深く関わらず」暮らしていくことを余儀なくされた。彼らは、何より仲間からバカにされることを恐れ、周囲から「スマート」と思われたい願望が強いという。
そんな意識が「上昇志向」や「競争志向」「劣等感」を醸成し、「他人の顔色を見て行動する」「無理をしても他人からよく思われたい」という意識に繋がる。こういった時代体験から、共通の世代心理が生まれ、未来や将来への漠然とした不安が広がり、消費マインドが抑制されるというのだ。
この嫌消費世代の消費性向は、企業や社会にも大きな課題を提示し、日本経済全般にマイナスの影響を及ぼすことが懸念されている。たとえば、自動車産業の生産額の縮小に比例する雇用喪失分は、約1万3000人に相当するという。ただの節約とは違い、消費そのものが嫌いな彼らは、産業界の脅威にさえなり得る存在だ。
その一方で、これまでの世代の過剰消費とは対極にある無駄のない「コンパクト」な消費スタイルが、海外の人たちの目には「クール」に映っているという著者の持論も、目を引くものだ。
周囲の空気を読みながら上昇することを目指し、ネットワークを広げながら、競争社会でサバイバルして生きていく。そんな「嫌消費」世代が、日本の市場をどのように変えていくのか?
ただのケチではない、「クールな消費者」としての新しい日本人像が生まれたように感じるのは、享楽主義のバブル世代である筆者だけであろうか? (田島 薫)
---------------≪ 引用ここまで ≫--------------
そしてもう一本
---------------≪ 以下引用 ≫--------------
【消費にも「正義」が求められる時代――これからの「消費」の話をしよう】竹井善昭 Diamond Online
http://bit.ly/fGvfdo
それにしても「正義」が大ブームである。こんなものがブームになるとは、誰が予測できただろう? 言うまでもなく、ハーバード大学の超人気教授マイケル・サンデルの著書『これからの「正義」の話をしよう』のことである。
「正義」をテーマとしたこの哲学の本が、50万部を超えてまだ売れ続けている。今年の4月にNHK教育テレビで放送されて話題となった、同教授の講義風景を収録した番組「ハーバード白熱教室」がその火付け役。12月にはDVDも発売予定で、このサンデル人気、というか正義のブームはまだまだ続きそうだ。正直に言って、筆者も世の中の人がこれほどまでに「正義」について考えるようになるとは予想してなかった。
しかし、考えてみれば、この「正義のブーム」と「社会貢献のムーブメント」は根底のところでつながっている。「社会貢献とは、正義を問うこと」でもあるからだ。自分の生き方や生活のどこに「正義」があるのか? 社会貢献とはそんな問いに答えていく作業でもある。
アフリカの饑餓や感染症撲滅のために、あるいは勉強したくても読む本がない途上国に図書館を建てるために、寄付やボランティアをすることは自分自身の「正義」の存在証明でもある。「正義」とは決して形而上学(*)的なものではなく、僕らの日々の生活行動を決定するものである。だから、社会貢献のムーブメントは人々の消費行動にも「正義」を問いかける。それがいま話題の『エシカル消費』である。
* 実在する物事の存在を決定する根本的な原理を解明しようとする研究
「エシカル(ethical)」というのは、一般的に「倫理的」「道徳的」と訳されるが、これは日本語としては感覚的に分かりにくい訳語だと思う。むしろ、「そこに正義がある」という意味だと解釈した方がピンとくるかもしれない。『エシカル消費』とは、「そこに正義のある消費」のことである。
たとえば、フェアトレード商品を買うことは、「生産者から搾取せず適正な価格で原料を購入することは正義である」という価値観に基づいた消費行動である。児童労働によって生産された服は安くても買わないという消費行動は、「児童労働には正義はない」という価値観に基づいた消費行動である。このように、「正義」を基準とした消費行動が『エシカル消費』である。
日本ではまだまだ聞き慣れない言葉ではあるが、ロンドンでは2007年ごろからたいへんなエシカルブームになっていたらしく、当時の英エコノミスト誌の記事にも「ethical capitalism」とか「buying ethical」がどうのこうのとか、ethicalという単語が頻出していた。「ethical consumer」という雑誌も発売されている。日本では、ethicalというわかりにくい言葉のせいかいまいち理解されてこなかったが、今年になってようやく『エシカル消費』が広まってきた。
(以下略)
---------------≪ 引用ここまで ≫--------------
ところでアメリカのマズローという人が、人間の自己実現への欲求には段階がある、として、五段階で考えた、「マズローの欲求五段階説」というのがあります。

【マズローの五段階欲求】
これを見ると、一番下層にあるのが生理的欲求で、食べたいとか寒いといった生きるための欲求が初めで次に安全を求め、つぎに社会的な欲求、そして自我の欲求、最も高いところに自己実現の欲求があるとされています。
これなどと併せて、上記の記事を読むと、どうやら論点は「物を売る」ということから、「物を買う」「物を買ってもらう」という点で、買う人の視点に移っているようです。
私としては、若年層の所得が減っているのが気になっていて、所得が少ないから余計な消費もしないし、せっかく買うのだから真剣に考えるようになっている、という単純なことではないか、とも思うのです。
もっと使えるお金があれば、外食だってしたいし車だろうがバイクだろうが趣味だろうが使いたいことはたくさんあるのに、我慢した結果が消費を嫌ったり、使うときに自分を納得させる理屈を求めるという現象となって表れているだけではなのかもしれませんし。
もっとも、生存や安全はおおむね社会が保証している日本なので、そこからより上位の認識になっている人が増えているのだとしたら、喜ばしいかもしれないのですが、「物が売れない」ということに変わりはないようです。
売るために大切なことは、売る側にも、商品にも、買う側にも共感できるものが必要ですが、私はそれは「正義」ではなくて「誠実」だろうと思っていて、そこに微妙なニュアンスの違いが残ります。
買う側の人間力がついてきたのかもしれない、と思うと、ちょっと面白いのですが。