





以下、公式サイトのあらすじコピペです。====ここから
1944年10月、アウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所。サウルは、ハンガリー系のユダヤ人で、ゾンダーコマンドとして働いている。ゾンダーコマンドとは、ナチスが選抜した、同胞であるユダヤ人の死体処理に従事する特殊部隊のことである。彼らはそこで生き延びるためには、人間としての感情を押し殺すしか術が無い。
ある日、サウルは、ガス室で生き残った息子とおぼしき少年を発見する。少年はサウルの目の前ですぐさま殺されてしまうのだが、サウルはなんとかラビ(ユダヤ教の聖職者)を捜し出し、ユダヤ教の教義にのっとって*手厚く埋葬してやろうと、収容所内を奔走する。そんな中、ゾンダーコマンド達の間には収容所脱走計画が秘密裏に進んでいた・・・。 *ユダヤ教では火葬は死者が復活できないとして禁じられている。
====コピペ終わり。
“息子とおぼしき少年”ってのがキモ。……それにしても、終始揺れる画面に、激疲れ、、、。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
もうすぐアカデミー賞の発表ですねぇ。本作も、外国語映画賞の本命だそうで。アカデミー賞、、、あんまし世間が騒ぐほどの価値を感じませんけれども、一応チェックはしちゃいます、、、。
で、感想ですが。世間は絶賛の嵐の様ですが、、、正直、私はあんまりグッときませんでした。そもそも、“息子とおぼしき少年”ってのが、どうしても、見終わって何日か経った今になっても、やっぱり腑に落ちないのです。
ここから、ネタバレバレになりますので、悪しからず(これからご覧になる予定の方は、お読みにならない方が良いです)。
どうしてサウルは、本当の息子ではない少年を“息子”と思って、あそこまでユダヤ教式の埋葬にこだわったのか。1)あの時点でサウルは既に精神的におかしくなっていたのか、2)息子と仮定して行動することで生きる意味を見出そうとしたのか、3)実は本当に同じくらいの年齢の息子がいて少年がよく似ていたのか、はたまた、4)本当はホントに彼の実の息子だったのか。
まあ、どれでも当てはまりそうな気がします。どう解釈しても良いと思います。私は、3)と4)はあり得ないと思いました。明確な根拠はないけれど、周囲の者たちに「お前に息子はいないだろう」と言われていることや、彼の少年の埋葬への執着ぶりが実の息子へのそれと考えるには違和感を覚えるものがあったことなどが理由といえば理由ですが、もっと直感的なモノです。
本当に血を分けた息子であれば、、、何と言うか、埋葬方法よりも、少年の遺体そのものに執着する気がしたというか。サウルは少年の遺体を持ち歩くんだけど、それがどうも、、、息子への愛というよりは、ユダヤ教信徒としての教義への忠誠みたいなものに見えたんです。
しかし、一方で彼は、ゾンダーコマンドとして、同胞の虐殺作業を担っている。これは教義に対する最大の背信行為ではないのか……? そこに、矛盾というほどの明確なものではないけれども、何かこう、、、とにかく腑に落ちないものがあったのです。
唯一、納得する解釈は1)の、サウルはもう精神的におかしくなっていた、というものですが、、、。なんか、それも違うような気がしてしまうし。
パンフの監督のインタビュー記事は一応隅々まで読みましたけれど、ううむ、、、ピッタリの言葉が見当たらないけれど、イマイチ私にはやはり“腑に落ちない”です。
別に、どの映画も腑に落ちなければいけないわけじゃないし、腑に落ちなくても、何か分からないけどグッとくる、ってのも確かにあります。でも、これは、腑に落ちないし、グッとも来なかった、、、。
こういう、ストーリー自体はフィクションながら、確かな記録を基に作られた映画はその部分では説得力があります。ゾンダーコマンドなる存在が何をしていたのか、絶滅収容所がどういうものだったのか、収容されていた人々が監視の目を逃れてどんな行動をとっていたのか、、、さんざん今まで映像や書物で見聞きして来たけれども、やはり圧倒的なものがありました。
映像も、既にさんざん批評されていますが、特殊な撮影方法で、サウルの視点や行動を集中的にフォーカスしているというのは、確かに斬新なんでしょう。手振れの映像は、結構平気な方ですが、本作はかなり疲れました。
ちょっと謎めいたストーリー、圧倒的な歴史的事実、斬新な撮影・演出、と三拍子揃えば、世間の注目度が上がるのも当然でしょう。作品の価値がどの程度のものか、私ごときが云々言うことじゃありません。きっと素晴らしい作品なのでしょう。というか、制作者のクリエイティブ精神は素晴らしいとは確かに思うのです。でも、心にはそれに比例した響きがなかったのです。どうにも不思議な感覚です。
本作を見ている間、特に中盤以降、頭の片隅で『炎628』がありました。何か似ているなぁ、、、と。何が、と言われると難しいのですが、絶望の描き方みたいなものが、、、ですかね。フリョーラの顔が脳裏をチラついていました。で、監督のインタビューを読んだら『炎628』が大きなインスピレーションになった、と言っているので、私の感覚はものすごいハズレじゃないのか、、、と思ったら却って混乱した気がします。ま、大したことじゃないんですが。
ラストのサウルの笑顔が印象的。
★★ランキング参加中★★
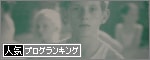
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます