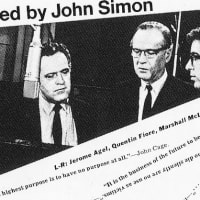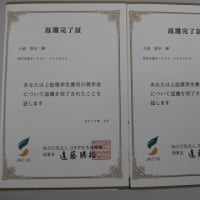ジェイン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生 / 新版』山形浩生訳, 鹿島出版会、2010.
都市論の古典。原著は1961年で、著者は当時ニューヨークに在住してジャーナリストと主婦をやっていた。公園を横断する幹線道路計画に反対してニューヨーク市と対立し、地元住民をまとめあげて勝利を収めたこともあるという。4年前に、背景をよく知らないまま採りあげた『市場の倫理 統治の倫理』(参考)の著者でもある。
内容は徹頭徹尾、当時主流だった都市計画論に対しての反論である。都市の過密を問題視し、郊外にベッドタウンを設けるか居住用の高層建築を広い区域に点在させるかして人口密度を低め、商業用途や居住用途といった機能別に都市を分割するというのがそれである。エベネザー・ハワードの田園都市論や、ル・コルビュジエの「輝く都市」が代表的である。こうした都市計画論は当時の行政に実際に採用されて、アメリカではそれに従った都市改造が進められていた。
本書の中で、そうした都市計画はうまくいっていないと著者は指摘する。人口密度を低めると、街路や公園に監視の目が行き届かなくなり、治安が悪化して近隣地域が荒廃するという。また、都市の機能分割は、それぞれの地域を使用する人の多様性を低めて都市の面白みを減少させるとも。結果、やはりそれは荒廃につながるという。それに対して、美的には計画都市に劣るかもしれないが、多少ごちゃごちゃして猥雑でもいいから、多様性のある活き活きとした都市を著者は賞賛するのである。その他、スラムの扱いや住宅補助、都市計画をめぐる経済についても扱われている。
難点があるとしたら、写真や地図など図版がほとんどないことである。当時のアメリカ大都市のイメージを日本人に理解させるには必要なものなのだが、訳者によれば原著者のエージェントがそういったものの掲載を禁じたとのことである。実際、僕に分からなかったのが、大都市が「荒廃」するというその程度である。それは凄まじいものなのだろうか。日本にいると、地方小都市にあるシャッター街といった寂れ方は頭に浮かぶのだが、東京や名古屋で多少閑散とした場所を通っても、不良少年に遭遇して身ぐるみ剥がれる危険があるとは思わない。街が壊れることの深刻さについて、読んでいてどうにも掴めなかった点である。
訳者の解説はとても親切で、著者の見識や本書の都市論としての評価と影響力を、その不備の指摘も含めて公平に伝えている。力作。
都市論の古典。原著は1961年で、著者は当時ニューヨークに在住してジャーナリストと主婦をやっていた。公園を横断する幹線道路計画に反対してニューヨーク市と対立し、地元住民をまとめあげて勝利を収めたこともあるという。4年前に、背景をよく知らないまま採りあげた『市場の倫理 統治の倫理』(参考)の著者でもある。
内容は徹頭徹尾、当時主流だった都市計画論に対しての反論である。都市の過密を問題視し、郊外にベッドタウンを設けるか居住用の高層建築を広い区域に点在させるかして人口密度を低め、商業用途や居住用途といった機能別に都市を分割するというのがそれである。エベネザー・ハワードの田園都市論や、ル・コルビュジエの「輝く都市」が代表的である。こうした都市計画論は当時の行政に実際に採用されて、アメリカではそれに従った都市改造が進められていた。
本書の中で、そうした都市計画はうまくいっていないと著者は指摘する。人口密度を低めると、街路や公園に監視の目が行き届かなくなり、治安が悪化して近隣地域が荒廃するという。また、都市の機能分割は、それぞれの地域を使用する人の多様性を低めて都市の面白みを減少させるとも。結果、やはりそれは荒廃につながるという。それに対して、美的には計画都市に劣るかもしれないが、多少ごちゃごちゃして猥雑でもいいから、多様性のある活き活きとした都市を著者は賞賛するのである。その他、スラムの扱いや住宅補助、都市計画をめぐる経済についても扱われている。
難点があるとしたら、写真や地図など図版がほとんどないことである。当時のアメリカ大都市のイメージを日本人に理解させるには必要なものなのだが、訳者によれば原著者のエージェントがそういったものの掲載を禁じたとのことである。実際、僕に分からなかったのが、大都市が「荒廃」するというその程度である。それは凄まじいものなのだろうか。日本にいると、地方小都市にあるシャッター街といった寂れ方は頭に浮かぶのだが、東京や名古屋で多少閑散とした場所を通っても、不良少年に遭遇して身ぐるみ剥がれる危険があるとは思わない。街が壊れることの深刻さについて、読んでいてどうにも掴めなかった点である。
訳者の解説はとても親切で、著者の見識や本書の都市論としての評価と影響力を、その不備の指摘も含めて公平に伝えている。力作。