カトリック宝塚教会の記事で、今更ながらではあるのですが、村野藤吾の才能に驚嘆したことを書きました(外観編・内部編)。そして先日、午後から時間が取れたこともあって関西大学千里山キャンパスに村野藤吾建築を見に出かけました。
同じ関西大学関係では3月の「関西洋風建築めぐり講座」で天六キャンパスを見学し(ここも素晴らしかったのですが、ブログには未アップのままです)、この時に千里山キャンパスに残る村野藤吾建築のことも少し紹介頂きました。
阪急の関大前で下車して徒歩数分、新入生も多いのでしょうか、登下校の若い男女で大にぎわいの中、広大な敷地の千里山キャンパスに到着しました。このキャンパス内に足を踏み入れるのは初めてです。村野藤吾は約30年間に40棟ほどの建物の設計に携わったとのことで、減りつつあるとはいえまだ複数の建物が現存しています。
まずは円神館(現・ITセンター S39)です。最初、円神館が目に入ったときは、円形の列柱に支えられた神殿風で名古屋で見た「旧稲葉地配水塔」と似ているなあとは思ったものの、今いちピンと来ず。しかし、後でもう一度じっくりと眺めてなかなか素晴らしいことが分かりました。これについては続きで書く予定です。

そして、KUシンフォニーホール(旧・特別講堂 S37年) 、東体育館(S38)を眺めた後、今回一番期待していた「簡文館」(S30)へ。


簡文館は元々、S3年竣工の旧・千里山図書館をS30年に増築したものです。最後の2枚の写真にS3年竣工部分が写っていますが、そちらは古い学校建築に見られるようなクラシカルなデザインです。一方、村野藤吾設計部分は円形であることが最大の特徴であるものの、頂部や窓まわりのデザイン、タイルの使い方やデザイン・色合いなどが実に印象的です。また、RC構造をデザイン的に見せているのも見事です。この日は良い天気で、青空をバックに美しい姿を見せてくれていました。今見ても古さは全くと言ってよいほど感じず、逆にすごく斬新なデザインに思えます。この建物が50年以上も前のものとは!









現在、建物の足元はかなり壁で囲まれていますが、元は吹き放ちのピロティになっていたそうで、もっと浮遊感があったそうです。その頃の姿を見たかったですね。現在ここは博物館になっており、この日も見学可能でした。内部(これも味わいがありました)および他の建物については続きの記事で書きたいと思います。それにしても凄いなあ。。。素晴らしいなあ。。。











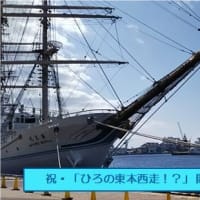









そうか、みんな村野藤吾だったのか。
改めて知りました。ITセンターなど、「ああ、新しい建物を建てたんやな」と思ったぐらいで。
関大には何度か足を運んでいますが(もちろん建築探訪ではなく)、古い建物だとは気付いてませんでした。惜しいことをしました。
この簡文館、そしてタイル画、とても素敵ですね。
関大にはかなりの数の村野藤吾関係建物があったようです。
いずれも建築家ならではのイマジネーションにあふれた建物だと思います。
>ITセンターなど、「ああ、新しい建物を建てたんやな」と思ったぐらいで・・・
そうですね。私も一見すると新しい建物のように思いましたから。
建物によっ、て解体されたり、改築・増築されたり手が入ったりしてオリジナルと違ってきたり、逆にまたオリジナルに近い状態に戻ったりと色々な物語があるようです。
簡文館の大きなタイル画は、解体された他の建物(村野物件)からはがしてきたもののようでした。
※自宅PCがトラブルで、続きがしばらくアップできないかもです(涙)。
簡文館のタイル画は、隣接してあった法文学舎1号館のエントランスホールにあったものです。
エントランスホールには、村野御得意の緩い勾配の斜路があり、
その斜路に近いところにあのタイルはあったのです。
斜路の支柱(とはめ込まれた定礎)は、モニュメントとして残されていると思います。
コメント、ありがとうございます。
法文学舎1号館のエントランスホールにあった頃のことは知らないのですが、関大校舎の内部などに村野色が残っていないかもう一度探訪したいと思います。