 かなり日数が経ってしまいましたが、9月21日にザ・シンフォニーホールで開催された京都市交響楽団・大阪特別講演に行ってきました。座席は2F AA-17でした。
かなり日数が経ってしまいましたが、9月21日にザ・シンフォニーホールで開催された京都市交響楽団・大阪特別講演に行ってきました。座席は2F AA-17でした。
指揮 :広上淳一(常任指揮者)
ピアノ:山本貴志
①デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」
②ラフマニノフ:パガニーニの主題による
狂詩曲
③リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲
④ラヴェル:ボレロ
※アンコール
ブラームス:ハンガリー舞曲 第6番<o:p></o:p>
曲目ごとの大まかな感想・評価です。
①:△ ②:〇 ③:◎ ④:◎<o:p></o:p>
プログラムの後半に演奏される曲やよく知っている曲ほど印象に残るのは致し方なしですね。曲目ごとにもう少し細かい感想を書くと・・・
①大太鼓の強打や鉄琴・ピッコロの高音などが印象的。<o:p></o:p>CDによる予習は3回くらいで、耳になじむところまでになっていなかったのがちょっと残念でした。
②予習は部分的に聴いたりも含めて1~2回といったところ。完全な予習不足でしたが、良い曲だと思いました。山本貴志さんは最初、鍵盤に覆い被さるような弾き方でちょっとビックリ。
この日のコンサートでは、ピアノソロとオケの協奏曲的な面と”競争”的な面の両方を併せもった感じがしました。指揮の広上さんは、オケをグーッと引っ張って大きな音を引き出し、それを山本氏に受け渡すというか放り投げるような指揮ぶりが印象的でした。CMなどでもよく使われたり、単独でとり上げられることも多い有名な第18変奏(アンダンテ・カンタービレ)はやはり飛び抜けて美しいメロディで、ピアノもオケも素晴らしかったです。
ピアノ以外では、オーボエソロ(美音!)→クラリネットソロ→ホルンソロの音の受け渡しやコンマス氏(若い泉原氏)のソロなどが印象的でした。演奏後はかなり盛大な拍手があり、山本氏も4回くらいステージに引っ張り出されましたが、アンコールはありませんでした。熱演で疲れておられたとは思いますが、もう少し拍手を続ければアンコールピースが聴けたのでしょうか?
③曲も美しいですし、迫力もあって、コンサートでは嬉しいプログラム。③④はよく知っていると考えて予習なしでした。出だしは割とゆっくり目のテンポでしたが、次第に白熱。全曲を通じて、コンマス氏のソロ、クラリネットトップ、イングリッシュホルンが素晴らしかったです。またオーボエトップの方はこの日は終始美音で見事な演奏でした。タンバリン、カスタネットなども印象的。
この曲が切れ目無く演奏されることは一応知っていましたが、予習なしもあって考えていたよりも短い感じがしてちょっとビックリ!もっとこの音の渦の中に浸っていたかったですね。広上さんは曲の途中、指揮台の上で飛んだり跳ねたり、踊ったりしておられました(笑)。見ていても実に楽しかったです。
④コンサートで「ボレロ」を実際に聴いたのは3回目くらいでしょうか。かすかな微弱音~最強音まで的確で素晴らしいリズムを刻んだスネアドラム。美しい音色を聴かせてくれた管楽器群のソロ、それをしっかりと支えた弦。期待通りに、いや期待以上に素晴らしかったです。
ソロはフルートから始まりますが、落ち着いた美しい音色が響き渡りました。後のソロ奏者もそのペースにうまく乗ったのか、全体的に非常に良かったです。メロディを奏でる楽器順は次のようでした(Wikipediaより)。
1.第1フルート
2.第1クラリネット
3.第1ファゴット
4.小クラリネット
5.オーボエダモーレ
6.第1フルート、第1トランペット(弱音器付き)
7.テナーサクソフォーン
8.ソプラニーノサクソフォーン→ソプラノサクソフォーン
(今日ではソプラノサクソフォーン1本で演奏)
9.ピッコロ(ホ長調とト長調)、ホルン(ハ長調)、チェレスタ(ハ長調)
10.オーボエ、オーボエ・ダモーレ(ト長調)、コーラングレ、第1,2クラリネット
11.第1トロンボーン
以下省略
私が特に印象に残ったのは第1フルート、オーボエダモーレ、テナーサクソフォーン、第1トロンボーンなどです。客演だったサクソフォーンの2人(女性)にはソロパートが終わると広上氏が親指を立ててgood!ポーズ。これもなかなか良かったです。
演奏後、お客さんの一番の拍手を浴びたのは、もちろんスネアドラム(女性)でした。聴衆だけでなく仲間からも大喝采が送られました。次いでお客さんの拍手が大きかったのはトロンボーントップだったでしょうか。楽器のことはよく分かっていませんが、トロンボーンで細かく正確な音程を刻むのはなかなか難しいと思われます。ずーっと以前、TV放映で某世界的オケの「ボレロ」でトロンボーンが音を外したのを聴いたことがあり(何とか挽回しましたが)、私もトロンボーンソロの前はちょっとドキドキしていました。しかし、ちょっとコミカルな感じもあるBパート(?)のメロディを見事に吹ききって天晴れ!です。
広上さんの指揮は振りが大きく、身体全体(特に上半身)を使って&動き回っての指揮ぶりでした。「ボレロ」の前半以外は、結構タイミングなどの指示を細かく出されていました。オケとの信頼関係も抜群なようですし、素晴らしい指揮者ですね。この日も素晴らしいコンサートを堪能してオケメンバーの方々の見送りを受けながら、気持ちよくホールを後にしました。















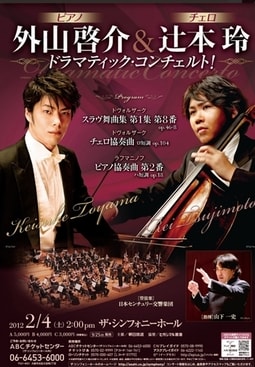 最近は年に2~3回、クラシックコンサートに行っており(昨年は4回:
最近は年に2~3回、クラシックコンサートに行っており(昨年は4回: これは全国から約3000人のミュージシャンが高槻に大集合し、2日間にわたって全43会場でジャズ他のパフォーマンスを繰り広げるものです。今回が12回目で、いわゆる興行イベントではなく、市民(普通の人々)による、市民のための、手作りのお祭りだそうです。
これは全国から約3000人のミュージシャンが高槻に大集合し、2日間にわたって全43会場でジャズ他のパフォーマンスを繰り広げるものです。今回が12回目で、いわゆる興行イベントではなく、市民(普通の人々)による、市民のための、手作りのお祭りだそうです。



