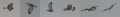■2011/2/22(火)12:07-15:57【天気】晴れ
【場所】蕪栗沼南側田圃
【種名】カワウ,ダイサギ,コサギ,アオサギ,マガン,オオハクチョウ,コハクチョウ,マガモ,カルガモ,コガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ミコアイサ,カワアイサ,ミサゴ1,トビ,オオタカ1,ノスリ3,チュウヒ1,タンチョウ1,タゲリ++,イソシギ1,オオハシシギ5,キジバト,ハクセキレイ,ツグミ,ホオジロ,カシラダカ,オオジュリン,スズメ,ムクドリ,コクマルガラス暗色型1,ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス(14科35種)
【メモ】北上川も相川も波伝谷もさらに伊豆沼も普通種だけだったので,蕪栗沼に行けば何かしらいるかもしれないと,白鳥地区と沼に行ったが,オオタカの幼鳥1羽がいるだけで,マガンもオオヒシクイもいない。田圃にかろうじてマガンがいた程度だった。がっかりして,今日は仕方がないと最後に田圃道を走っていたら,これまで見逃していたタンチョウがいた。春夏はケリの番がいる田圃で採餌していた。採餌する姿がなかなかいいし,よく鳴いていたので,EOS7Dで動画を撮影した。ピントが合うか気になったが,しっかり合っていた。三脚がないので,いつも手持ちだが,モニターを見ながらの撮影というのは,ちょとたいへんだった。そのうちタンチョウは,南側田圃の真ん中の道のすぐ脇に採餌しながら移動したので,遠回りして順光になる位置で畦に座り込んでこちらにやってくるのを例によって待っていた。すると,どんどんこちらへやってくる。ドジョウも何回かつかまえて食べていた。タンチョウはただこの辺にいるのではなく,そういう餌がある環境だからいるのであって,餌がなかったり,塒がなかったりすれば,ここにはいないはずだ。そう考えると,タンチョウが2年続けて来る蕪栗沼と周辺環境に視点をおいて鳥を見ることが,鳥たちをよりよく理解することになるのだと思う。自分自身,昨年,北浦の田圃にタンチョウが来た時にはあまり,思わなかったが,実家の田圃もある身近な田圃地帯でタンチョウがドジョウを食べて越冬しているということは,とてもすてきなことなのだ。ちなみに歌川広重の「名所江戸百景」冬の部「蓑輪金杉三河しま」や,同じく「東海道五十三次」の「原」にはそれぞれ2羽のタンチョウとその周辺環境が描かれている。ずっと昔はタンチョウは身近な鳥だったのだろう。蕪栗沼南側の田圃でも,ケリがよくいる用水路あたりの風景はとてもいい。この用水路は,両側や底が今では珍しいがコンクリートではない。オオハシシギが,堤からやってきてここでドジョウを食べていたのもなるほどという感じだ。
さて,本当に帰る時間になって,堤を見ていくと,オオハシシギが5羽いた。2羽はいなくなっていた。前に見た時も2羽はペアで他の群れと離れて採餌していたので,どのへんにでもいるのかもしれない。
【写真】






■ドジョウを捕まえたタンチョウ。嘴にドジョウが絡みついている。



■しきりに餌を探して田圃を歩き回っている。












■畦に座って待っていると,どんどん近づいてきた。横位置では入らなくなり,縦位置で撮影した。



■最終的に4mくらいまで近づいてきて,そこから右の方に餌を探しながら歩いて行った。何しろ大型なので,せわしない感じは全くしない。時々,立ってはグルルグルルとよく鳴いていた。/蕪栗沼のオオタカ若鳥
Copyright(C)2011 Shigenobu Aizawa All Rights reserved.
【場所】蕪栗沼南側田圃
【種名】カワウ,ダイサギ,コサギ,アオサギ,マガン,オオハクチョウ,コハクチョウ,マガモ,カルガモ,コガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ミコアイサ,カワアイサ,ミサゴ1,トビ,オオタカ1,ノスリ3,チュウヒ1,タンチョウ1,タゲリ++,イソシギ1,オオハシシギ5,キジバト,ハクセキレイ,ツグミ,ホオジロ,カシラダカ,オオジュリン,スズメ,ムクドリ,コクマルガラス暗色型1,ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス(14科35種)
【メモ】北上川も相川も波伝谷もさらに伊豆沼も普通種だけだったので,蕪栗沼に行けば何かしらいるかもしれないと,白鳥地区と沼に行ったが,オオタカの幼鳥1羽がいるだけで,マガンもオオヒシクイもいない。田圃にかろうじてマガンがいた程度だった。がっかりして,今日は仕方がないと最後に田圃道を走っていたら,これまで見逃していたタンチョウがいた。春夏はケリの番がいる田圃で採餌していた。採餌する姿がなかなかいいし,よく鳴いていたので,EOS7Dで動画を撮影した。ピントが合うか気になったが,しっかり合っていた。三脚がないので,いつも手持ちだが,モニターを見ながらの撮影というのは,ちょとたいへんだった。そのうちタンチョウは,南側田圃の真ん中の道のすぐ脇に採餌しながら移動したので,遠回りして順光になる位置で畦に座り込んでこちらにやってくるのを例によって待っていた。すると,どんどんこちらへやってくる。ドジョウも何回かつかまえて食べていた。タンチョウはただこの辺にいるのではなく,そういう餌がある環境だからいるのであって,餌がなかったり,塒がなかったりすれば,ここにはいないはずだ。そう考えると,タンチョウが2年続けて来る蕪栗沼と周辺環境に視点をおいて鳥を見ることが,鳥たちをよりよく理解することになるのだと思う。自分自身,昨年,北浦の田圃にタンチョウが来た時にはあまり,思わなかったが,実家の田圃もある身近な田圃地帯でタンチョウがドジョウを食べて越冬しているということは,とてもすてきなことなのだ。ちなみに歌川広重の「名所江戸百景」冬の部「蓑輪金杉三河しま」や,同じく「東海道五十三次」の「原」にはそれぞれ2羽のタンチョウとその周辺環境が描かれている。ずっと昔はタンチョウは身近な鳥だったのだろう。蕪栗沼南側の田圃でも,ケリがよくいる用水路あたりの風景はとてもいい。この用水路は,両側や底が今では珍しいがコンクリートではない。オオハシシギが,堤からやってきてここでドジョウを食べていたのもなるほどという感じだ。
さて,本当に帰る時間になって,堤を見ていくと,オオハシシギが5羽いた。2羽はいなくなっていた。前に見た時も2羽はペアで他の群れと離れて採餌していたので,どのへんにでもいるのかもしれない。
【写真】






■ドジョウを捕まえたタンチョウ。嘴にドジョウが絡みついている。



■しきりに餌を探して田圃を歩き回っている。












■畦に座って待っていると,どんどん近づいてきた。横位置では入らなくなり,縦位置で撮影した。



■最終的に4mくらいまで近づいてきて,そこから右の方に餌を探しながら歩いて行った。何しろ大型なので,せわしない感じは全くしない。時々,立ってはグルルグルルとよく鳴いていた。/蕪栗沼のオオタカ若鳥
Copyright(C)2011 Shigenobu Aizawa All Rights reserved.