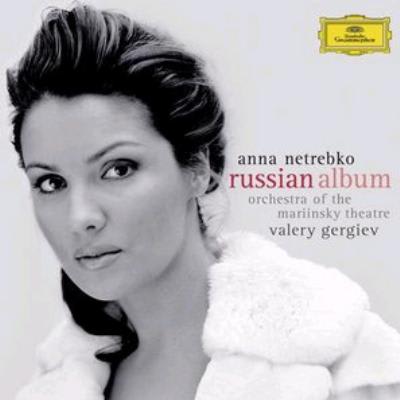やっと、私のスピーカーから鳴り響いた。この時を、どのくらい長い年月待ち続けていたか!
ヴェルディの歌劇「ドン・カルロ」の5幕版による全曲CDから第1幕の「フォンテンブローの森の場」
フラヴィアーノ・ラボーのドン・カルロ、アントニエッタ・ステッラのエリザベッタ。そしてガブリエーレ・サンティーニ指揮ミラノ・スカラ座管弦楽団・合唱団による演奏。
ドイツ・グラモフォン原盤の1961年の録音。
歌劇「ドン・カルロ」は「フォンテンブローの森の場」を省いた4幕版での公演、また録音が多いですが、私は、このオペラは5幕版でなくてはと強く思っています。
フォンテンブローの森の場でのカルロとエリザベッタとの出会い、喜び。そしてエリザベッタとカルロの父フィリッポ2世との婚約が決まった知らせ、悲しみと絶望。
この長大な人間ドラマのオペラの全ては、ここから始まっているのである。私の変なこだわりかもしれませんが、これを聴かなかったら、私にとって、このオペラを聴く喜びは半減である。
そして、このオペラの5幕版の魅力を私に伝えてくれたのはサンティーニ指揮ミラノ・スカラ座管弦楽団・合唱団による録音のレコードでした。それも、たった1組の中古レコード。
私が大学生の時、カラヤン指揮による全曲レコード(4幕版)が発売され、フレーニ、ギャウロフ、カップッチルリという大好きなオペラ歌手が勢揃いだったので当時貧乏学生の私にとって大出費でしたが、カラヤン盤を購入しました。まだまだ、このオペラに関して知識がほとんど無かった私はカラヤン盤の解説書を読んでいて5幕版のことを知り、ぜひ聴いてみたい強く思いましたが、何せ金欠病!
それでも、どうしてもと思い、当時、数奇屋橋にあった中古レコード店の「ハンター」でサンティーニ指揮のグラモフォン盤(国内盤)を捜しだして購入。しばらくは、金銭面では、たいへんな生活だった!
余談ながらCDの時代になって、ネットで往年の名演奏の録音がたいへんな安価で手に入る時代になりましたが、私の学生時代を思い出すと、たいへん複雑な気持ちになります。
購入した中古レコードはケースに薄い布が貼られた立派なアルバムで、おそらく、このレコードは、この録音が我が国で初めて発売された時のアルバムのようである。
そして、この中古レコードは思い入れも強いですが私の宝として大切に聴いてきました。そして、この録音はイタリア・オペラの数多い録音の中で最上位の録音であると、私は固く信じています。
CDの時代になって、私の持っていた、ほとんどのレコードは我が家の物置部屋に移してしまいましたが、この中古レコードは現在までCDと一緒にいます。
しかし、CDの時代になったからには、ぜひともこの録音もCDで聴いてみたいと思っていましたが、何故か発売されない!いや、発売はされましたがドイツ・グラモフォンのスカラ座でのヴェルディのオペラ全曲録音の全てをセットにした膨大で高額なセット物だった。内容的に私が持っているCDと重複している録音も多く、手が出しにくい、手が出ない不親切な代物だった。そして、この20余年、単独で発売される気配は全くなくレコード会社に怒りすら感じていました。
そんな状態でしたが、最近、ネットでいろいろ見ていたらイタリアのレーベルでグラモフォンのライセンス盤がリリースされているのを大発見して、直ぐに手配し、そしてCDが届きました。価格は1900円だった・・・
歌劇「ドン・カルロ」は主役が揃ってはじめて緊迫したドラマになる難しいオペラですが、歌手が揃った時の迫力、物凄さは言語に絶するものがあります。このオペラの長さを忘れさせてくれるものがあり、ヴェルディのオペラの醍醐味があります。
この録音ではボリス・クリストフ、アントニエッタ・ステッラ、フラヴィアーノ・ラボー、フィオレンツァ・コッソット、エットーレ・バスティアニーニと言った名歌手たちが最高のヴェルディの歌唱を聴かせてくれます。そしてミラノ・スカラ座のオケとコーラスの輝かしい演奏!
私にとって、かけがえのない録音。
正に私の一生の宝!
ヴェルディ万歳!
ヴェルディの歌劇「ドン・カルロ」の5幕版による全曲CDから第1幕の「フォンテンブローの森の場」
フラヴィアーノ・ラボーのドン・カルロ、アントニエッタ・ステッラのエリザベッタ。そしてガブリエーレ・サンティーニ指揮ミラノ・スカラ座管弦楽団・合唱団による演奏。
ドイツ・グラモフォン原盤の1961年の録音。
歌劇「ドン・カルロ」は「フォンテンブローの森の場」を省いた4幕版での公演、また録音が多いですが、私は、このオペラは5幕版でなくてはと強く思っています。
フォンテンブローの森の場でのカルロとエリザベッタとの出会い、喜び。そしてエリザベッタとカルロの父フィリッポ2世との婚約が決まった知らせ、悲しみと絶望。
この長大な人間ドラマのオペラの全ては、ここから始まっているのである。私の変なこだわりかもしれませんが、これを聴かなかったら、私にとって、このオペラを聴く喜びは半減である。
そして、このオペラの5幕版の魅力を私に伝えてくれたのはサンティーニ指揮ミラノ・スカラ座管弦楽団・合唱団による録音のレコードでした。それも、たった1組の中古レコード。
私が大学生の時、カラヤン指揮による全曲レコード(4幕版)が発売され、フレーニ、ギャウロフ、カップッチルリという大好きなオペラ歌手が勢揃いだったので当時貧乏学生の私にとって大出費でしたが、カラヤン盤を購入しました。まだまだ、このオペラに関して知識がほとんど無かった私はカラヤン盤の解説書を読んでいて5幕版のことを知り、ぜひ聴いてみたい強く思いましたが、何せ金欠病!
それでも、どうしてもと思い、当時、数奇屋橋にあった中古レコード店の「ハンター」でサンティーニ指揮のグラモフォン盤(国内盤)を捜しだして購入。しばらくは、金銭面では、たいへんな生活だった!
余談ながらCDの時代になって、ネットで往年の名演奏の録音がたいへんな安価で手に入る時代になりましたが、私の学生時代を思い出すと、たいへん複雑な気持ちになります。
購入した中古レコードはケースに薄い布が貼られた立派なアルバムで、おそらく、このレコードは、この録音が我が国で初めて発売された時のアルバムのようである。
そして、この中古レコードは思い入れも強いですが私の宝として大切に聴いてきました。そして、この録音はイタリア・オペラの数多い録音の中で最上位の録音であると、私は固く信じています。
CDの時代になって、私の持っていた、ほとんどのレコードは我が家の物置部屋に移してしまいましたが、この中古レコードは現在までCDと一緒にいます。
しかし、CDの時代になったからには、ぜひともこの録音もCDで聴いてみたいと思っていましたが、何故か発売されない!いや、発売はされましたがドイツ・グラモフォンのスカラ座でのヴェルディのオペラ全曲録音の全てをセットにした膨大で高額なセット物だった。内容的に私が持っているCDと重複している録音も多く、手が出しにくい、手が出ない不親切な代物だった。そして、この20余年、単独で発売される気配は全くなくレコード会社に怒りすら感じていました。
そんな状態でしたが、最近、ネットでいろいろ見ていたらイタリアのレーベルでグラモフォンのライセンス盤がリリースされているのを大発見して、直ぐに手配し、そしてCDが届きました。価格は1900円だった・・・
歌劇「ドン・カルロ」は主役が揃ってはじめて緊迫したドラマになる難しいオペラですが、歌手が揃った時の迫力、物凄さは言語に絶するものがあります。このオペラの長さを忘れさせてくれるものがあり、ヴェルディのオペラの醍醐味があります。
この録音ではボリス・クリストフ、アントニエッタ・ステッラ、フラヴィアーノ・ラボー、フィオレンツァ・コッソット、エットーレ・バスティアニーニと言った名歌手たちが最高のヴェルディの歌唱を聴かせてくれます。そしてミラノ・スカラ座のオケとコーラスの輝かしい演奏!
私にとって、かけがえのない録音。
正に私の一生の宝!
ヴェルディ万歳!