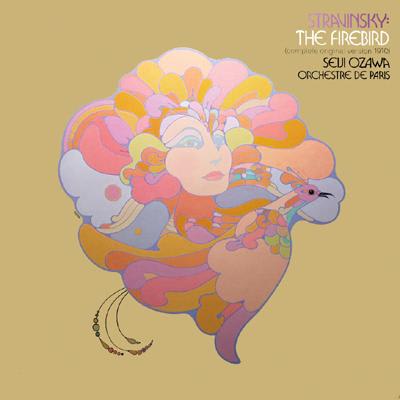①シベリウス 合唱作品集 セット・ムルト指揮ドミナンテ合唱団(2009年、2010年録音 BIS盤)
②シベリウス 組曲「恋人」作品14(弦楽合奏版) ユハニ・ラミンマキ指揮エスポー市室内管弦楽団(1989年録音 FINLANDIA盤)
③シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26 パーヴォ・ベルグルンド指揮ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団(1986年録音 EMI盤)
当ブログ休止中によく聴いていたのはシベリウスとブルックナーの作品。
特に私自身、最近、シベリウスに傾倒している。シベリウスと言えば交響曲ですが、最近、声楽曲や合唱曲に興味が出てきました。
本当は全集で手に入れたかったのですが、当方、現在、財政難である。
そんな時、フィンランドの合唱団であるドミナンテ合唱団によるシベリウス合唱曲集の1枚のCDが届きました。この合唱団、フィンランド屈指の名門合唱団とのこと。
交響曲にはない、素朴で、何か心が洗われるような作品の数々。ますますハマりそうである。
私は昔から弦楽アンサンブルの演奏による組曲「恋人」と言う作品が大好きで、作品の持つ、はかなさ、可憐さに聴くたびに心が震えていました。
この組曲「恋人」のオリジナルが合唱曲であるということは知っていたのですが、まだ聴いたことがなかった。
そして、今回届いたCDの1曲目に、この合唱曲が含まれていて、やっと聴くことが出来たという喜びが大きい。それもアカペラである。
本当に、何か遠い昔に思いを馳せさせるような心に沁みる作品。
また、このCDの最後には、こちらもアカペラによる「フィンランディア賛歌」が収録されている。
聴けば直ぐに分かるのですが、旋律は、あの交響詩「フィンランディア」の中間部である。
あの中間部がアカペラによって歌われているのである。大編成のオーケストラによる交響詩「フィンランディア」とは別世界である。
この「フィンランディア賛歌」、感動ものである。
残念なのは輸入盤なので対訳がないこと。
歌詞が、分からなくても、これだけ心に沁みるのですから、もし歌詞の意味が分かったら、もっと感銘を深くするのは間違いないでしょう。
「恋人」や「フィンランディア賛歌」だけでも歌詞を知りたいものです。
しかし、本当に、いいCDが手に入ったものと喜んでいます。

②シベリウス 組曲「恋人」作品14(弦楽合奏版) ユハニ・ラミンマキ指揮エスポー市室内管弦楽団(1989年録音 FINLANDIA盤)
③シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26 パーヴォ・ベルグルンド指揮ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団(1986年録音 EMI盤)
当ブログ休止中によく聴いていたのはシベリウスとブルックナーの作品。
特に私自身、最近、シベリウスに傾倒している。シベリウスと言えば交響曲ですが、最近、声楽曲や合唱曲に興味が出てきました。
本当は全集で手に入れたかったのですが、当方、現在、財政難である。
そんな時、フィンランドの合唱団であるドミナンテ合唱団によるシベリウス合唱曲集の1枚のCDが届きました。この合唱団、フィンランド屈指の名門合唱団とのこと。
交響曲にはない、素朴で、何か心が洗われるような作品の数々。ますますハマりそうである。
私は昔から弦楽アンサンブルの演奏による組曲「恋人」と言う作品が大好きで、作品の持つ、はかなさ、可憐さに聴くたびに心が震えていました。
この組曲「恋人」のオリジナルが合唱曲であるということは知っていたのですが、まだ聴いたことがなかった。
そして、今回届いたCDの1曲目に、この合唱曲が含まれていて、やっと聴くことが出来たという喜びが大きい。それもアカペラである。
本当に、何か遠い昔に思いを馳せさせるような心に沁みる作品。
また、このCDの最後には、こちらもアカペラによる「フィンランディア賛歌」が収録されている。
聴けば直ぐに分かるのですが、旋律は、あの交響詩「フィンランディア」の中間部である。
あの中間部がアカペラによって歌われているのである。大編成のオーケストラによる交響詩「フィンランディア」とは別世界である。
この「フィンランディア賛歌」、感動ものである。
残念なのは輸入盤なので対訳がないこと。
歌詞が、分からなくても、これだけ心に沁みるのですから、もし歌詞の意味が分かったら、もっと感銘を深くするのは間違いないでしょう。
「恋人」や「フィンランディア賛歌」だけでも歌詞を知りたいものです。
しかし、本当に、いいCDが手に入ったものと喜んでいます。