8月4(日)の朝日新聞2面は、一部広告欄以外は、アメリカ大統領選の記事でした。”女性・若者へ「違い」演出”と題するもので、ハリス氏に関しては、”ハリス氏に「世代交代」党に高揚感”と題をつけ、トランプ氏に関しては、”「極左」決めつけ トランプ氏が攻撃”という題がつけられていました。アメリカの大統領選に関して、これほどはっきり支持・不支持の意識化を潜ませた記事は、いままでなかったと思います。
私のように時間的余裕があり、あちこちから情報を集めることのできる立場にある日本人は少なく、したがってこの記事を批判的に読むことが難しい一般の読者は この記事で間違いなくハリス候補を支持するようになると思います。
なぜ朝日新聞は、支持率が拮抗している他国の大統領選の候補に関して、内政干渉と思われるほどはっきり、民主党ハリス候補の支持を意識化するような記事を掲載するのか、と私は疑問に思うのです。
また、バイデン大統領は、昨年6月のインタビューで、日本の防衛予算増を巡って「私が説得した」と語りました。日本政府はあわてて、「わが国自身の判断」と申し入れをしています。でも、防衛費の大増額は、岸田首相が、防衛大臣と財務大臣に指示するという異例の独裁的決定でした。したがって、「わが国自身の判断」などというのは、日米の主従関係を隠し、言い繕うための申し入れであることは明らかだと思います。
こうした防衛費増額決定の経緯は、日本の「主権」や「民主主義」を根底から否定するものであるにもかかわらず、日本のメディアは、バイデン大統領の発言を「失言」などとして、追及しようとしませんでした。私は、そういうところに、日本のメディアがディープステート(DS)の影響下にあることが窺われるような気がするのです。
そして、朝日新聞その他のメディアのハリス支持の姿勢は、トランプ氏がディープステート(DS)の解体を宣言していることと無関係ではないだろうと思うのです。ディープステート(DS)、すなわち「闇の政府」は、実態がはっきりしません。でも、アメリカ政府の機関であるCIAやNSAなどが、金融や軍需産業、大手メディアとネットワークを組織し、アメリカ政府といっしょに、あるいは、アメリカ政府の背後で権力を行使していることはあり得ることだと思います。
以前、エドワード・スノーデンを取材した元ガーディアンのジャーナリスト、グレン・グリーンワルド(Glenn Edward Greenwald)が、選挙戦中に誤った情報でイラク戦争を引き起こしたCIAの責任を問いただしたドナルド・トランプに対して、”民主党の重鎮、チャック・シューマー上院議員がテレビ番組で「情報機関に逆らい続けると潰されるぞ」と警告した”という事実を明らかにし、問題視していました。
また、 前回の大統領選の際、共和党のタカ派と考えられてきた人たちが、トランプ候補を支持せず、クリントン候補の側に鞍替えしたというようなことも語っています。
上記のグリーンワルドによると、トランプ政権発足後に、共和党を支えるネオコン知識人の一人とされるウィリアム・クリストル(William Kristol) 、『ウィークリー・スタンダード』誌編集長)が、”自分たちが作っていたシンクタンク「フォーリン・ポリシー・イニシアチブ」を閉じ、民主党のヒラリー派を巻き込んで新しく「民主主義保全同盟」という組織に作り変えた”ともいいます。
さらにグリーンワルドは、トランプ氏の登場によって、”共和党に棲みついていたネオコンが、民主党と合流した”ともいうのです。トランプ氏の登場で、アメリカ政界が大きく変化したということだと思います。
こうしたことは、現実には、トランプ氏が解体を宣言したディープステート(DS)の存在抜きには考えにくいことです。

「“ディープ・ステート=闇の政府”を解体し、腐敗したワシントンに民主主義を取り戻す。まず、2020年の大統領令を再び発令し、質の悪い官僚たちを排除するための大統領権限を取り返す」と宣言しているトランプ氏は、そういう意味で、単なる大統領候補ではなく、ディープステート(DS)を乗り越え、アメリカを、また、世界を激変さ得る存在だと思います。
トランプ氏の言動には危うい面もあり、心配なことも多々あるのですが、彼が、”私は新たな戦争を始めなかった、ここ数十年で初の大統領となったことを特別に誇らしく思う”と述べ、「ウクライナ戦争を終わらせる」と語り、さらに、「私が大統領なら、ハマスのイスラエル襲撃はなかった」と言い、北朝鮮を訪れて、金正恩とも握手をしたトランプ氏に、私は期待したい面もあるのです。
Qアノンが、「アメリカの政財界やメディアは“ディープ・ステート(闇の政府)”に牛耳られている」と言っているからということで、トランプ氏の発言を、何でもQアノンと結びつけ、ディープステート(DS)を「陰謀論」と結論づけてはいけないと思います。また、トランプ氏が選挙目的のために「ディープステートを解体する」という公約を掲げている、というのもいかがなものかと思います。

関連して、私は、トランプ氏が批判的な立場を取っている「ビルダーバーグ会議」というものの存在も気になってます。いったい何を話し合っいるのか、なぜ極秘なのか、と思うのです。
そして、今日もまた、ベネズエラの反政府デモなどの報道が続いているのですが、ウクライナと同じような政変に発展するのではないかと心配しています。ウクライナでは、当時オバマ政権の国務次官補で、ウクライナ担当であったビクトリア・ヌーランドが講演会で、「ウクライナの民主化に50億ドルを費やした」と語り、アメリカ議会でも問題になったということです。ベネズエラには、どれくらいの資金を投じているのか、と気になります。
Twitter上では、”ベネズエラ情勢について、主流メディアもイーロン・マスクも反マドゥロのデモの映像を盛んに流すが、大統領選挙時にマドゥロ支持ラリーに膨大な人数が集まっていた映像はなぜか流さない。なぜだろうか?”という投稿があり、膨大な数の人たちが行進している映像が取り上げられているのです。(https://twitter.com/i/status/1819027761870364685)
だから私は、そういう情報操作がくり返されてきた歴史を確かめる意味で、「わたしは見たポル・ポト キリング・フィールズを駆けぬけた青春」馬渕直城(集英社)から、「キングフィールズの真実」を抜萃しておきたいと思ったのです。
「ポル・ポト」や「クメール・ルージュ」という言葉を聞けば、日本を含む西側諸国の多くの人は「大虐殺」を連想するのではないかと思います。でも、カンボジアで長期にわたり命がけの取材を続け、カンボジアの人たちと深く関わった馬渕直城氏は、”THE KILLING FIELDS” 邦題『キリングフィールド』というハリウッド映画は、”ポル・ポト派の兵士たちを悪鬼の如くを描き出し、彼らによって”大虐殺”が行われたというイメージを世界中に焼き付けたことはまちがいない。その計り知れない悪影響の大きさを考えると、単なる映画だといって、虚偽を見過ごすことはできないのである”と書いているのです。
だから、「善悪を逆さまに見せる」西側諸国の政治戦略は、あらゆる分野・領域に広がっているといえるのではないかと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二章 プノンペン解放
キングフィールズの真実
1984年、カンボジアの解放を背景に、”THE KILLING FIELDS” 邦題『キリングフィールド』という映画がハリウッドで制作された。
映画の粗筋はおよそ以下のようである。ニューヨークタイムズ誌の記者シドニー・シャンバーグは、カンボジア人助手のディス・プラン(正しくはディット・プロン)と戦火のカンボジアを取材していた。プノンペン陥落後、シャンバーグはからくも国外へ脱出するが、プランはポル・ポト政権下に取り残され、クメール・ルージュが支配するサハコーで、強制労働を強いられ、虐殺場面を目にする。長い軟禁状態の末、運良く脱走し、タイへ逃れる。そこで四年ぶりにシャンバーグと感動の再会を果たすという、二人の友情を軸に描きながら、”大虐殺”の有り様を訴えるというものだ。
先に書いた通り、解放の日、私はプノンペンにいた。そこで目撃したことは映画とは大きく違っていた。もちろん、映画はあくまでもフィクションであり、事実と違うといってことさらにあげつらうのは無意味かもしれない。しかし、この映画がポル・ポト派の兵士たちを悪鬼の如くを描き出し、彼らによって”大虐殺”が行われたというイメージを世界中に焼き付けたことはまちがいない。その計り知れない悪影響の大きさを考えると、単なる映画だといって、虚偽を見過ごすことはできないのである。
ある大新聞の記者が、あの映画は真実の悲惨さを充分に伝えていない、といった間の抜けた記事を書いていたが、記者の言う「真実」とは、何を指すのか。現場を知りもしない者が、よくもそんなことを言えるものだと、その記事を見た私は怒りに駆られた。映画という娯楽作品としていったん情報が流れていくと、それが真実としてまかりと通ってしまう。その恐ろしさを改めて感じたものだ。
大体、邦題では「キリング・フィールド」となっているが、原題は「キリングフィールズ」であって、アメリカとの戦争、革命時代、ベトナム侵攻と、フィールド(戦場)が何度も重なったところにクメール民族の不幸があったのだというのが制作側の意図だ。邦題ではそのニュアンスがきれいに消されてしまった。
この映画は、そもそもシドニー・シャンバーグが、ニューヨーク・タイムズ・マガジン」誌の1980年1月20日号に書いた手記『ディット・プロンの死と生』を原作としているのだが──ちなみに、シャンバーグはこの手記によりピュリッツアー賞を受賞している──、この手記自体がすでに事実を大きく曲げたものだった。
実際、映画上映後、事実とのあまりの違いを批判されたプロデューサーのデイヴィット・パットナムは、この映画は政治的なことが主題ではなく、シャンバーグとプロンの友情物語として見てほしいと語っている。
しかし、その「友情」すらも虚偽なのだ。実際のシャンバーグは、人前でプロンを罵倒したり、突き飛ばしたりしていた。映画では、フランス大使館にいるカンボジア人に退居命令が出た時、プロンはタイへ逃げようとするのだが、シャンバーグは一緒に逃げようと急遽英国パスポートを作り、材料の乏しいなか、パスポート用にプロンの顔写真をアル・ロコフが撮影し現像するといった場面がある。しかし実際には、プロンは自分の写真を持っていたが、私の忠告で偽パスポート作りをとりやめたのだ。こんな二人のあいだに友情など生まれようはずもなかったのである。
また、シャンバーグは日頃からアジア人を蔑視するところがあった。サイホンも後に「週刊プレイボーイ」誌のインタビューに答えて、彼についてこう語っている。
「あの人をカンボジア人たちは、陰で”悪い目の人”と呼んでいました。悪い目とは、人のことを悪く解釈する人のこと。あの人はカンボジア人をいつも見下していた。およそ、ヒューマニズムとは、遠くはなれた人なんです」
そんな彼の態度は同胞であるアメリカ人ジャーナリストにとっても不快だったのだろう。彼らにも総スカンを食っていた。
シャンバーグのアジア人蔑視は恐怖と裏腹で、フランス大使館に避難していた時も、彼はたえず脅えており、大使館から一歩も出ようとしなかった。私が大使館内の生活を撮るべく、カメラを向けたら、「おれたちが苦しんでいるのを撮るな!」、とヒステリックに叫び、レンズに向かって手を広げたのである。そればかりか、外で写真を撮っている私をやっかんだのか、大使館員をそそのかして、私のカメラを取り上げさせたのである。
「従わなければ女房ともども大使館にいられなくしてやる」
そんな言葉を吐く、なんとも低劣な俗物というのが彼の本性であった。
映画『キリング・フィールド』は、フィクションではあるが、ドキュメンタリーの体裁をとっており、それが観る者に、より「衝撃」を与えることになるのだが、事実、ここでは多くの人々が実名で登場する。「ニューヨーク・タイムズ」のカメラマン、アル・ロコフもその一人である。
解放前、ロン・ノル政権下のプノンペンにあったケマラ・ホテルは欧米人たちの溜り場になっていて、私もよくそこに通っていた。そこに時折、アメリカの海兵隊上がりのカメラマンがやってきた。それがアル・ロコフだった。彼は海兵隊の写真班員としてベトナム戦に参加した元兵士だった。
いったいロコフはベトナムの戦場でどのような地獄を見てきたのか。私とほぼ同年齢だというのに、目から精気が失せ、かれに笑顔を見せてもその目は冷たく見開かれたままだった。常時マリファナで酔い、アメリカからきた同国人ともめったに話をしない。
恰好も1970年代のヒッピー風で長髪という容貌の持ち主だった。そんなロコフがある時、彼が撮影した写真を焼き付けし、見せてくれた。私は息を呑んだ。すべて死んで腐敗した兵士の死体ばかりだったのだ。腐った死体の上を列になって歩く蟻のクローズアップだとか、水溜りの中で笑うように大きく下顎を開けた頭骸骨だとか、そんなものばかりだ。
報道カメラマンの職分を逸脱した、そのあまりにもグロテスクな写真を見せられた私は、おそらく彼はこのベトナム戦争で底知れぬ闇の奥を見てしまい、少々頭が変になってしまったのだろうと思った。
その写真を一度でも見せられた者は、誰もが気味悪がって彼と関わろうとしなくなる。それでもお互い売れないフリーランスのカメラマン同士だったこともあり、私とロコフはやりとりをするようになった。一緒に戦場へ行くこともあった。実際、ロコフは付き合ってみると意外にいいやつなのだ。
彼と行動を共にするうちに、どうやらヨコフは戦場で死んだ人間の声を聞くことができるに違いないと思うようになった。とてつもない死臭が漂う熱帯の密林で、腐り、分解しつつある人体にごく至近からカメラを構えて跪(ヒザマズ)くロコフ。長い時間、死体ばかりを見続けてきたロコフは、まるであの世へ行ってしまった者たちからメッセンジャーに選ばれているかのようだった。カンボジアでは死者の霊は49日間死んだ場所に残っているという。怨念を抱きながら死んだ者が、死臭を放ち、そばにいる者に取り憑く。
私は初め死体が不気味で、写真を撮影してもすぐに逃げるようにその場から離れていた。だが、そのうち免疫ができ、死体があちこちに散らばる戦場に長くいても、あまり気にならなくなった。だが、そうなると今度は長くいる分、漂う死臭が知らぬまに自分に取り憑いてくる。疲れてその日は、洗濯できず、翌日に同じ服に腕を通そうとすると、死臭が残っていることに気づく。
現場で死臭にさらされるのは避けようがない。服に付くのも仕方がない。それでもまだ死臭を死臭だと認識できるうちはいい。拭いきれない死臭がレンズを通して頭の中に入り込み、現場に長く居座るとあちら側からの声をロコフのように聞くようになるのだ。その声がシャッターを切らせる。それが、ロコフの写真が、死臭をこれでもかというぐらいに放散させている理由だった。
ごく普通の社会生活を送る者にとって、このにおいはあまりにも縁遠く、大方の者は嗅いだ瞬間に眉間に深いしわを寄せるか、顔をそむける。戦場写真の売買を手掛ける通信社や新聞社も、死体写真はあまり買わない。
ところが、そんなロコフの写真が売れた。買ったのはほかでもない、あのシャンバーグと映画プロデューサーだった。
田舎出の純朴なクメール青年が解放軍兵士だったという設定では、プロデューサーやシャンバーグの思う娯楽映画のストーリーが成立しない。そこで彼は死臭を放つロコフの一連の写真に目を付けて買った。そしてとてつもない蛮行を繰り返す極悪兵士の悪業の”証拠”として、ロコフの死体写真を使った。彼の解放時を含めた戦場写真をベースとして映像を創作したのだ。あの映画にこれでもかというぐらいに頭蓋骨の山が出てくるのは、そのためかもしれない。シャンバーグ自身は、プノンペン滞在中、服に死臭が付くことはなく、ましてや頭の中に死臭がこびりついて離れなくなるようなこともなかった。なぜなら、彼は現場取材にはほとんど出ないタイプの記者だったからだ。
後にロコフが怒りを込めて言った。
「たった5000ドルだぜ、全部まとめて。ああれでやつはいったいいくら儲けたんだ」
シャンバーグが、彼から買い取った写真の値段のことだった。
そのほか、この映画には私の知り合いのカンボジア人が何人か出演している。「カラワン」というフォークバンドのリードボーカル、スラチャイは、小隊長の役で、実際にはなかった殺戮場面を演じてみせた。
スラチャイはタイ国籍だが、クメール人が多く住むタイのスリン県出身のクメール人だった。さらに彼は、クメール・ルージュと友好関係にあったタイ共産党にも参加していた。つまり、ポルポト派とはごく近い線にいたのだ。その彼が反ポル・ポト・プロパガンダの映画に出演していたというのは、なんとも皮肉なことである。
実は、サイホンもまたこの映画に関わっていた。映画のロケはほとんどタイで行われたのだが、その際に彼女はキャスティングに参加している。しかし、脚本を読んだ彼女は唖然とした。彼女が目にした事実と脚本で書かれていることがあまりにも違っていたからだ。脚本に書かれている凄絶な市街戦や虐殺・暴行シーンなど一切なかった。そのことをプロデューサーやスタッフに抗議すると、「脚本通りに映画ができるわけじゃない」「映画は映像により脚本とは別の感じ方をするものだ」と説得され、彼女の抗議は結局受け入れられなかった。
後に彼女はこう語った。
「他のカンボジア人はお金が欲しくて映画に出るだけで何も言わない。私がこれまで日本とタイで活動して来たのは何のためだったと思いますか。問題が帰れるところがあるかどうか、ということなんです。カンボジアつぶすようなことはできません」
この映画は結果的にカンボジア人蔑視を助長したことになる。このことを看過してはならない。















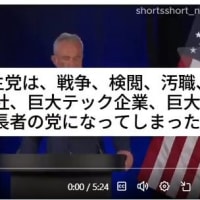











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます