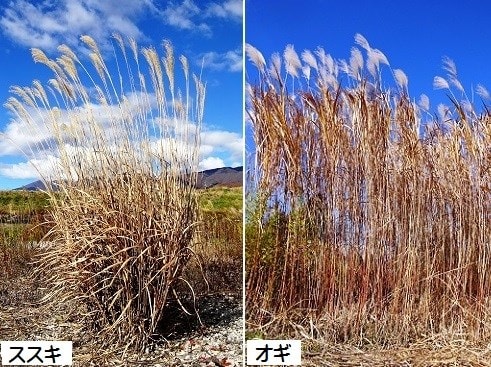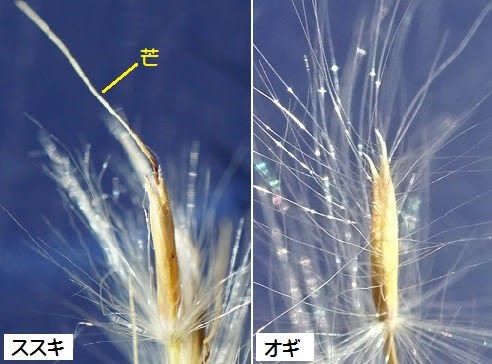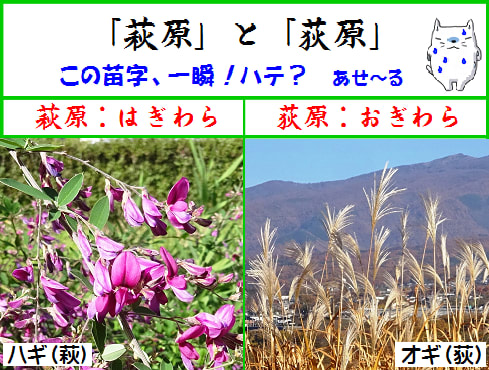家の周りや道端などでおなじみの、カタバミ科カタバミ属のカタバミです。
ハート型の葉と鮮やかな黄色い花は可愛いのですが、雑草としては難敵です。

我が家の芝生に入り込んだカタバミ、とてもしぶとく絶やしきれません。
アカカタバミやウスアカカタバミと呼ばれるカタバミの品種です。

アカカタバミは花の中心部が赤く染まることが多く特徴的です。
カタバミより繁殖力が強いのか、どこにでも芽を出してはびこります。

道端でよく見かけるオッタチカタバミは外来種、美しい花を咲かせます。

カタバミとオッタチカタバミはよく似ています。
見分け方を調べてみると、いくつかのポイントがありました。

カタバミが這性で、オッタチカタバミは名のとおり立性です。
這うか立つかでほぼ見分がつきますが、迷う場合は他のポイントを比べます。
根は、オッタチカタバミに比べてカタバミは太く、抜き取り除草が大変です。

托葉の観察はルーペが必要ですが、分かり易い見分けポイントです。

葉の縁の毛が立っているのか、曲がっているのかの見分けです。
葉によって毛の状態が多少違い、ちょっと見分け難いでしょうか。

オッタチカタバミの見分け方に「果実の柄が斜めに下がる」とあります。
そのとおりでしたが、カタバミにも下がる果柄がありました。

種子の違いは明瞭で、オッタチカタバミには10本ほどの白線が入ります。
種子の長さは1mm前後と小さいので観察にはルーペが必要です。