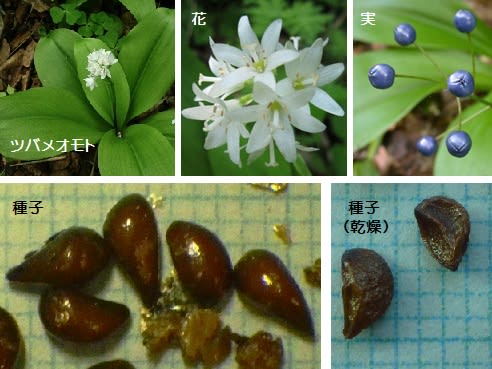水溜まりができるほどの強い雨でしたが、昼からは陽が射してきました。

今日は1日中雨かと思い、午前中から近くの温泉『湯楽里館』にでかけました。
当館は南向きの丘の上に立ち、東御市内や丸子方面が一望できる絶景の温泉です。
温泉館と並び、地元の農産物を直売する『ゆらり市』や農産物加工品店もあります。
市の店先には時期の野沢菜、店内には人気商品の大粒干しぶどうが並べられています。

農家の女性の皆さんが集まり、数年前から農産物の加工に取り組み始めました。
なかでも、特産の種なしぶどう大粒品種を原料にした干しぶどうは、抜群の人気です。

黒、緑、赤色のぶどうの粒を房から取り外し、きれいに洗って乾燥棚に並べます。
これを乾燥機に入れ、美味さの頂点を観ながら一昼夜ほど熱と風で干し上げます。

良質な原料からできあがった、最高級干しぶどうの完成です。
東御市産ぶどうの風味が濃縮され、おいしくておいしくて、試食の手が止まりません

できあがった干しぶどうと、一般に売られている外国産のものとを比べてみました。
大きさはもちろん、味わいの深さと香り、そして歯ごたえは至宝の干しぶどうです。

画像は今年、parfum doux(ぱるふぁんどぅ)で干しぶどうにした6品種です。
それぞれ1粒ずついただき、特徴を忘れないようにパンフレットに並べてみました。

今日は1日中雨かと思い、午前中から近くの温泉『湯楽里館』にでかけました。
当館は南向きの丘の上に立ち、東御市内や丸子方面が一望できる絶景の温泉です。
温泉館と並び、地元の農産物を直売する『ゆらり市』や農産物加工品店もあります。
市の店先には時期の野沢菜、店内には人気商品の大粒干しぶどうが並べられています。

農家の女性の皆さんが集まり、数年前から農産物の加工に取り組み始めました。
なかでも、特産の種なしぶどう大粒品種を原料にした干しぶどうは、抜群の人気です。

黒、緑、赤色のぶどうの粒を房から取り外し、きれいに洗って乾燥棚に並べます。
これを乾燥機に入れ、美味さの頂点を観ながら一昼夜ほど熱と風で干し上げます。

良質な原料からできあがった、最高級干しぶどうの完成です。
東御市産ぶどうの風味が濃縮され、おいしくておいしくて、試食の手が止まりません

できあがった干しぶどうと、一般に売られている外国産のものとを比べてみました。
大きさはもちろん、味わいの深さと香り、そして歯ごたえは至宝の干しぶどうです。

画像は今年、parfum doux(ぱるふぁんどぅ)で干しぶどうにした6品種です。
それぞれ1粒ずついただき、特徴を忘れないようにパンフレットに並べてみました。











 t
t