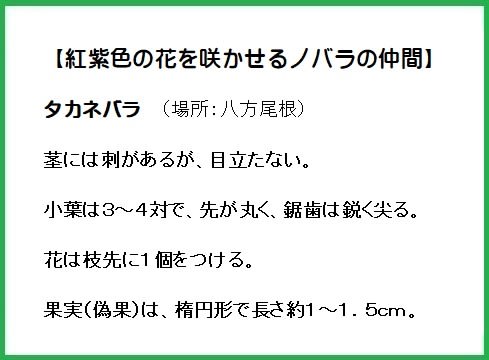「刻(とき)を忘れさせる島 吐噶喇(トカラ)」の旅がようやく実現しました。
十島村へは「フェリーとしま」が週2便、奄美の名瀬港往復で運航されています。
今回は有人島7島のうち、2回の往復便を利用して、中之島と宝島を巡りました。
往復便で行ったり来たりを繰り返すと、4往復便で全島を巡ることもできます。
もし、島に渡った後に悪天候に見舞われた場合は、じっくりと刻を忘れましょう。

フェリーは鹿児島本港の南埠頭から、夜中の11時に出航します。
9時から乗船ができると聞きましたので、8時30分ごろに乗り場に到着しました。

乗船券は出航が決まってから販売するとのことで、空港で出航の確認をしました。
鹿児島港から中之島までの料金は、二等客室で、一人6,180円です。

今日はそれほど混んでいませんが、混雑時は通路にも寝具が敷かれるようです。

レストランには売店と、10種類ほどのメニューがあり食事ができます。
ですが、営業時間や、船酔いなどの事情で食事がとれない場合もあります。
島内には食堂はありませんし、店屋さんも夕方のみの営業だったりします。
そこで用心のため、カップ麺や保温ポット、腹持ちの良いおやつを持参しました。

届け先と花屋さんの名の書かれた花束が、洗面所の脇にありました。
離島でのこの時期の花束、すぐにピンときました(後に紹介)。

ほぼ定刻に十島村の玄関口、北緯30度の口之島に到着しました。

島の生活物資は、すべて「フェリーとしま」によって運ばれてきます。
下したばかりのコンテナの脇に車をつけ、さっそく荷物を積み込んでいます。
生協、取引店、あるいはネットなどから、お米や嗜好品、衣料品などが届きます。

口之島を出て間もなくすると、高い山が見えてきました。
トカラ列島の中で一番高い山、標高979mの活火山、御岳(おたけ)です。

天候に恵まれて軽快な7時間半の船旅、中之島港に着岸しました。
降りる皆さんは、島民の方、仕事の方がほとんどで、観光客は稀です。