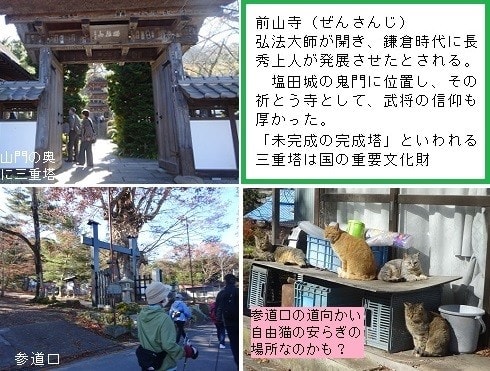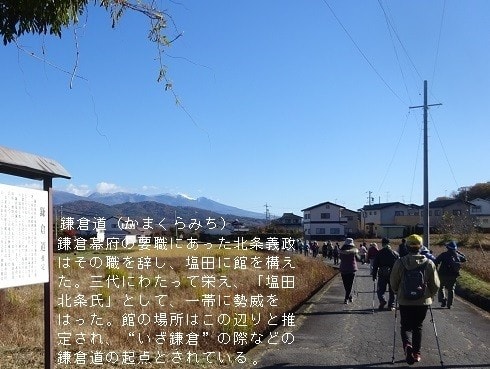この日の目的地の皆神山が目前に見えてきました。

急傾斜の山道に横たわる風倒木、酷暑の中で冒険気分の山登りです。

1時間ほどで山頂の皆神神社の随神門に到着です。

クロサンショウウオの産卵が見られるのは早春だそうです。
門の正面は侍従神社、その右手奥に本社の熊野出速雄神社があります。
本社の裏に御神木のヒムロビャクシンがあるそうですが、見落としてしまいました。
境内の横には広い草地があり、ここで早めの昼食です。

午後からは、代官町(象山東)駐車場に車を止めて近隣を歩きました。

第二次世界大戦末期に、日本の政府中枢機能移転のために掘られた地下坑道跡です。
平和な世界を語り継ぐための戦争遺跡として、入場無料で公開されています。

地下壕のすぐ横の恵明禅寺、六文銭が目立ち、真田家ゆかりと分かります。
松代藩主真田幸道の正室豊姫の墓所かあり、本殿天井の龍の絵は迫力満点です。
豊姫が嫁ぐ際に持参したあんずの種から当地があんずの名産地になったとか。

小高い場所に、竹山随護稲荷神社(たけやまずいごいなりじんじゃ)があります。
風情ある通りを少し歩くと山寺常山邸の大きな長屋形式の表門が見えてきます。
この表門は、江戸時代末期から明治初期に建てられたと推定されているそうです。

佐久間象山先生と並ぶ勝海舟、吉田松陰、坂本龍馬などの銅像、ビックリです。
さらに訪問者の高杉晋作などのリレーフ、佐久間象山の偉大さが伝わります。

松代の耕作放棄地で見つけたオオアカバナの群落、長野県では絶滅危惧ⅠA 類です。