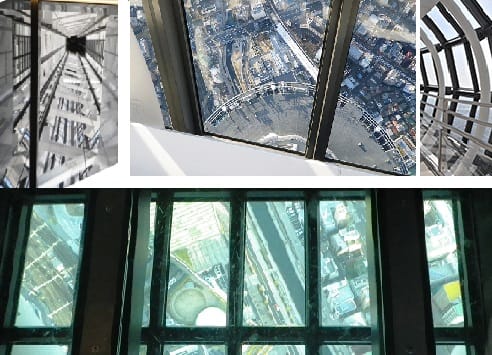「世界らん展日本大賞2015」が開催されている東京ドーム内の案内図の複写です。
今年の同展には、世界23カ国から約3,000種、10万株以上のランが出品されたそうです。
25周年記念とあって、特別主催者展示や特別企画があり見どころいっぱいでした。
バスツアーの見学時間は2時間、的を絞り①から⑬を中心に楽しませていただきました。

① 審査は『個別審査部門』など6部門からなり、今年は1,289点が出品されたそうです。
画像はシンボルオブジェBirth(誕生)と、それに向かうオーキッド・ロードです。
250万輪のランの花が会場を埋め、9日間の会期中多くの見学者を魅了したことでしょう。
この日に合わせて花を仕上げた出品者の皆さんの技術と熱意と努力はすごいですね。

②「King of Orchid・ロスチャイルド家の蘭」
蘭の王様とも称されるロスチャイルディアナム、非常に高価なものとされるそうです。

③「宮内庁の蘭と盆器」
宮内庁所蔵の『蘭鉢』と呼ばれるすばらしい盆器が展示されております。
パフィオペディラムの株との調和がみごとな伊万里錦泥丸蘭鉢、目の保養ができました。

④ 日本初公開!蘭の妖精「オルキス」
蘭の妖精「オルキス イタリカ」、小さくて可愛く、美しい神秘的なランでした。
真冬の日本でこのようにたくさんの花を咲かせることは非常に難しいことなのだそうです。
白い妖精 真冬の奇跡 育てた人の苦労をねぎらうように妖精は軽やかに舞う(読売新聞)。

⑤ らんの秘密あれこれ ・・奥深い蘭の世界を体感・・
ランの香りや表面の触感、そして独特な形、それらには理由があるとのことです。
キサントパンスズメガは長い口吻を持つ蛾、セスキペダレは長い距(きょ)を持つ蘭です。
共に長さは30cm近く、長い口吻(こうふん)を距に差し込んで奥の密を吸うのだそうです。
花が蝶や蜘蛛に似たランや、パンジー似のランは蘂(ずい)柱と先端の葯帽が可愛いです。

⑥ 記念撮影コーナー
色とりどりのランで飾られた背景をバックに、思い出の1枚が1200円でお持ち帰りです。

⑦ 海洋博公園 沖縄美ら海(ちゅらうみ)水族館
水量14トンクラスの大迫力水槽に、30種700匹の熱帯魚の仲間たちが泳ぎ回っています。
周囲は南国のランで彩られ、熱帯魚とランのコラボが神秘ワールドを演出しています。

⑧ 25周年記念特別企画 ・・假屋崎省吾さんのアレンジメントディスプレイ・・
意味は分からなかったのですが、あっけにとられ楽しんで見させていただきました。

⑨ 加賀 正太郎物語 ~蘭と共に生きた実業家~
明治21年生まれの実業家で、栽培した多数の洋蘭を日本版画として残したとのことです。
加賀正太郎さんにまつわるランと日本版画の作品の数々が展示されていました。

⑩ 女性大使のテーブルディスプレイ
駐日女性大使によるランをモチーフにしたテーブルディスプレイが披露されていました。
お国柄が表現された作品には、大使の温かなおもてなしの心がこもっています。

⑪ 「バッキンガム宮殿の蘭」
英国王室ゆかりのランとエリザベス女王の結婚式のブーケが展示されたコーナーです。
「オンシジューム アレクサンドレー」はアレクサンドラ王妃の名が付けられたランです。

⑫ 日本大賞2015受賞花 デンドロビウム・スミリエ「スピリット・オブ・ザマ」
座間洋らんセンター(神奈川県座間市)の加藤春幸さん35歳の作品です。
**案内板の審査講評より** 見事に栽培されており、株の大きさと花の数、花の質、
どれにおいても、大賞にふさわしく、すばらしい作品です。
ここまで咲き揃うことは大変珍しく、通常上部の花が咲く頃には、下部の花が終わって
いる場合が多いのですが、この作品は下から上まで見事に咲き揃っています。
本日の審査に最高な状態で出品されたことは、出品者の情熱と努力を感じます。

⑬ 「ディスプレイ審査部門」(飾り付け)特別奨励賞 岐阜県立恵那農業高等学校
高校生の迫力ある作品「ふる郷の祭り・・山車・・」が世界らん展を彩っています。
穂のように垂れ下がる黄色い花は「デンドロキラム」で高山祭の山車を表現しています。
作品に使われた40種3000株のすばらしいランは、生徒達が丹精込めて育てた株です。
デンドロキラムを一斉に咲かせる技術ひとつをとっても大変なことなのだそうです。
「恵那農業高校にとって世界らん展は甲子園のようなところ」との生徒らの談(TV放送)。
故郷に寄せる思いと誇りを表現したい、との思いが結集されたすばらしい大作です。