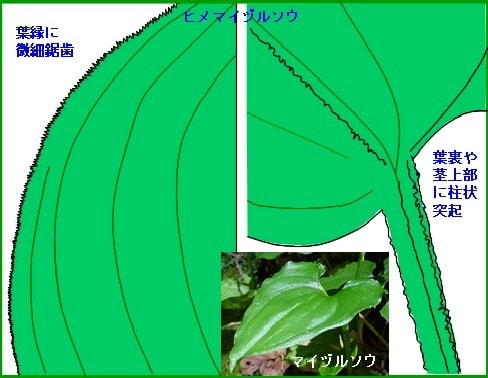上信越自動車道から下りて国道18号につながる道路脇の植え込みです。
この時期に植え込み内に生える植物を毎年見に来ます(この日は4月4日)。

2019年4月に見たことのない植物が生えていることに気づき、調べた植物です。
ナデシコ科のカギザケハコベというヨーロッパ原産の帰化種です。
日本では1990年に仙台港で初めて採取されたそうです。

葉の多くは地際部にかたまってロゼット状につきます。
茎葉は対生で2,3対がつき、形状は狭長楕円形で、先端が尖ります。

葉の縁や茎には腺毛が目立ちます。
腺毛は全草に生えるのではなく、ない葉や茎もあります。

茎の先に5~10数個の花を散形状につけます。
蕾のころは花柄が下がることが多いですが、開花時には上向きになります。

蕾で特徴的な点は、蕚の基部に黒色の模様をつけることです。
模様は点であったり、U字形であったりします。

花弁は透けるような白色で5個、先端が不規則に切れ込みます。
雄蕊は3~4個で、柱頭は3裂します。

果実は蒴果で、熟すと先端が外側に巻き、たくさんの種子をまき散らします。
種子は1mmほどの楕円形で中央部がとって状に隆起します。
全面がいぼ状突起で覆われます。

今日の本題はここからですが、カギザケハコベ元気がよく陣地を広げています。
隙間があれば根を下ろし、3月から種子を実らせ散布をします。
この周辺では春の花のナズナやホトケノザなどとの勢力争いが激化しています。

民家の庭にも侵入が始まりました。
今後、畑の雑草とならないかととても気がかりです。