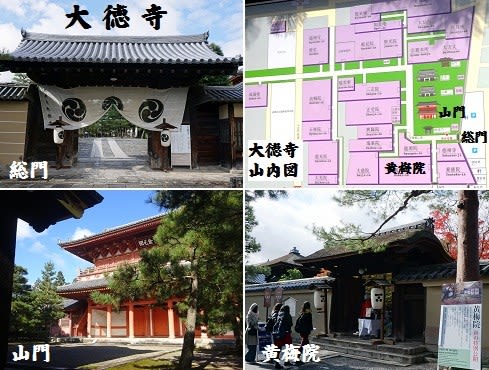朝食をいただき、7時40分に御岳(おたけ)を目指して出発です。
宿のご主人が、「歩きは大変なので途中まで車で送ろうか」とのおすすめ。
ありがたいのですが、道すがらの花探しということで、遠慮申し上げました。

宿を出ると早速、見たことのないキイチゴの白い大きな花が咲いています。
かなり特徴的で「リュウキュウバライチゴ」かと思われます。
後で聞いた話ですが、イチゴを島に輸送することはできないそうです。
ですから、この実が赤く熟れる頃は、キイチゴ狩りが大人気のようです。

舗装の隙間に咲くスミレ、沖縄でも見た「リュウキュウコスミレ」でしょう。

坂道を下り、村の大通りに出たところで、旅の親子連れと情報交換です。
道脇にはクレソン(画像右上)がいっぱい、水がきれいな証拠です。
集落のはずれの分かれ道に、「村道御岳線起点」の道路標識があります。
島内の旅行者は、画像右下の青い服の青年、左上の親子、私共の5名のようです。

道路の脇には「シマイズセンリョウ」が花盛りです。

島の北側を回る道から御岳登山道への分岐点、りっぱな標識があります。
みちくさ道中でここまで約1時間、登山道入口まで5.8kmとあります。

コンクリート舗装の広い道を登り始めると、落石か?道路に石が落ちています。
原因は「トカラヤギ」、斜面を昇り降りする際に落とすのだそうです。

開花時期、淡褐色の軟毛や刺の様子などから「ホウロクイチゴ」としました。

タチツボスミレの海岸型と言われる、「ツヤスミレ」と思われます。

テンナンショウの仲間の見分けは難しいのですが、かなり特徴的です。
初めて見ますが、すぐさま「ムサシアブミ」が頭に浮かびました。

5cmほどの長さの茎に花をつけた「ヒメハギ」、濃紫色の変わった形の花です。

今日3種類目のスミレ、側弁の基部に毛を生やす「リュウキュウシロスミレ」。

標高400mを超すあたりから、ツツジの花が見ごろの時期となっていました。

このツツジ、「サクラツツジ」か「アラゲサクラツツジ」かで迷っています。
見分けのポイントは成葉時の毛の有無とか、この葉は成葉には早そうですが。

「コモウセンゴケ」が名の由来のように、道路の法面を赤く染めています。
特徴は、葉長が柄を含め1~2cm、葉身と葉柄の堺が不明瞭、花は淡紅色です。

1km毎に標識があり、登山道まであと2km地点まで登ってきました(10:50)。
かわいく咲く「フデリンドウ」の脇に、腰を下ろして一休みです。

赤い実を残す、「カラタチバナ」と「ハダカホオズキ」が目を引きます。

下向きの花を咲かせ、ビロード状の手触り、「ビロードカジイチゴ」でしょう。

11時30分、登山道入口に到着、舗装道は少し先のテレビ受信塔まで続いています。
標高750mほど、ここからは急な山道に入りますが、道は整備されています。
登りはスニーカーで十分でしたが、帰りの下りで、かなりつま先を痛くしました。

12時20分、トカラ富士とも呼ばれる標高979mの御岳の山頂に立ちました。
御鉢の中はすさまじい様相でさすが活火山、かっては硫黄を採掘したそうです。
周囲一周や底まで下れるそうですが、疲れもたまり相談の結果、やめました。
マルバツツジが山肌に張り付くように群生、開花期は素晴らしい景観でしょう。
** 次回は集落の様子などを予定しています **