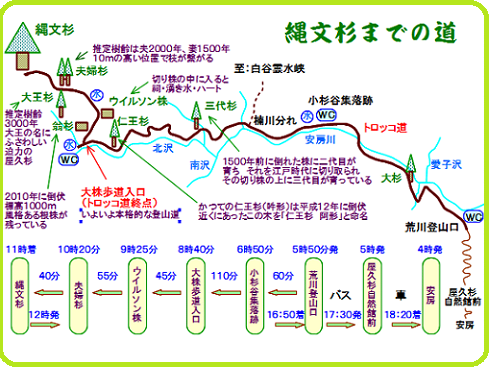20日に、京都五山の一つに数えられる『東福寺(とうふくじ)』を訪ねました。
境内の渓谷を染める紅葉の庭に心躍り、建物の庭に心静まる、絶妙なお寺さんでした。

北門側から入り、渓谷に架かる、「東福寺三名橋」の一つ『臥雲(がうん)橋』を渡ります。
臥雲橋から望む渓谷の紅葉は絶景ですが、混雑による危険防止のため撮影禁止です。
『日下門』から境内に入り、渓谷沿いのモミジの庭園に入ると、カメラの放列、その先は。

カメラの先は、渓谷の紅葉を渡る真ん中の橋、東福寺看楓拝観のメイン『通天橋』です。
渓谷『洗玉澗(せんぎょくかん)』には、2000本ものモミジが植えられているそうです。
鮮やかな赤と黄色が織りなす圧倒的な景観、目に焼き付けたり、カメラに納めたり。
モミジの庭園から回廊を上りきると別世界、白砂と緑の植込みの庭に入ります。
ここは、開山を祀ったお堂の『開山堂』と住居だった『普門院』、庭はとても清楚です。

最大の見どころ、『通天(つうてん)橋』からの紅葉、奥に見える屋根は臥雲橋です。

『方丈庭園』、方丈とは禅宗寺院における僧侶の住居、後には応接にも用いたそうです。
作庭家の重森三玲(みれい)作の方丈庭園は、方丈の東西南北の四方にあります。
南庭は210坪の広い庭で、巨石によって力強く配置された島と、砂紋の海です。
北庭は、伝統的な市松模様を用いた斬新な庭、お釈迦様の入滅までを表現したとか。
方丈から見る通天橋と渓谷の紅葉、庭園の借景にも取り込まれているとのことです。

『偃月(えんげつ)橋』の入口に、「特別公開 国宝龍吟庵」とあります。(龍吟:りょうぎん)
塔頭(たっちゅう:寺院の中に ある個別の坊)の一つで、三つの枯山水庭園があります。
南庭の『無の庭』は、方丈の前庭で白砂が敷かれ、奥の竹垣に趣深い文様があります。
西庭の『龍の庭』は、青石が龍、白砂が海、黒砂が黒雲を表すそうです。
東庭の『不離の庭』は、国師と称された禅僧の故事を石組みで表しているのだとか。

東福寺の国宝『三門』は、現存する禅寺の三門としては日本最古 のものです。
寺院の門の多くは「山門」と表記されますが、 東福寺では「三門」です。

日が落ち闇が深まった頃、『青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)』を訪ねました。
ここは京都東山山頂、最近、青蓮院の飛び地境内に『将軍塚青龍殿』が建ちました。

紅葉のライトアップ期間、ライトを浴びたモミジは紅を増し、幻想的に輝いています。

闇の中に浮かび上がる、将軍塚青龍殿(しょうりゅうでん)とイロハモミジなどの紅葉です。