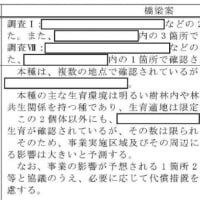私はアイヌ文学に少し興味がありました。物語が自然にやさしく、人と動物との境界がないようでとても学ぶべきことがあると感じたからです。なかでも「ミソサザイ」のお話が好きで、これは保全生態学の最も重要なこと、小さな生き物を軽くみてはいけない、森を破壊する者は罰されるべきだといった点で、先進国がようやく気づいたことを、アイヌの人たちがずっと前から深く理解していたことを示しています。
新聞の広告で「アイヌ語の贈り物」(新泉社)という本をみつけたので読みました。物語そのものよりも、著者が若いときにアイヌの人の生活に入り込んでアイヌ語をマスターし、言葉だけでなく、その背景にある自然観まで理解していることに衝撃を受けました。同時にことばの的確さと文章力、文章の構成力にもただならぬものを感じました。感動が大きかったので文章を読みながら、著者に手紙を書きたいと感じていましたが、巻末をみたら2012年10月に亡くなっていたことを知り愕然としました。
本の一部に「ほかのことにかかわったためにアイヌのことからしばらく遠ざかっていた」という意味の記述があり、気になっていました。
年末年始は殺人的に忙しかったのですが、野上ふさ子という人の名前が記憶に残っていました。そうしたら「いのちに共感する生き方」(彩流社)が出ました。手に入れて、私の中でばらばらにあったものがつながりました。実験動物の反対運動をしていた人でもあったのでした。私は動物実験に反対するヒステリックな動物愛護派の人だと思い、著作を読んでいませんでした。シーシェパードのようなグループだと思い込んでいたのです。あの人がアイヌ文学の専門家でもあったのか、驚きでした。
「いのちに共感・・」はこれから大きな反響を呼ぶと思います。自叙伝としても高い評価を受けると思いますが、野上ふさ子という人の人生の一貫性そのものが圧倒的な説得力をもって迫ってくるという意味ですごい作品だと思いました。彼女は少女時代からおそるべき読書量で本を読みます。読破力というべきかもしれません。自慢話はないのですが、事実として書かれていることが、この人のただならぬことを能弁に語ります。日本の私小説の脆弱さを指摘するあたり、文章を書くということは何かということも考えさせます。文章を書くのに重要なのは小手先の技術ではなく、書くべき内容であり、それを可能にするにはそれに値する生き方をしなければならないということです。
彼女は私とまったく同じ年齢で、大学に入るが意味を見いだせなくて退学し、北海道でアイヌの社会に入る体験をし、そこから日本社会の過ちに気づき、勇気をもって闘いを始めます。逮捕され獄中生活をするという体験までしていたことにほんとうに驚きました。
その正義感は心の深いところから出てはいますが、いわゆる感情論ではなく、豊富な知識に裏付けられた論理があります。その正義感はやがて人間のためとされる動物実験の不正に向かい、法律を改正させる力にもなります。私自身、生物を扱う職業におり、構造的にいえば対決せざるをえない立場にいるともいえます。ですから彼女の論理展開には緊張のまじった気持ちを持ちながら読みました。でも、よくある動物愛護情緒論でないことがわかりました。ここでは詳しくは書きませんが、少なくとも一部の動物実験はやめるべきだというところで同意できる部分がたくさんありました。同時に私自身がおこなう野外実験はそれとはまったく違うこともわかりました。一番大切なことは動物に対する敬意があるかないかです。私はこのブログでくり返しいっているように、名もないような小さなどこにでもいる動植物を賛美する気持ちがあります。しかしぼんやり見ているだけではそのことを知ることができず、たとえば柵を作ってシカの影響をなくするどうなるかという実験や、糞虫が森林の中でどういう働きをしているかを知るために糞トラップで採集したり、実験室に糞をおいて分解速度を調べたりしました。同じ実験でも動物に苦痛を与えるものに野上さんがきっぱりと中止を主張します。それも実験の残虐性そのものというよりも、もっと論理的にそもそも人間ではない動物を使っておこなう実験は結局は人間にとってどうであるかを結論できないと説きます。確かにそうです。
彼女はさらに深めます。そもそも地上のある生き物がほかの生き物を犠牲にして生きることは倫理的に許されるのかと。私は当面、そこまでのディープエコロジーともいえる生命観をもつにはいたっていません。人間である以上、人間が主体であることを否定できないし、それをすれば自己否定になると思うからです。それでも、飽食や濫費はつつしみたいという点では今の「豊かな」国の文明は大きな修正が必要だと感じるという点で野上さんに共感します。
本の最後は自らの癌との闘いが記されています。個人の体験記録でありながら、少女時代の自然との交流、新潟の農業社会の変容、アイヌとの出会いと生命尊重の共感、虐待される動物の命の復権、そうしたことの一貫したテーマとして自らの闘病を語り、すべての人へに通じる普遍的な問題へと高めています。そこに友人が入院してお見舞いに行ったときにみた、たくさんの管をさされて機械にがんじがらめになったような姿を見たときの衝撃、そこから抱いた現代医学への疑惑、動物実験で論じたのと同じ、専門家が陥る個別の課題にはまり込むことによってことの本質を見失うおそろしさを鋭く指摘します。そして自然療法を選択し、まさに自らの命をもって自分の生きて来た姿勢が正しかったことを証明するかのごときすごみをつきつけます。
この本に中には印象に残ることばに溢れていますが、今日はここまでにしておきます。もしあと数年、いや一年でも生きて、原発事故のことについて語ってくれるのを聞きたかったという無念が残ります。私たちはすばらしい人を失いました。野上さんは天上から、心配しながら祖国を見守っていると思います。
新聞の広告で「アイヌ語の贈り物」(新泉社)という本をみつけたので読みました。物語そのものよりも、著者が若いときにアイヌの人の生活に入り込んでアイヌ語をマスターし、言葉だけでなく、その背景にある自然観まで理解していることに衝撃を受けました。同時にことばの的確さと文章力、文章の構成力にもただならぬものを感じました。感動が大きかったので文章を読みながら、著者に手紙を書きたいと感じていましたが、巻末をみたら2012年10月に亡くなっていたことを知り愕然としました。
本の一部に「ほかのことにかかわったためにアイヌのことからしばらく遠ざかっていた」という意味の記述があり、気になっていました。
年末年始は殺人的に忙しかったのですが、野上ふさ子という人の名前が記憶に残っていました。そうしたら「いのちに共感する生き方」(彩流社)が出ました。手に入れて、私の中でばらばらにあったものがつながりました。実験動物の反対運動をしていた人でもあったのでした。私は動物実験に反対するヒステリックな動物愛護派の人だと思い、著作を読んでいませんでした。シーシェパードのようなグループだと思い込んでいたのです。あの人がアイヌ文学の専門家でもあったのか、驚きでした。
「いのちに共感・・」はこれから大きな反響を呼ぶと思います。自叙伝としても高い評価を受けると思いますが、野上ふさ子という人の人生の一貫性そのものが圧倒的な説得力をもって迫ってくるという意味ですごい作品だと思いました。彼女は少女時代からおそるべき読書量で本を読みます。読破力というべきかもしれません。自慢話はないのですが、事実として書かれていることが、この人のただならぬことを能弁に語ります。日本の私小説の脆弱さを指摘するあたり、文章を書くということは何かということも考えさせます。文章を書くのに重要なのは小手先の技術ではなく、書くべき内容であり、それを可能にするにはそれに値する生き方をしなければならないということです。
彼女は私とまったく同じ年齢で、大学に入るが意味を見いだせなくて退学し、北海道でアイヌの社会に入る体験をし、そこから日本社会の過ちに気づき、勇気をもって闘いを始めます。逮捕され獄中生活をするという体験までしていたことにほんとうに驚きました。
その正義感は心の深いところから出てはいますが、いわゆる感情論ではなく、豊富な知識に裏付けられた論理があります。その正義感はやがて人間のためとされる動物実験の不正に向かい、法律を改正させる力にもなります。私自身、生物を扱う職業におり、構造的にいえば対決せざるをえない立場にいるともいえます。ですから彼女の論理展開には緊張のまじった気持ちを持ちながら読みました。でも、よくある動物愛護情緒論でないことがわかりました。ここでは詳しくは書きませんが、少なくとも一部の動物実験はやめるべきだというところで同意できる部分がたくさんありました。同時に私自身がおこなう野外実験はそれとはまったく違うこともわかりました。一番大切なことは動物に対する敬意があるかないかです。私はこのブログでくり返しいっているように、名もないような小さなどこにでもいる動植物を賛美する気持ちがあります。しかしぼんやり見ているだけではそのことを知ることができず、たとえば柵を作ってシカの影響をなくするどうなるかという実験や、糞虫が森林の中でどういう働きをしているかを知るために糞トラップで採集したり、実験室に糞をおいて分解速度を調べたりしました。同じ実験でも動物に苦痛を与えるものに野上さんがきっぱりと中止を主張します。それも実験の残虐性そのものというよりも、もっと論理的にそもそも人間ではない動物を使っておこなう実験は結局は人間にとってどうであるかを結論できないと説きます。確かにそうです。
彼女はさらに深めます。そもそも地上のある生き物がほかの生き物を犠牲にして生きることは倫理的に許されるのかと。私は当面、そこまでのディープエコロジーともいえる生命観をもつにはいたっていません。人間である以上、人間が主体であることを否定できないし、それをすれば自己否定になると思うからです。それでも、飽食や濫費はつつしみたいという点では今の「豊かな」国の文明は大きな修正が必要だと感じるという点で野上さんに共感します。
本の最後は自らの癌との闘いが記されています。個人の体験記録でありながら、少女時代の自然との交流、新潟の農業社会の変容、アイヌとの出会いと生命尊重の共感、虐待される動物の命の復権、そうしたことの一貫したテーマとして自らの闘病を語り、すべての人へに通じる普遍的な問題へと高めています。そこに友人が入院してお見舞いに行ったときにみた、たくさんの管をさされて機械にがんじがらめになったような姿を見たときの衝撃、そこから抱いた現代医学への疑惑、動物実験で論じたのと同じ、専門家が陥る個別の課題にはまり込むことによってことの本質を見失うおそろしさを鋭く指摘します。そして自然療法を選択し、まさに自らの命をもって自分の生きて来た姿勢が正しかったことを証明するかのごときすごみをつきつけます。
この本に中には印象に残ることばに溢れていますが、今日はここまでにしておきます。もしあと数年、いや一年でも生きて、原発事故のことについて語ってくれるのを聞きたかったという無念が残ります。私たちはすばらしい人を失いました。野上さんは天上から、心配しながら祖国を見守っていると思います。