2月17日
詩とは、感情ではなく、認識である。
その言葉をどこで読んだのか。三島由紀夫の「詩を書く少年」だったか、リルケの「マルテの手記」だったか。ものすごく昔のことなので思い出せませんが、常々至言だと思ってきました。
誰もがいつも目の前に見ていながら、あるいは感じていながら、はっきりと認識できないでいることを、最適の言葉の組み合わせで表現する、それが詩です。つまり、極端に言えば、詩は科学の発見と同じだと言えます。その逆も真で、万有引力の法則は詩であり、相対性理論も詩です。誰もがリンゴが木から落ちるのを何千年も見続けてきたのに、そこに働く力の実体をはっきり取り出してみることができなかった。それに名前をつけ提示する。また、経験的には、誰もが、主体によって時間の流れ方は遅くも早くもなるということを感じていたけれども、それが事実になる場合もある(もちろん、相対性理論の内容はそれよりはるかに複雑なものを含んでいるのでしょうが)ということを、つきとめて見せてくれる。ニュートンもアインシュタインも詩人だと言えます。私が理系の勉強を放棄したのは、ただ頭が悪かったという理由ばかりでなく、ひとつには科学とは別のやり方で新しい認識を得ることもできると思ったからです。
さて、そのような前置きを書いたうえで、私が生まれて初めて、本ではなく耳で、直接聞いた詩を紹介します。それは、
ハットリ君の目は、死んでいる
という、小学校の同級生のつぶやきでした。
いうまでもなく、この詩でうたわれている「ハットリ君」とは、藤子不二雄の漫画「忍者ハットリ君」の主人公のことです。Q太郎、パーマン、ウメ星デンカと追いかけてきて、この新しいキャラクターに出会って以来、何かが違う、何かが引っかかって、これまでの藤子不二雄作品のように素直に笑えない。そう皆が思っていたその「何か」。この詩は、それをズバリ言い切っています。その場でこの言葉を耳にした全員が、胸のつかえがとれるような爽快感を味わったことは間違いありません。
しかし残念ながら、これをうたった詩人が誰だったのか覚えていません。小さな声で、歌うように、いつもめちゃくちゃおかしい話をしてくれた田谷のひーちゃんか、通学路を歩いているとき、ある家の洗濯物を見て、「ブラジャーがぶらじゃがっとる」という言葉を吐いた藤川ヒデか。いや、やはり早熟で幼稚園のころから文化面でのヒーローだった高見のしんちゃんか。永遠に謎のまま皆いなくなっていくのでしょうね。いや、もはやいないやつもいるか。
ブルックリンでの子ども時代を書いた、ヘンリー・ミラーの「黒い春」をまた読んでみたくなりました。読書に戻ります。
詩とは、感情ではなく、認識である。
その言葉をどこで読んだのか。三島由紀夫の「詩を書く少年」だったか、リルケの「マルテの手記」だったか。ものすごく昔のことなので思い出せませんが、常々至言だと思ってきました。
誰もがいつも目の前に見ていながら、あるいは感じていながら、はっきりと認識できないでいることを、最適の言葉の組み合わせで表現する、それが詩です。つまり、極端に言えば、詩は科学の発見と同じだと言えます。その逆も真で、万有引力の法則は詩であり、相対性理論も詩です。誰もがリンゴが木から落ちるのを何千年も見続けてきたのに、そこに働く力の実体をはっきり取り出してみることができなかった。それに名前をつけ提示する。また、経験的には、誰もが、主体によって時間の流れ方は遅くも早くもなるということを感じていたけれども、それが事実になる場合もある(もちろん、相対性理論の内容はそれよりはるかに複雑なものを含んでいるのでしょうが)ということを、つきとめて見せてくれる。ニュートンもアインシュタインも詩人だと言えます。私が理系の勉強を放棄したのは、ただ頭が悪かったという理由ばかりでなく、ひとつには科学とは別のやり方で新しい認識を得ることもできると思ったからです。
さて、そのような前置きを書いたうえで、私が生まれて初めて、本ではなく耳で、直接聞いた詩を紹介します。それは、
ハットリ君の目は、死んでいる
という、小学校の同級生のつぶやきでした。
いうまでもなく、この詩でうたわれている「ハットリ君」とは、藤子不二雄の漫画「忍者ハットリ君」の主人公のことです。Q太郎、パーマン、ウメ星デンカと追いかけてきて、この新しいキャラクターに出会って以来、何かが違う、何かが引っかかって、これまでの藤子不二雄作品のように素直に笑えない。そう皆が思っていたその「何か」。この詩は、それをズバリ言い切っています。その場でこの言葉を耳にした全員が、胸のつかえがとれるような爽快感を味わったことは間違いありません。
しかし残念ながら、これをうたった詩人が誰だったのか覚えていません。小さな声で、歌うように、いつもめちゃくちゃおかしい話をしてくれた田谷のひーちゃんか、通学路を歩いているとき、ある家の洗濯物を見て、「ブラジャーがぶらじゃがっとる」という言葉を吐いた藤川ヒデか。いや、やはり早熟で幼稚園のころから文化面でのヒーローだった高見のしんちゃんか。永遠に謎のまま皆いなくなっていくのでしょうね。いや、もはやいないやつもいるか。
ブルックリンでの子ども時代を書いた、ヘンリー・ミラーの「黒い春」をまた読んでみたくなりました。読書に戻ります。












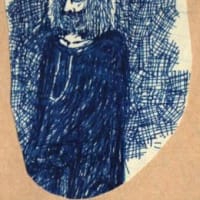
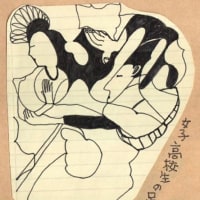
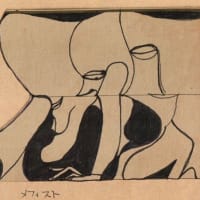
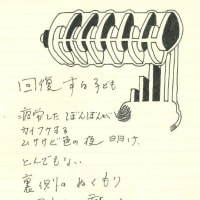
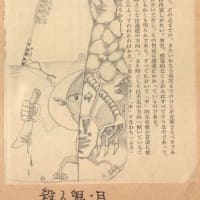
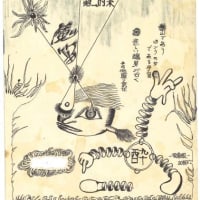
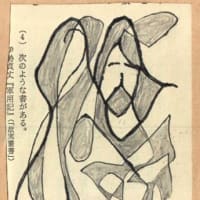
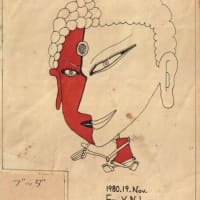






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます