夢を見ていた。
夢の中で、僕は、現実と少しも違わない場所にいた。
僕は、主人に髪を切ってもらっているところだった。
気持ちが落ち着いて、のんびりしていた。
主人は気のいい人で、ときどき僕に冗談を言った。世代の差を感じさせるような、あまりおもしろくもない冗談だったが、僕はいちいち大声をあげて笑っていた。
すると、主人が急に黙りこんだ。僕が馬鹿みたいに大きな声で笑ったのが気にさわったのだろうか。
僕は今度は、自分のほうから冗談を言い始めた。ところが、その冗談は気の利かないものばかりだった。主人のことをいい人だと思っているのに、なぜか主人を傷つけるようなことばかり言ってしまう。言ったあと、すぐに後悔するのだが、それでも言わずにいられない。一番いけなかったのは、
「ご主人の顔はネズミみたいですね」
というひとことだった。
僕はいってしまったあとで、自分はもう殺されても仕方がないと思った。全身から汗がふき出した。
けれども主人は、
「そうですか」
と言ったきりで、べつに怒っている様子もない。
「寛容な人だ」
と思うとうれしさがこみ上げてくる。
「おい、ラジオをつけてみろ」
主人が言った。
奥さんの姿が、目の前の鏡の中を横切った。たしかに奥さんだと見えたが、思い出してみると、なにか人間ではないものだったような気もした。
「ミナサン。センソウハ、オワリマシタ」
ラジオが、まるでロボットのような声で言った。
そういえば、さっきから店の外がオレンジ色に明るく光っていた。あれは、地震で町が焼けていると思っていたのだが、そうか、戦争だったのか、と僕は思った。
気がつくと、主人と奥さんとごま塩頭の男が、僕の目の前で棒立ちになって泣いていた。
「戦争なんてたいしたことじゃない」
主人への暴言と同じように、そんなひとことを彼らに向かって言いそうになり、僕ははっとして口をつぐんだ。
三人はまだ泣き続けている。奥さんだけが、ときどき僕のほうを横目で見る。そのたびに、僕は自分が責められているような息苦しさを感じる。
「さあ、それでは『日本語のヘンカク』の始まりです。この曲をどうぞ」
ラジオが、底抜けに明るい声でそう言った。続いて、聞いたこともない奇妙な音楽が流れてきた。「日本語のヘンカク」と、どういう関係があるのかまるでわからない。おおぜいの人間が、好きなようにラッパを吹いているだけの、でたらめな曲だった。それを聞いていると、心が緊張して、胃が痛くなってきた。が、それは、本当は曲のせいではなくて、空腹のせいだということが僕にはわかっていた。
「空腹感と胃痛を混同しているな」
心の中で僕はそう言った。
「お客さん、お客さん……」
耳元で声がした。
一瞬、最終電車に乗ったまま居眠りをして、とんでもないところまできてしまった、という錯覚を起こしたが、目を開けると同時にそれは消えた。
目の前に縞模様の布が広がっている。
整髪料のにおいが鼻をつく。
そうだ、僕は散髪にきたんだ……。
「お客さん、お客さん」
主人の声が、ようやく現実のものとして聞こえてきた。
「はい」
僕は、そう答えて頭をあげた。まだ、寝ぼけているのだろう。頭がふらふらと揺れるような気がする。
「終わりましたよ」
主人が言った。
「そうですか」
僕は言った。
眠る前までの出来事が、ぼんやりと頭の中に蘇ってきたが、記憶があいまいで夢との区別がつかなかった。
おそらく、みんな夢だったのだろう、と僕は思った。そうでなければこうして生きているはずはない。
そんなことよりも、僕は自分が居眠りをしていたことが気恥ずかしかった。きっと、だらしない顔で眠っていたに違いない。そのうえ、あの夢を見たのだ。寝言のひとつも言ったかもしれない。
「どうもすみません」
僕はそう言いながら、隣の椅子のほうへちょっと目をやった。
あの客はもういなかった。いや、ひょっとしたら最初から僕の前に客などいなかったのかもしれない。
頭のどこかのねじがはずれたみたいに、その辺の記憶さえはっきりとしない。
散髪あとの頭皮が空気にふれるせいか、頭がスースーする。
「頭が軽くなったでしょう?」
主人が言った。
「ええ、すっきりしました」
僕は言った。正直な感想だった。
仕上がり具合を確認しようと、僕は正面に向きなおした。が、鏡の中を覗いたとたん、
「え」
と思わず声が出た。
奇妙なことに、僕の髪は、少しも短くなっていなかった。
だがそれは、かさばっていたわけでもない。楕円形の頭に、長い髪がべったりと張り付くように伸びているのだ……。
その僕の頭の横で、主人はいま、にやにやと笑っている。
「あの……」
僕は鏡の中の主人に向かって言った。
「本当に終わったのでしょうか」
いやな予感がした。
「終わりました」
主人は表情も変えずに言った。
「でも、髪が……」
「すっかり仕上がりました」
主人は僕の言葉を遮った。
不安が、少しずつ僕の心の中に広がってきた。その不安は、僕が以前からよく知っている不安のようだった。
主人は一歩後ろに下がり、ゆっくりとした動作で僕の体を覆っていた布をはずすと、静かに言った。
「あなたの頭は、りっぱなゴム風船に仕上がりました」
不思議なことに、そう言われても、僕にはあまり驚きがなかった。主人がそういうことが前もってわかっていたという気がした。この場所で、ずっと以前にも、同じことを経験したことがあったように思えた。
僕はおそるおそる右手を上げ、顔に触れた。
すっかり凸凹のなくなったゴムの皮膚が、指の下でぶよぶよと伸縮した。
指を放し、今度は手のひらで頭を軽く弾いてみた。
ぱあん、と乾いた音がして、僕の頭は、細くなったままの首の上でふわふわと漂い始めた。
いつのまにか、僕の頭は中身が空っぽになり、本物のゴム風船になっていたのだった。
僕は、頭の揺れを両手で止めて、もう一度自分の顔を見直した。
耳が押しつぶされていることを除けば、正面から見たのではそんなに変わっているようには見えない。が、横顔がひどかった。横を向いても、頭の形はただの楕円形の輪郭だけで、前を向いているときと少しも変わらない。
「これからは、誰にも横顔を見られないようにしよう」
と、僕は考えた。が、そう考えたあとで、すぐにそれがこの場の状況とはちぐはぐな間の抜けた考えだと気づいた。
僕はもう一度、右手で頭を弾いた。力が入りすぎたのか、頭は大きく揺れ、めまいがした。急いで揺れを止めた。
「風船だ……」
言葉と同時に胸の奥から熱いものがこみ上げてきて、僕は泣き出した。
これではもう、まともな社会生活を送ることはできないだろう。もちろん、結婚することもできないだろう。頭がゴム風船になった男を夫に持ちたがる女などいないだろう。
そんなことを考えながら、僕は泣いた。
「散髪、しましょうか?」
主人が、ふいに事務的に言った。
「もちろん、ハサミやカミソリなど、刃物を使う以上、あなたの頭が割れてしまう恐れが十分あるわけですが……」
ハサミ、カミソリという言葉が、これほど恐ろしく耳に響いたことはなかった。
「いいえ、いいえ、もう、このままでいいです……」
僕はそう言った。これ以上、ひどい目にはもうあいたくなかった。ゴム風船の頭は元に戻らないとしても、とにかく割れてしまうよりは、このままでも頭があるほうがましだと思った。
僕は泣きながら椅子から立ち上がった。
と、体を前にかがめた拍子に頭が大きく揺れて、鏡の下の棚に置いてあったカミソリの刃に触れた。
たちまち僕の頭は粉々に飛び散った。
僕は、破片になった目から涙を流して、なお泣き続けた。
すると、やはり破片になってしまった僕の耳に、主人と、いつのまにか戻ってきたらしい隣の客のカラカラという笑い声とともに、
「いや、あの人もこれでよかった」
という、聞き慣れない、不思議に説得力を持った声が聞こえてきた。















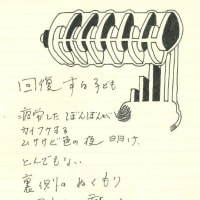










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます