僕は、これまで一度も、女の子とつきあったことがない。それには、僕の自意識過剰なところも大いに関係がある。僕は今でも女の子と話をするだけで心臓が破裂せんばかりになるし、声が上ずったりする。が、僕が女の子とつきあえない理由はそれだけではない。僕は、誰かを好きになると、すぐにこう考えるのだ。「もしも、この娘(こ)とうまくいって、いつまで続くだろうか」と。もちろん、いつまで続くかは予想できない。しかしそれと同時に、「いつかは終わる」ということも明らかすぎるほど分るのだ。いつか、が、いつであっても、うまくいかなくなる時が来るに違いない。そうなった時のことを考えると、第一歩で、僕はつまずいてしまう。童貞の言い訳ネ、と女の子に言われそうだが、僕は女の子に、そう言われても、はい、としか言えない。女の子は、体の中に、世界の目的をそのまま持っているのだから、強いのはあたり前なのだ。だが、僕は、それを持っていない。僕には、自分に目的があるとは思えない。僕は、どのような苦労も避けられるなら避けたい。だから、女の子とうまくいかなくなった時のことを考えるとうんざりする。そのうんざりを避けるためなら、うまくいく、ことを投げ出してかまわないと思うのだ。童貞の、醜男の負け惜しみだと言われても、確かに、それもそうなのだ、と言うしかない。いずれにせよ、或る女の子とつきあうなら、やがてはうんざりする関係になって別れるか、結婚するかのどちらかだ。そして結婚には、義務が伴う。うんざりも、義務も、僕は両方ともイヤだ。――そうなるとは限らないぜ、と僕に言う人もいる。精神的にも肉体的にも、しっかり結ばれて、幸福になれる場合もあるのではないか、と。そうかもしれない。しかし、それは少数だろう。僕は凡人なのだから、そんな気高いものに触れられるわけがない。僕のやり方は一つだ。原因を作らないこと。それしか知らない。
テレビでは、一幕目が終わりかけていた。
タコ焼き屋の娘が、どこかの会社の社長に結婚を迫られているのだが、娘には、好きな男がいる。だがその男は、土方の人夫で、タコ焼き屋の主人としては、やはり、社長のところへ嫁いでほしい、と思っている。今画面には、土方の男と、タコ焼き屋の娘が二人きりで、しんみりとした雰囲気である。――本当に、よくあるパターンというやつだが、僕は、これが大好きなのだ。お笑い花月劇場は、泣かせる。人情というのは、泣かせる。僕は、今では、ひどく安っぽくなった、人情が好きだ。ほのぼのさせるような、インテリやクリスタル族が軽蔑するようなものが好きだ。僕は、できるなら、お笑い花月劇場の登場人物のように生きたい。何度も、そう思って、そうしようと、それこそ数百回も挑戦した。朝起きて、「今日から僕は変わるんだ」と何度も呟いて、外へ出た。が、一日を終え、帰ってくる時には、もう昨日までの、不機嫌な顔に戻っていた。全ては徒労だった。周囲の人々は、現代人とかいう人々は、みんなかしこかった。中途半端故にかしこかった。僕は毎日、泣いておうちへ帰る。僕は、小学校の時、「どうとく」の時間に習ったことを守っている。ところが、他人のためになることをしたくても何一つできず、他人のためになることをすると、親孝行ができない。親孝行をしようと思えば、他人のことなどかまっていられないらしい。不幸な人に手をさしのべて、あなた自身にも責任があると言えば非難される。幸福な人は、不幸な人をかえりみない。そして僕が、そう言うと、はやく大人になりなさいと言われる。大人は自分のコピーを残そうとしているだけなのに、犯罪者は、不道徳だと言い、不道徳でも犯罪者でなければ、あの人は大物だと言う。人間同士のつながりが大切です、と大人は言い、ドアに鍵をかけて、プライバシーは大切と言う。けれど鍵をかけ続ける人は、変人呼ばわりされる。陰口をたたかない人は陰口をたたかれる。正直が一番、と言いながら、嘘も方便と言い、現代人は孤独だ、という講演会に千人の人が集まって微笑みを交わす。世の中は難しい。この難しい世の中が、一体何のためにあるのか、僕にはぜんぜん分らない。きっと僕一人、頭が死ぬほど悪いのだろう。だが、僕の頭が悪かろうが、そんなことはどうでもいい。僕には、人間に、ハンショク以上のどんな目的があるとも思われないし、そのハンショクが、ゴキブリのハンショクより高級であるのかどうかも分らない。ただ一つ分るのは、ぜんぜん意味の分らないこの世界で、苦労するのも努力するのもゴメンだということだけだ。世界中が、お笑い花月劇場だ。ただし誰も自分が喜劇役者だと認めはしないだろうが・・・・・・。
――気がつくと、母が泣いていた。僕は灰皿で、フィルターまで火の届いた煙草をもみ消し、ハネ起きた。
「どうしたん?」
母は、エプロンを顔に当てて肩をふるわせている。
「お前は・・・・・・お前っていう子は・・・・・・かあさん心配で死にそうなよ」
ああ、お母さん。母さん。僕が、いい子すぎるばっかりに・・・・・・。母さん泣かないで。母さんを泣かせているのは僕ではありませんよ。
「だいじょうぶ、心配ない、ない。オレ先生になる。ちゃんと国語の先生になるけぇ。泣きんさんな、母さん」
テレビの中のセリフではない。僕が言ったのだ。
「いやいやなるんならやめんさい」
「いやいやじゃない。ほんま。オレ先生が好きじゃけぇ。子どもに教えるんは、おもしろいし」
母は、僕のこんな言い訳を信じたわけではないだろうが、ようやく泣き止んだ。
「いっそ幸わせになれんね、私は」
母は言った。そうだ。しあわせになろうとする人は、しあわせになれないのだ。母はかわいそうだ。だが、どうしようもない。
「コーヒー作ろうか」
母が言った。
「うん、ちょうど飲みたかったんじゃ」
僕はほっとして言った。
母は、台所で、インスタントコーヒーを作り始めた。
一幕目は終わっていた。土方の男が、タコ焼き屋の娘に、「もう嫌いになった言うとるやろが。しつこい女やで」と言った。それは、男が、その娘のことを考えて身を引くために、わざと言ったのだが、僕は、それだけで、ホロリときた。
「おもしろい?」
コーヒーカップを二つ運んできながら母が言った。
「うん」
僕は、涙を流していた。二幕目で、二人が結ばれると分っていながらも、その土方の男の姿に感動した。
「馬鹿じゃね、お前は」
テーブルの上に、コーヒーカップを置きながら、母は、久しぶりに、むかしの母のように微笑んで言った。
「ほんと、バカじゃね、この子は。子どものころから何を見てもすぐ泣くんじゃけぇ」
僕は、コーヒーカップを手に取った。にじんでぼんやりしている茶色の液体を一口飲んだ時、僕は、色々なことが悲しくなってきて、思わずしゃくりあげた。
テレビでは、一幕目が終わりかけていた。
タコ焼き屋の娘が、どこかの会社の社長に結婚を迫られているのだが、娘には、好きな男がいる。だがその男は、土方の人夫で、タコ焼き屋の主人としては、やはり、社長のところへ嫁いでほしい、と思っている。今画面には、土方の男と、タコ焼き屋の娘が二人きりで、しんみりとした雰囲気である。――本当に、よくあるパターンというやつだが、僕は、これが大好きなのだ。お笑い花月劇場は、泣かせる。人情というのは、泣かせる。僕は、今では、ひどく安っぽくなった、人情が好きだ。ほのぼのさせるような、インテリやクリスタル族が軽蔑するようなものが好きだ。僕は、できるなら、お笑い花月劇場の登場人物のように生きたい。何度も、そう思って、そうしようと、それこそ数百回も挑戦した。朝起きて、「今日から僕は変わるんだ」と何度も呟いて、外へ出た。が、一日を終え、帰ってくる時には、もう昨日までの、不機嫌な顔に戻っていた。全ては徒労だった。周囲の人々は、現代人とかいう人々は、みんなかしこかった。中途半端故にかしこかった。僕は毎日、泣いておうちへ帰る。僕は、小学校の時、「どうとく」の時間に習ったことを守っている。ところが、他人のためになることをしたくても何一つできず、他人のためになることをすると、親孝行ができない。親孝行をしようと思えば、他人のことなどかまっていられないらしい。不幸な人に手をさしのべて、あなた自身にも責任があると言えば非難される。幸福な人は、不幸な人をかえりみない。そして僕が、そう言うと、はやく大人になりなさいと言われる。大人は自分のコピーを残そうとしているだけなのに、犯罪者は、不道徳だと言い、不道徳でも犯罪者でなければ、あの人は大物だと言う。人間同士のつながりが大切です、と大人は言い、ドアに鍵をかけて、プライバシーは大切と言う。けれど鍵をかけ続ける人は、変人呼ばわりされる。陰口をたたかない人は陰口をたたかれる。正直が一番、と言いながら、嘘も方便と言い、現代人は孤独だ、という講演会に千人の人が集まって微笑みを交わす。世の中は難しい。この難しい世の中が、一体何のためにあるのか、僕にはぜんぜん分らない。きっと僕一人、頭が死ぬほど悪いのだろう。だが、僕の頭が悪かろうが、そんなことはどうでもいい。僕には、人間に、ハンショク以上のどんな目的があるとも思われないし、そのハンショクが、ゴキブリのハンショクより高級であるのかどうかも分らない。ただ一つ分るのは、ぜんぜん意味の分らないこの世界で、苦労するのも努力するのもゴメンだということだけだ。世界中が、お笑い花月劇場だ。ただし誰も自分が喜劇役者だと認めはしないだろうが・・・・・・。
――気がつくと、母が泣いていた。僕は灰皿で、フィルターまで火の届いた煙草をもみ消し、ハネ起きた。
「どうしたん?」
母は、エプロンを顔に当てて肩をふるわせている。
「お前は・・・・・・お前っていう子は・・・・・・かあさん心配で死にそうなよ」
ああ、お母さん。母さん。僕が、いい子すぎるばっかりに・・・・・・。母さん泣かないで。母さんを泣かせているのは僕ではありませんよ。
「だいじょうぶ、心配ない、ない。オレ先生になる。ちゃんと国語の先生になるけぇ。泣きんさんな、母さん」
テレビの中のセリフではない。僕が言ったのだ。
「いやいやなるんならやめんさい」
「いやいやじゃない。ほんま。オレ先生が好きじゃけぇ。子どもに教えるんは、おもしろいし」
母は、僕のこんな言い訳を信じたわけではないだろうが、ようやく泣き止んだ。
「いっそ幸わせになれんね、私は」
母は言った。そうだ。しあわせになろうとする人は、しあわせになれないのだ。母はかわいそうだ。だが、どうしようもない。
「コーヒー作ろうか」
母が言った。
「うん、ちょうど飲みたかったんじゃ」
僕はほっとして言った。
母は、台所で、インスタントコーヒーを作り始めた。
一幕目は終わっていた。土方の男が、タコ焼き屋の娘に、「もう嫌いになった言うとるやろが。しつこい女やで」と言った。それは、男が、その娘のことを考えて身を引くために、わざと言ったのだが、僕は、それだけで、ホロリときた。
「おもしろい?」
コーヒーカップを二つ運んできながら母が言った。
「うん」
僕は、涙を流していた。二幕目で、二人が結ばれると分っていながらも、その土方の男の姿に感動した。
「馬鹿じゃね、お前は」
テーブルの上に、コーヒーカップを置きながら、母は、久しぶりに、むかしの母のように微笑んで言った。
「ほんと、バカじゃね、この子は。子どものころから何を見てもすぐ泣くんじゃけぇ」
僕は、コーヒーカップを手に取った。にじんでぼんやりしている茶色の液体を一口飲んだ時、僕は、色々なことが悲しくなってきて、思わずしゃくりあげた。















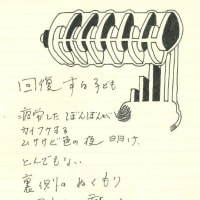










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます