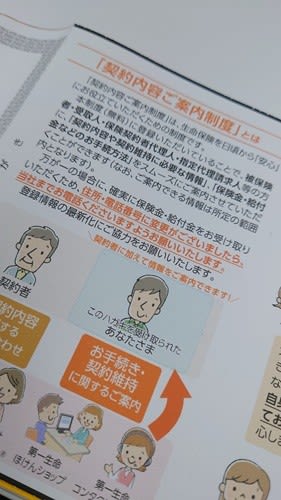年末のあいさつ回りのなかで、四方山話のネタとして私が父と任意後見人契約を結んだ、という話を出すことがあります。
合う相手さんもそろそろ六十歳の還暦間近な方もいて、そうなると親御さんの年齢も八十代後半という方が多くいます。
まだまだ健康な親御さんが多い中、たまに「母が認知症で」とか「そろそろ何か考えなくてはならないと思っていたところでした」という方がおられます。
しかし公務員で転勤が多い身分でいる限り、自分が家を建てる終の棲家と親御さんが住んでいる土地が近くになるとは限りません。
まして全国転勤ともなると、自分は北海道にいるけれど親は内地の地方都市で暮らしていて、もう今後親の近くに住めるようなことにはならない、と割い切らざるを得ない人も多くいます。
私自身のように、親の家と私の家とが車で30分くらいのところにいるなどというのは本当に稀なことです。
さらには「親とはもう没交渉でもう何年も会っていない」とか、「自分は次男で、長男がいるけれど兄とは仲が悪くてもう何年も会っていない」といった家族関係の良し悪しのようなものも見えてきます。
「今は何も考えていませんでしたが、これからのどこかで家族と話し合って意思を確認しておくほうが良いことがわかりました」
敢えて意識の外に置いていたような老親の問題も、いつかは対処せざるを得なくなるわけで、いかに平時に冷静に準備ができるか、考えておくほうが良いのです。
◆
子供の時は、小中高大と義務教育から高等教育まで知識やスキルを学ぶ時間がたっぷり与えられます。
そしてそれは大人になるための準備期間として社会が子供たちに与えている猶予期間です。
子供から「どうして子供は勉強しなくちゃいけないの?」と訊かれたら大人は、「そうやって大人になる準備をするんだよ」と答えるでしょう。
子供が大人になるためには勉強の場所と時間が与えられているのに、大人が老人になるための勉強は時間も場所も与えられてはいません。
年寄りになるための勉強もあるはずです。
そのことに気が付くか、目の前で起きている事態に引きずられるようにして問題に直面するかは人それぞれですが、「親も自分も老いる」ということへの知識やスキルを身に着ける機会を社会は与えてくれません。
少しでも早くそのことに気が付いて、人に聞いたり勉強を始めるということは大切なことだとおもいます。
もっとも、いざ勉強をしようと思うと、世の中には本も情報もあふれていて、自分に適した情報は何かに戸惑うかもしれません。
親が大変になったら、まずお住まいの土地の地域包括支援センターに相談をする、ということだけ覚えておきましょう。
プロのアドバイスは必ず役に立つはずです。
歳を取ることへの勉強は生涯学習です。