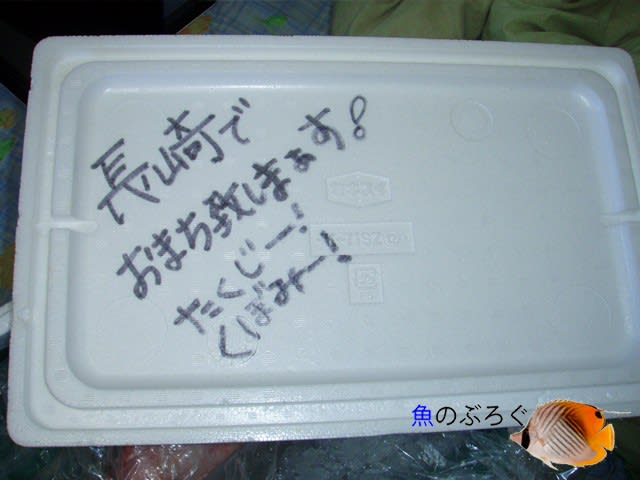先週の金曜日、静岡県焼津港「長兼丸」の長谷川さんの船に乗せていただく機会があったのでしたが、その際に採集されたソコダラ科のトウジンの仲間(トウジン属)。トウジン属は以前に「トウジン」の記事でも書いたのですが、どうしても似た種類ばかりで難しいものです。この種類は体側に薄いバンドがあり、ミヤコヒゲやムスジソコダラの仲間だと思います。
トウジンの仲間は同定が大変難しい。その理由は体側の斑紋だけでなく、鱗の様子や、果ては手触りまでが同定のキーになるから。
トウジンの仲間のうち、とげとげした鱗をもち、体側の後半に太い横帯を有する種は3種いるようで、これらは頭頂部の鱗の形状により区別できる、と魚類検索。

これが頭頂部。頭頂の鱗は両眼のちょうど中央あたりの鱗。拡大していってもどうも隆起線が1本多いように見える。ということはミヤコヒゲであろう。ミヤコヒゲは水深360~760mに生息し、その分布域は房総半島から沖縄舟状海盆とかなり広域におよび、駿河湾ももちろん分布域に入る。
対してほかのズナガソコダラ・ムスジソコダラは九州-パラオ海嶺にのみ分布とある。これらのうち、どちらか忘れてしまったが、たしかムスジソコダラのほうは以前に駿河湾の海底にいるのを見たような気もする。もしかしたらムスジソコダラも駿河湾にいるのかもしれない。念のためもう一度確認したい。
いずれにせよ大事なのは、本種の肉は白身でありとてもおいしい種類ということである。そのため標本の確保が難しい。もしかなうのであればもう一度標本を入手したいのだが。