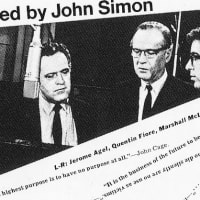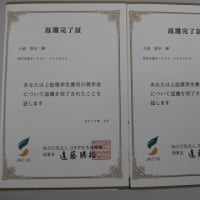ルイ・カストロ『パジャマを着た神様:ボサノヴァの歴史外伝』国安真奈訳, 音楽之友社, 2003.
『ボサノヴァの歴史』の続編で、原著は2001年のA onda que se ergueu no mar。原題をGoogle翻訳にかけると「海の中で上昇した波」と訳された。全19章あるが、それぞれがミュージシャンを一人か二人採りあげてのオマージュ・エッセイとなっている。邦題の「パジャマを着た神様」とはジョアン・ジルベルトのこと。彼のほか、ジョビン、ナラ・レオン、ジョアン・ドナートなどが採りあげられている。日本ではあまり知られていないボサノバ勃興前の歌手、オルランド・シルヴァ、ディック・ファルネイ、ルーシオ・アルヴィスについても詳しい。なぜかブリジット・バルドーのリオ滞在記もある。
ジョビンの音楽の影響関係の考察──彼の曲に付けられた英詞がいかに酷かったか、というのもある──や、ジョアンの隠遁生活については複数章にまたがる。特に興味深かったのは、テノーリオ・ジュニオールという、軍事政権下のアルゼンチンで無実の罪で拘束されて拷問死したピアニストの悲劇をまくらにした章。1966年頃にブラジルのレコード会社は、「国内で売れない」というのを理由に、インスト系の演奏者に録音機会を与えなくなってしまったという。その結果、歌手を除いたブラジル人演奏家の大量国外移住(主に米へ)が起こり──例えばデオダートやセルジオ・メンデス、アイルト・モレイラ──、海外でのボサノバ~ジャズ・サンバの普及につながった、と。他の章では日本にも少々言及があって、1990年代にはリオの中古レコード店で一心不乱に1950年代~60年代の中古盤を探す日本人バイヤーがいた(おそらくリイシューのため)とか、ナラ・レオン晩年の録音は日本のレコード会社の企画だったと記されている。
惜しむらくは、ブラジルの国内事情以外では、米国との関係に視野が限られており、1990年代のボサノバ再評価の理由を把握してきれいないこと。そのためには1980年代の英国ネオアコや、ニッチな需要にも応えようとした日本のバブル時代の経済力(上のナラ・レオンがヒントになったはず)に言及する必要があると思うのだが、まあそれは著者の仕事ではないかもしれない。あと、著者はボサノバ至上主義者らしく、その後に出てきたMPBを批判している。通常どっちも好きだろと思うのだが、ブラジル国内では違うんだろうな。
『ボサノヴァの歴史』の続編で、原著は2001年のA onda que se ergueu no mar。原題をGoogle翻訳にかけると「海の中で上昇した波」と訳された。全19章あるが、それぞれがミュージシャンを一人か二人採りあげてのオマージュ・エッセイとなっている。邦題の「パジャマを着た神様」とはジョアン・ジルベルトのこと。彼のほか、ジョビン、ナラ・レオン、ジョアン・ドナートなどが採りあげられている。日本ではあまり知られていないボサノバ勃興前の歌手、オルランド・シルヴァ、ディック・ファルネイ、ルーシオ・アルヴィスについても詳しい。なぜかブリジット・バルドーのリオ滞在記もある。
ジョビンの音楽の影響関係の考察──彼の曲に付けられた英詞がいかに酷かったか、というのもある──や、ジョアンの隠遁生活については複数章にまたがる。特に興味深かったのは、テノーリオ・ジュニオールという、軍事政権下のアルゼンチンで無実の罪で拘束されて拷問死したピアニストの悲劇をまくらにした章。1966年頃にブラジルのレコード会社は、「国内で売れない」というのを理由に、インスト系の演奏者に録音機会を与えなくなってしまったという。その結果、歌手を除いたブラジル人演奏家の大量国外移住(主に米へ)が起こり──例えばデオダートやセルジオ・メンデス、アイルト・モレイラ──、海外でのボサノバ~ジャズ・サンバの普及につながった、と。他の章では日本にも少々言及があって、1990年代にはリオの中古レコード店で一心不乱に1950年代~60年代の中古盤を探す日本人バイヤーがいた(おそらくリイシューのため)とか、ナラ・レオン晩年の録音は日本のレコード会社の企画だったと記されている。
惜しむらくは、ブラジルの国内事情以外では、米国との関係に視野が限られており、1990年代のボサノバ再評価の理由を把握してきれいないこと。そのためには1980年代の英国ネオアコや、ニッチな需要にも応えようとした日本のバブル時代の経済力(上のナラ・レオンがヒントになったはず)に言及する必要があると思うのだが、まあそれは著者の仕事ではないかもしれない。あと、著者はボサノバ至上主義者らしく、その後に出てきたMPBを批判している。通常どっちも好きだろと思うのだが、ブラジル国内では違うんだろうな。