「獣の奏者」探求編、完結編で感動して、以前2巻読んだことがあった「守り人」シリーズを
また読み進めて、とうとう完読してしまった。
バルサ、チャグム本当にお疲れ様。
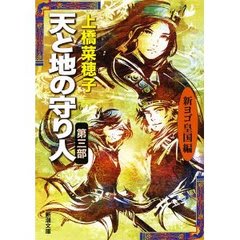
精霊の守り人
闇の守り人
夢の守り人
虚空の旅人
神の守り人 来訪編 帰還編
蒼路の旅人
天と地の守り人 ロタ王国編 カンバル王国編 新ヨゴ王国編
それにしても上橋さんはやっぱりすごい人だ。
「絶対的視点のない物語」を書きたいと、どれかのあとがきにあったけど
敵味方という単純二極ではなく、攻め入る国、攻められる国それぞれの事情を
等しい感情で描いている。立場の違う個人の身近な実情を知ると
そうならざるを得ない決断や行動を無下に非難できない。
今、現実にも世界中が混沌とした雰囲気に包まれており、
たとえば日韓、日中の微妙な関係を保つためにも、
上橋さんような、ある意味冷静で合理的で、さらには国という囲いを超えた考え方が必要なのだろう。
描写もすばらしい。
馬のあしらいや武士の立ち姿、動物のちょっとした動きなど
たった一行の表現でありありと情景が目に浮かび、まるでその場にいるような気持ちになる。
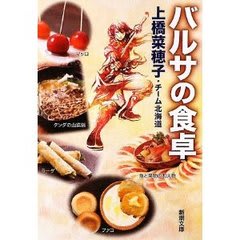
そうそう「バルサの食卓」という本も買ってしまった。
寒い、つらい、さびしい、悲しい、そんな場面で温かい食べ物が登場すると
読んでいるだけで胃袋からぽかっと温かくなったっけ。
また読み進めて、とうとう完読してしまった。
バルサ、チャグム本当にお疲れ様。
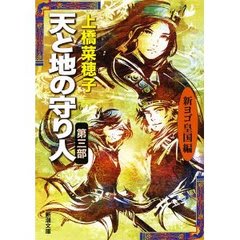
精霊の守り人
闇の守り人
夢の守り人
虚空の旅人
神の守り人 来訪編 帰還編
蒼路の旅人
天と地の守り人 ロタ王国編 カンバル王国編 新ヨゴ王国編
それにしても上橋さんはやっぱりすごい人だ。
「絶対的視点のない物語」を書きたいと、どれかのあとがきにあったけど
敵味方という単純二極ではなく、攻め入る国、攻められる国それぞれの事情を
等しい感情で描いている。立場の違う個人の身近な実情を知ると
そうならざるを得ない決断や行動を無下に非難できない。
今、現実にも世界中が混沌とした雰囲気に包まれており、
たとえば日韓、日中の微妙な関係を保つためにも、
上橋さんような、ある意味冷静で合理的で、さらには国という囲いを超えた考え方が必要なのだろう。
描写もすばらしい。
馬のあしらいや武士の立ち姿、動物のちょっとした動きなど
たった一行の表現でありありと情景が目に浮かび、まるでその場にいるような気持ちになる。
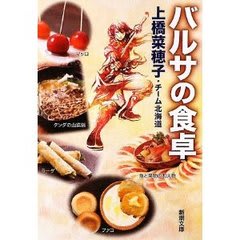
そうそう「バルサの食卓」という本も買ってしまった。
寒い、つらい、さびしい、悲しい、そんな場面で温かい食べ物が登場すると
読んでいるだけで胃袋からぽかっと温かくなったっけ。












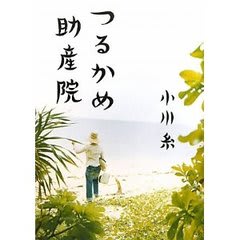



 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック
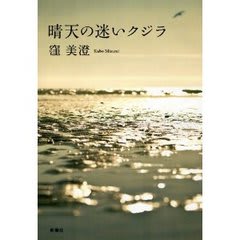
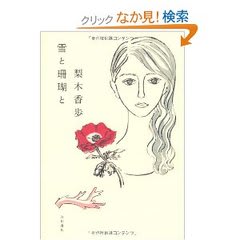

 。
。




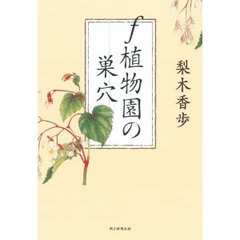
 weblio辞書より「犬雁足」
weblio辞書より「犬雁足」 weblio辞書より「月下香」
weblio辞書より「月下香」 weblio辞書より「ムジナモ」貉のシッポみたいな食虫植物
weblio辞書より「ムジナモ」貉のシッポみたいな食虫植物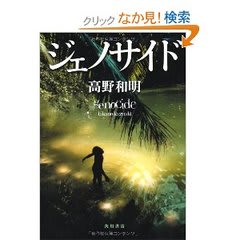
 物語に登場するハイズマン・レポートのようなことをかつて学生のときに教えられた記憶がある。久しぶりにそんな危機感を思い出しました。
物語に登場するハイズマン・レポートのようなことをかつて学生のときに教えられた記憶がある。久しぶりにそんな危機感を思い出しました。 と明るい本を読むことにしました。
と明るい本を読むことにしました。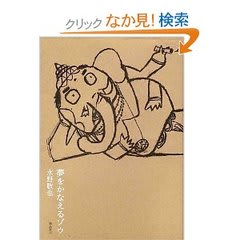
 」と思った覚えがあるのに、顔が思い出せない。
」と思った覚えがあるのに、顔が思い出せない。 ネット文明は本当にベンリ!
ネット文明は本当にベンリ! 、この幸福感はハウツーものを読んで失敗する典型的なパターンで
、この幸福感はハウツーものを読んで失敗する典型的なパターンで 自分の「夢」が人に喜んでもらえるものすなわち「愛」ならば必ずや成功する。
自分の「夢」が人に喜んでもらえるものすなわち「愛」ならば必ずや成功する。


