verse, prose, and translation
Delfini Workshop
博士の愛した数式
2007-02-23 / 映画
金曜日、 。「博士の愛した数式」この映画は、公開されたときには、さほど関心がなかったのだが、後で、観たくなって、TSUTAYAでずっとチェックしていた。やっと借りることができた。非常に、いい映画だった。登場人物は、4人と言っていい。博士、その家政婦、その息子、博士の義理の姉。交通事故で、博士の記憶は、80分しかもたない。この映画は、数学の美しさを描きながら、人と人の結びつきが、数学のように、ピュアなものになりえることを、示そうとしているように思えた。
。「博士の愛した数式」この映画は、公開されたときには、さほど関心がなかったのだが、後で、観たくなって、TSUTAYAでずっとチェックしていた。やっと借りることができた。非常に、いい映画だった。登場人物は、4人と言っていい。博士、その家政婦、その息子、博士の義理の姉。交通事故で、博士の記憶は、80分しかもたない。この映画は、数学の美しさを描きながら、人と人の結びつきが、数学のように、ピュアなものになりえることを、示そうとしているように思えた。
現実という名のもろもろの諸条件の中で、われわれは生きていかなければならない。ちょうど、それは、一枚の紙に「直線」を描いたとき、それは常に直線ではありえず、両端を結んだ「線分」にしかなりえないように、現実は現れる。しかし、無限の直線の広がりは、人の心の中に、確かに存在する。これもまた、大いなる現実である。
博士が愛した数式とは、オイラーの等式のことだった。eiπ + 1 = 0
この映画に触発されて、積読になっていた数学関連の本をパラパラ読んだ。ぼくは、数学的センスはないが、ユークリッドが、「素数は永遠に続き、無限にある」ことを証明したシンプルでエレガントな証明に素直に感動することができたのだった。
 。「博士の愛した数式」この映画は、公開されたときには、さほど関心がなかったのだが、後で、観たくなって、TSUTAYAでずっとチェックしていた。やっと借りることができた。非常に、いい映画だった。登場人物は、4人と言っていい。博士、その家政婦、その息子、博士の義理の姉。交通事故で、博士の記憶は、80分しかもたない。この映画は、数学の美しさを描きながら、人と人の結びつきが、数学のように、ピュアなものになりえることを、示そうとしているように思えた。
。「博士の愛した数式」この映画は、公開されたときには、さほど関心がなかったのだが、後で、観たくなって、TSUTAYAでずっとチェックしていた。やっと借りることができた。非常に、いい映画だった。登場人物は、4人と言っていい。博士、その家政婦、その息子、博士の義理の姉。交通事故で、博士の記憶は、80分しかもたない。この映画は、数学の美しさを描きながら、人と人の結びつきが、数学のように、ピュアなものになりえることを、示そうとしているように思えた。現実という名のもろもろの諸条件の中で、われわれは生きていかなければならない。ちょうど、それは、一枚の紙に「直線」を描いたとき、それは常に直線ではありえず、両端を結んだ「線分」にしかなりえないように、現実は現れる。しかし、無限の直線の広がりは、人の心の中に、確かに存在する。これもまた、大いなる現実である。
博士が愛した数式とは、オイラーの等式のことだった。eiπ + 1 = 0
この映画に触発されて、積読になっていた数学関連の本をパラパラ読んだ。ぼくは、数学的センスはないが、ユークリッドが、「素数は永遠に続き、無限にある」ことを証明したシンプルでエレガントな証明に素直に感動することができたのだった。
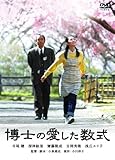 | 博士の愛した数式 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 角川エンタテインメント |
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
映画「墨攻」
2007-02-10 / 映画
土曜日、 のち
のち 。終日、仕事。
。終日、仕事。
午後から時間ができたので、映画「墨攻」を観に行って来た。とにかく、「墨家」という集団の興味深さは尋常ではない。それに惹かれて観てきたのであるが、映画としては、まあ、70点くらいではないだろうか。戦闘・軍事シーンが95%なので、女性や戦闘に興味のない人は飽きるかもしれない。ぼくも多少飽きた。戦闘シーンや軍事的なシーンはメーンでも構わないと思うが、もっと技術的に丁寧に、墨家の知恵や創意工夫、専門知識を描いた方が良かったと思う。また、墨家の思想は歴史的に並外れてユニークなのだから、その点も突っ込んで欲しかった。革離という墨家の主人公を演じた、香港スター、アンディ・ラウはなかなか良かったと思う。演技も中国語の音も耳に心地よかった。敵方の趙軍の名将、巷淹中を演じた韓国のスター、アン・ソンギも重厚な演技で素晴らしかった。あのヨンさまをイメージしてしまうせいか、韓国の男優の声は低いという印象があるが、アン・ソンギの声は高く、ときどきかすれて、渋い感じを出していた。ただ、中国人キャストの中に入ると、中国語ネイティブではないせいで、若干、中国語の音に硬さが感じられた。
この映画は、コミック「墨攻」を原作にしているが、全8巻もあるコミックをすべて映画化したわけではないだろう。印象的なシーンを映画化したものと思う。革離が墨家内部の反対を押し切って、梁の救援に来た経緯や当時の墨家の社会的な位置づけなどは省略されている。梁の城を革離が守るという一点に焦点を当てて、この映画は作られている。
この映画を観ても、当然、墨家の謎は解けない。ますます深まる。しかし、ますます、墨家と諸子百家に興味を持った。帰りに早速、書店でコミック「墨家」とビギナーズクラシック『老子・荘子』(角川書店)を購入。中国の戦国時代には、たくさん面白い思想家が出たが、日本の戦国時代はどうだったのか。その辺も気になりだしている。
 のち
のち 。終日、仕事。
。終日、仕事。午後から時間ができたので、映画「墨攻」を観に行って来た。とにかく、「墨家」という集団の興味深さは尋常ではない。それに惹かれて観てきたのであるが、映画としては、まあ、70点くらいではないだろうか。戦闘・軍事シーンが95%なので、女性や戦闘に興味のない人は飽きるかもしれない。ぼくも多少飽きた。戦闘シーンや軍事的なシーンはメーンでも構わないと思うが、もっと技術的に丁寧に、墨家の知恵や創意工夫、専門知識を描いた方が良かったと思う。また、墨家の思想は歴史的に並外れてユニークなのだから、その点も突っ込んで欲しかった。革離という墨家の主人公を演じた、香港スター、アンディ・ラウはなかなか良かったと思う。演技も中国語の音も耳に心地よかった。敵方の趙軍の名将、巷淹中を演じた韓国のスター、アン・ソンギも重厚な演技で素晴らしかった。あのヨンさまをイメージしてしまうせいか、韓国の男優の声は低いという印象があるが、アン・ソンギの声は高く、ときどきかすれて、渋い感じを出していた。ただ、中国人キャストの中に入ると、中国語ネイティブではないせいで、若干、中国語の音に硬さが感じられた。
この映画は、コミック「墨攻」を原作にしているが、全8巻もあるコミックをすべて映画化したわけではないだろう。印象的なシーンを映画化したものと思う。革離が墨家内部の反対を押し切って、梁の救援に来た経緯や当時の墨家の社会的な位置づけなどは省略されている。梁の城を革離が守るという一点に焦点を当てて、この映画は作られている。
この映画を観ても、当然、墨家の謎は解けない。ますます深まる。しかし、ますます、墨家と諸子百家に興味を持った。帰りに早速、書店でコミック「墨家」とビギナーズクラシック『老子・荘子』(角川書店)を購入。中国の戦国時代には、たくさん面白い思想家が出たが、日本の戦国時代はどうだったのか。その辺も気になりだしている。
 | 墨攻 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| アミューズソフトエンタテインメント |
コメント ( 2 ) | Trackback ( )
月はどっちに出ている
2006-11-27 / 映画
月曜日、 。旧暦、10月7日。
。旧暦、10月7日。
崔洋一監督の「月はどっちに出ている」(1993年)を観た。崔監督は、去年、「血と骨」を観て、圧倒されてから、関心のある監督だった。原作は梁石日「タクシー狂躁曲」。梁石日は「血と骨」の原作の著者でもある。
映画「血と骨」でディープな暴力とそれによる神話作用に圧倒されていたので、この映画の現実を笑いでくるんだアプローチに、最初は、肩透かしを食ったような感じた。しかし、観終わって、これはかなり計算された、優れた作品だと思うようになった。せりふは、現実にかわされている本当に近い感じが出ている。公の場で、このまま、やりとりしたら、「差別だ!」といきりたつ者も出てくるだろう。その意味で、笑わせながらも現実に肉薄する崔監督の果敢さは、特筆すべきだと思う(映画の終わりに、言い訳のように、「この映画はフィクションであり、現実の団体・人物とはいっさい係わりがありません」という白けた字幕が出ることがあるが、この映画は、一番最初に「この映画はすべて事実です」と字幕が流れる!)。
この映画では、役者の演技が絶妙で、唸らされる。主演の岸谷五朗のとぼけたちょい悪ぶり、フィリピンパブのチーママ役のルビー・モレノの大阪弁の可笑しさ、したたかさ、そして、かわいらしさ。主演二人の名演技を食ってしまうような脇役陣の凄さ。中でもホソ役の有薗芳記の哀しい演技には心打たれた。元ボクサーで、カネがいつもなく、かみさんに逃げられ、故郷に子供たちを残してタクシー運転手しているパンチドランカーの小男を見事に演じている。忠男(岸谷)とコニー(モレノ)がエッチしている部屋に何度も電話してきて、「一瞬、カネ貸してくれよぉ」と迫る可笑しさ。このせりふは、何度も何度も白痴のように繰り返され、「おもしろうてやがてかなしき鵜舟かな」という感じになってくる。もう一人、忘れられないのが麿赤児である。実に上手い! あの怪優が、常に「ですます調」を崩さないタクシー会社の小心な統括責任者を演じている。
この映画は、一面で、アジアでは、まだ冷戦が終わっていないことを想起させる。他方で、在日朝鮮人や在日韓国人、フィリピン人、イラン人といった、日本の周辺に生きる人々が、生命エネルギーをほとばしらせ、抑圧的な現実と渡り合っていく姿が描かれている。笑わされて、哀しくなって、最後に、元気出して行こう! そんな気にさせる映画である。
 。旧暦、10月7日。
。旧暦、10月7日。崔洋一監督の「月はどっちに出ている」(1993年)を観た。崔監督は、去年、「血と骨」を観て、圧倒されてから、関心のある監督だった。原作は梁石日「タクシー狂躁曲」。梁石日は「血と骨」の原作の著者でもある。
映画「血と骨」でディープな暴力とそれによる神話作用に圧倒されていたので、この映画の現実を笑いでくるんだアプローチに、最初は、肩透かしを食ったような感じた。しかし、観終わって、これはかなり計算された、優れた作品だと思うようになった。せりふは、現実にかわされている本当に近い感じが出ている。公の場で、このまま、やりとりしたら、「差別だ!」といきりたつ者も出てくるだろう。その意味で、笑わせながらも現実に肉薄する崔監督の果敢さは、特筆すべきだと思う(映画の終わりに、言い訳のように、「この映画はフィクションであり、現実の団体・人物とはいっさい係わりがありません」という白けた字幕が出ることがあるが、この映画は、一番最初に「この映画はすべて事実です」と字幕が流れる!)。
この映画では、役者の演技が絶妙で、唸らされる。主演の岸谷五朗のとぼけたちょい悪ぶり、フィリピンパブのチーママ役のルビー・モレノの大阪弁の可笑しさ、したたかさ、そして、かわいらしさ。主演二人の名演技を食ってしまうような脇役陣の凄さ。中でもホソ役の有薗芳記の哀しい演技には心打たれた。元ボクサーで、カネがいつもなく、かみさんに逃げられ、故郷に子供たちを残してタクシー運転手しているパンチドランカーの小男を見事に演じている。忠男(岸谷)とコニー(モレノ)がエッチしている部屋に何度も電話してきて、「一瞬、カネ貸してくれよぉ」と迫る可笑しさ。このせりふは、何度も何度も白痴のように繰り返され、「おもしろうてやがてかなしき鵜舟かな」という感じになってくる。もう一人、忘れられないのが麿赤児である。実に上手い! あの怪優が、常に「ですます調」を崩さないタクシー会社の小心な統括責任者を演じている。
この映画は、一面で、アジアでは、まだ冷戦が終わっていないことを想起させる。他方で、在日朝鮮人や在日韓国人、フィリピン人、イラン人といった、日本の周辺に生きる人々が、生命エネルギーをほとばしらせ、抑圧的な現実と渡り合っていく姿が描かれている。笑わされて、哀しくなって、最後に、元気出して行こう! そんな気にさせる映画である。
 | 月はどっちに出ている [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| オデッサ・エンタテインメント |
 | タクシー狂躁曲 (ちくま文庫) |
| 梁 石日 | |
| 筑摩書房 |
コメント ( 4 ) | Trackback ( )
刑務所の中
2006-10-09 / 映画
月曜日、 。旧暦、8月18日。
。旧暦、8月18日。
どうも風邪らしい。めったに引かないのだが、昨日は悪寒がひどく、今日は体が重い。熱はないが、予定していた作業は中止して、ぼーっとすごす。
◇
映画「刑務所の中」(崔洋一監督、山崎努、香川照之他、2002年)を観た。この映画の原作は、花輪和一の同名のコミックである。数年前に読んで、面白かったので、映画化されたと聞いて、楽しみにしていた。封切りは観られなかったので、前からTSUTAYAで探していた。
銃刀法違反で懲役3年の刑を受けた花輪さん自身の旭川刑務所での体験がそのまま描かれている。体験自体が特異なので、映像はどこを取っても驚くようなことばかりである。それでいて、暗くない。むしろ、コミカルである。そのコミカルさは、現実のある面が極端化され、それを大真面目に行うところにあるように思う。房の外では、歩き方や歩数まで決められており、トイレは許可を得なければならない。作業中にトイレに行くときには、手を上げて「ねがいまーす」と大声で刑務官に願い出るのである。刑務官は、教壇のような高いところにいて、作業を監視し、手を上げた受刑者に応えて、指差すのであるが、その指し方が意識的で大仰で実におかしい。何かを指差すときには、いきなり指すのが普通だが、刑務官は、いったん、指先を背中側にもってきてから相手を指差す。腕の動きは180度を動くことになるので、実に派手な指差し方なのである。
この映画で印象的だったのは、受刑者・刑務官の体の動きである。とりわけ、監視される受刑者の体の動きは面白い。房(5人一部屋)の中は別として、いったん外に出て作業場に向かったり運動場に向かったりするときには、指先まで監視が行き届き、管理されている。集団で行進するときなどは、ある種の美しささえある。まさに、刑務所は極限の管理社会である。
面白いのは、反抗する人間がほとんどいないことだ。むしろ、支配されることに喜びを見出し、進んで服従しているふしがある。花輪さん自身、房内で「不正連絡」をしたかどで、懲罰独房に入れられるのであるが、ここの居心地が集団房よりいい。個室で、風呂も一番風呂。作業は独房内で行い、薬局で使用する紙袋の作成作業という軽作業(花輪さんは自発的に、一日200個作成に挑戦して実現している。ノルマはなさそうだった)。ただし、トイレは個室内に設置されているが、自由に使用できない。ここでも許可を受けなければならない。その他は、実に良さそうなのだ。花輪さん自身、ここで一生すごせと言われたら、3日泣くけれど、諦めがつくだろうな、と回想している。刑務所生活で一番の思い出になったところらしい。
刑務所の食事は、意外にいい。普段は米7割麦3割の飯を主体に、少量のおかずが3品くらい、汁物が1品。中でも、正月三が日は、娑婆以上かもしれない。2、3キロ太るという冗談が出るくらいである。24時間監視され、刑務官にしょっちゅう「たるんでいるぞ」と大声でどなられたり注意されたりするものの、作業は週休2日で、休日には映画鑑賞もある。
日本の「刑務所文化」の起源・モデルは、たぶん、日本帝国軍隊にあるのだろう。刑務官はいわば、上官で受刑者は初年兵である。映画では、刑務官の暴力はなかったが、数年前に刑務所内の暴力が社会問題化したことがあった。刑務官の絶対的な権力を見ていると、そこから物理的な暴力までは近いなという気はした。
極限の管理社会にプライバシーはない。どこまでも刑務所内の空間は明るく透明で、「個人」はない、「内面」はない。食欲・性欲・睡眠欲は、ミニマムに抑えられている。種々の欲望が抑制されているという点で、刑務所は、おそらく、日本でもっとも非資本主義的な社会圏の一つだろう(刑務所の画面を見ていて美しく感じるのは、こっち側の欲望まみれの現実がそう感じさせるに違いない)。けれど、人間である。欲望はあるはずだ。抑えられればそれだけ溜まる。一説では、北朝鮮の兵士は、若い女性が笑っただけで、射精してしまうとも言われている。食欲・睡眠欲は統制できるとしても、性欲はどうしているのだろう。その辺の現実も描かれていると、コミカルを超えたディープでブラックな味わいが出たかもしれない。
 。旧暦、8月18日。
。旧暦、8月18日。どうも風邪らしい。めったに引かないのだが、昨日は悪寒がひどく、今日は体が重い。熱はないが、予定していた作業は中止して、ぼーっとすごす。
◇
映画「刑務所の中」(崔洋一監督、山崎努、香川照之他、2002年)を観た。この映画の原作は、花輪和一の同名のコミックである。数年前に読んで、面白かったので、映画化されたと聞いて、楽しみにしていた。封切りは観られなかったので、前からTSUTAYAで探していた。
銃刀法違反で懲役3年の刑を受けた花輪さん自身の旭川刑務所での体験がそのまま描かれている。体験自体が特異なので、映像はどこを取っても驚くようなことばかりである。それでいて、暗くない。むしろ、コミカルである。そのコミカルさは、現実のある面が極端化され、それを大真面目に行うところにあるように思う。房の外では、歩き方や歩数まで決められており、トイレは許可を得なければならない。作業中にトイレに行くときには、手を上げて「ねがいまーす」と大声で刑務官に願い出るのである。刑務官は、教壇のような高いところにいて、作業を監視し、手を上げた受刑者に応えて、指差すのであるが、その指し方が意識的で大仰で実におかしい。何かを指差すときには、いきなり指すのが普通だが、刑務官は、いったん、指先を背中側にもってきてから相手を指差す。腕の動きは180度を動くことになるので、実に派手な指差し方なのである。
この映画で印象的だったのは、受刑者・刑務官の体の動きである。とりわけ、監視される受刑者の体の動きは面白い。房(5人一部屋)の中は別として、いったん外に出て作業場に向かったり運動場に向かったりするときには、指先まで監視が行き届き、管理されている。集団で行進するときなどは、ある種の美しささえある。まさに、刑務所は極限の管理社会である。
面白いのは、反抗する人間がほとんどいないことだ。むしろ、支配されることに喜びを見出し、進んで服従しているふしがある。花輪さん自身、房内で「不正連絡」をしたかどで、懲罰独房に入れられるのであるが、ここの居心地が集団房よりいい。個室で、風呂も一番風呂。作業は独房内で行い、薬局で使用する紙袋の作成作業という軽作業(花輪さんは自発的に、一日200個作成に挑戦して実現している。ノルマはなさそうだった)。ただし、トイレは個室内に設置されているが、自由に使用できない。ここでも許可を受けなければならない。その他は、実に良さそうなのだ。花輪さん自身、ここで一生すごせと言われたら、3日泣くけれど、諦めがつくだろうな、と回想している。刑務所生活で一番の思い出になったところらしい。
刑務所の食事は、意外にいい。普段は米7割麦3割の飯を主体に、少量のおかずが3品くらい、汁物が1品。中でも、正月三が日は、娑婆以上かもしれない。2、3キロ太るという冗談が出るくらいである。24時間監視され、刑務官にしょっちゅう「たるんでいるぞ」と大声でどなられたり注意されたりするものの、作業は週休2日で、休日には映画鑑賞もある。
日本の「刑務所文化」の起源・モデルは、たぶん、日本帝国軍隊にあるのだろう。刑務官はいわば、上官で受刑者は初年兵である。映画では、刑務官の暴力はなかったが、数年前に刑務所内の暴力が社会問題化したことがあった。刑務官の絶対的な権力を見ていると、そこから物理的な暴力までは近いなという気はした。
極限の管理社会にプライバシーはない。どこまでも刑務所内の空間は明るく透明で、「個人」はない、「内面」はない。食欲・性欲・睡眠欲は、ミニマムに抑えられている。種々の欲望が抑制されているという点で、刑務所は、おそらく、日本でもっとも非資本主義的な社会圏の一つだろう(刑務所の画面を見ていて美しく感じるのは、こっち側の欲望まみれの現実がそう感じさせるに違いない)。けれど、人間である。欲望はあるはずだ。抑えられればそれだけ溜まる。一説では、北朝鮮の兵士は、若い女性が笑っただけで、射精してしまうとも言われている。食欲・睡眠欲は統制できるとしても、性欲はどうしているのだろう。その辺の現実も描かれていると、コミカルを超えたディープでブラックな味わいが出たかもしれない。
 | 刑務所の中 特別版 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ジェネオン エンタテインメント |
 | 刑務所の中 (講談社漫画文庫) |
| 花輪 和一 | |
| 講談社 |
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
関西での対話(2) 蟻の兵隊
2006-09-03 / 映画
日曜日、 。旧暦閏7月11日。
。旧暦閏7月11日。
午後、掃除して、夕方、喫茶店で、H・カレール・ダンコースの『レーニンとは何だったのか』(藤原書店)を読む。600ページ以上もあり、返却日も迫っているので、結論と解題だけ読んだ。
「レーニンとスターリンの間にあるのは、革命の理想に献身するあまり、時に不法で残酷な手段に訴えざるを得なかった誠実な革命家と個人的な権勢欲に燃える粗暴な野心家という決定的な差異ではなく、せいぜいがニュアンスの差、むしろ、継承性と発展である」(『同書』p.625)
レーニンにしても、毛沢東にしても、ポルポト、金日成にしても、罪深い。その罪深さは、人格の罪深さなのか、歴史の罪深さなのか。
◇
忘れてしまわないうちに、映画の感想を述べておきたい。関西旅行は、こっちを朝の6時半の新幹線で立った。十三で朝10時から「蟻の兵隊」を観るためである。
この映画「蟻の兵隊」は、「日本軍山西省残留問題」を扱ったドキュメンタリーである。映画は、元残留兵奥村和一さんの姿を追う。奥村和一さんの表情がいい。実に悲惨で理不尽な体験をしているのに、温厚でいい表情をしている。この温和な表情が、徐々に変貌する。最後の生き残りの証人の元上官から、残留問題の証言を得ようと電話するが、相手にされない。電話では埒があかないと雨の中を自宅まで押しかけるが、過去のことは忘れたとする上官からは、ついに証言が得られない。温厚な奥村さんから表情が消え、能面のような恐ろしい顔になる。この変化をカメラは静かに捉える。このあたりは、「行き行きて神軍」とも似ている。
この映画の山場は、国民党軍側に立って、共産党軍と戦った中国山西省を、奥村さんが訪れるシーンだろう。戦争の悲惨を知る農民と奥村さんとの対話、日本軍に17歳で輪姦された中国人女性の言葉。共産党軍の元兵士の言葉。さまざまな言葉が、表情が、土地の風景が、映し出される。輪姦された中国人女性は、話しながら嗚咽するが、一兵士の行為は軍の命令だとして許すのである。このシーンでは、涙が出そうになった。中国農民の首を日本刀で切り落としていた処刑場を知っている中国農民たちは、杖をついて補聴器をつけた奥村さんの姿を見て、ささやく。「おい、あんなおじいさんだぞ、杖もついているぞ」奥村さんと中国農民の対話では、けっして、農民は奥村さんを見ない。見ないまま、いかに戦時中、日本軍が野蛮だったかを手振り身振りを交えてしゃべるのである。黙って頷きながら聞く奥村さん。共産党軍の元兵士は、日本軍が戦争が終っても残っていることが理解できない。天皇のために戦うのならまだ理解できるが、なぜ、国民党軍のために戦ったのか。
日本軍に雇われて砲台陣地を守備した中国人の子孫に、奥村さんは突如、怒り始める。なぜ、逃げ出したのか。敵前逃亡はもっとも恥ずべきことだ、とその息子や孫に怒りをぶちまけるのである。そのとき、奥村さんは、完全に日本兵に戻っている。「自分の中には日本兵がまだいるのです」奥村さんの言葉である。
冒頭、靖国神社が出てくる。正月の靖国である。
「奥村さん、今日は、参拝ですか」
「とんでもない、資料を調べに来たんですよ」
「奥村さん、靖国についてどう思いますか」
「侵略戦争を戦った兵士が神になることはありえません」
残留兵士2,600人。敗戦後、4年間残留して共産党軍と戦い、5年間抑留生活を送る。550人が戦死、700人以上が捕虜となる。
「天皇陛下万歳! と言って死んでいったんですよ。どうして、これが軍命令でないと言えるんですか」
 。旧暦閏7月11日。
。旧暦閏7月11日。午後、掃除して、夕方、喫茶店で、H・カレール・ダンコースの『レーニンとは何だったのか』(藤原書店)を読む。600ページ以上もあり、返却日も迫っているので、結論と解題だけ読んだ。
「レーニンとスターリンの間にあるのは、革命の理想に献身するあまり、時に不法で残酷な手段に訴えざるを得なかった誠実な革命家と個人的な権勢欲に燃える粗暴な野心家という決定的な差異ではなく、せいぜいがニュアンスの差、むしろ、継承性と発展である」(『同書』p.625)
レーニンにしても、毛沢東にしても、ポルポト、金日成にしても、罪深い。その罪深さは、人格の罪深さなのか、歴史の罪深さなのか。
◇
忘れてしまわないうちに、映画の感想を述べておきたい。関西旅行は、こっちを朝の6時半の新幹線で立った。十三で朝10時から「蟻の兵隊」を観るためである。
この映画「蟻の兵隊」は、「日本軍山西省残留問題」を扱ったドキュメンタリーである。映画は、元残留兵奥村和一さんの姿を追う。奥村和一さんの表情がいい。実に悲惨で理不尽な体験をしているのに、温厚でいい表情をしている。この温和な表情が、徐々に変貌する。最後の生き残りの証人の元上官から、残留問題の証言を得ようと電話するが、相手にされない。電話では埒があかないと雨の中を自宅まで押しかけるが、過去のことは忘れたとする上官からは、ついに証言が得られない。温厚な奥村さんから表情が消え、能面のような恐ろしい顔になる。この変化をカメラは静かに捉える。このあたりは、「行き行きて神軍」とも似ている。
この映画の山場は、国民党軍側に立って、共産党軍と戦った中国山西省を、奥村さんが訪れるシーンだろう。戦争の悲惨を知る農民と奥村さんとの対話、日本軍に17歳で輪姦された中国人女性の言葉。共産党軍の元兵士の言葉。さまざまな言葉が、表情が、土地の風景が、映し出される。輪姦された中国人女性は、話しながら嗚咽するが、一兵士の行為は軍の命令だとして許すのである。このシーンでは、涙が出そうになった。中国農民の首を日本刀で切り落としていた処刑場を知っている中国農民たちは、杖をついて補聴器をつけた奥村さんの姿を見て、ささやく。「おい、あんなおじいさんだぞ、杖もついているぞ」奥村さんと中国農民の対話では、けっして、農民は奥村さんを見ない。見ないまま、いかに戦時中、日本軍が野蛮だったかを手振り身振りを交えてしゃべるのである。黙って頷きながら聞く奥村さん。共産党軍の元兵士は、日本軍が戦争が終っても残っていることが理解できない。天皇のために戦うのならまだ理解できるが、なぜ、国民党軍のために戦ったのか。
日本軍に雇われて砲台陣地を守備した中国人の子孫に、奥村さんは突如、怒り始める。なぜ、逃げ出したのか。敵前逃亡はもっとも恥ずべきことだ、とその息子や孫に怒りをぶちまけるのである。そのとき、奥村さんは、完全に日本兵に戻っている。「自分の中には日本兵がまだいるのです」奥村さんの言葉である。
冒頭、靖国神社が出てくる。正月の靖国である。
「奥村さん、今日は、参拝ですか」
「とんでもない、資料を調べに来たんですよ」
「奥村さん、靖国についてどう思いますか」
「侵略戦争を戦った兵士が神になることはありえません」
残留兵士2,600人。敗戦後、4年間残留して共産党軍と戦い、5年間抑留生活を送る。550人が戦死、700人以上が捕虜となる。
「天皇陛下万歳! と言って死んでいったんですよ。どうして、これが軍命令でないと言えるんですか」
 | 蟻の兵隊 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| マクザム |
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
ゲド戦記
2006-08-04 / 映画
金曜日、 。旧暦7月11日。
。旧暦7月11日。
午前中、仕事に専念。午後、家族と待ち合わせて「ゲド戦記」を観る。前評判が悪かったので、あまり期待していなかったのだが、かなりよく出来ていると思う。絵が雑だとか、青空が薄っぺらいだとかという評価もあったが、ぼくの印象は、逆で、背景画を周到に用意している。クロード・ロランやブリューゲルの絵をモデルにしたらしい背景画は実に繊細でニュアンスに富んでいる。とくに空と雲の描写は音楽的で美しく、海に石段が消えていくところなど、見たこともないローマ帝国の都市は、こんな感じだったのではないかとさえ思った。また、アニメーションのダイナミズムは特筆していいと思う。スター・ウォーズの第1作で驚いたダイナミズムと同じ驚きをこの映画でも味わった。静と動が渾然となってアニメとしてはトップレベルの作品だと思う。
作中でテルーがアカペラで歌を歌いアレンが涙を流すシーンがあるのだが、これが非常に良かった。歌の力というものを一瞬感じることができた。吾郎監督の作詞、谷山浩子の作曲だが、詞も印象に残った。ただ、残念だったのは、歌うシーンの草のざわめきなどが、マンガチックな描写であったことだった。背景画が美しいだけに、もっと丁寧にリアルに描きこんで欲しかった。
物語は一見、勧善懲悪の枠組みになっているが、多様な解釈を許すもので、観終わって謎が残される。家族で観たので、後で、いろいろ話してみたのだが、3人が3人ともまったく違う解釈だった。影がキーワードになり、実際に、アレンの「影」も登場して、ユングの考え方が応用されているように感じるが、一方で、調和した世界とその調和の崩壊というモチーフがあり、これは、マルクスの疎外論の機制とも重なる。また、死による生の虚無感といったニヒリズムの問題が、アレンと魔女(男?)クモに共通の問題として提示され、2人はこの問題の解決のために永遠の生を求める。テルーは、アレンに、生命の連鎖に目を向けさせ、アレンは、死で一切が無に帰することを恐れているのではなく、人生を引き受けて生きることを恐れているのだと告げる。
ぼくの意見では、吾郎監督の処女作の方が「ハウル」より良かったし、メッセージも分かりやすかったように思う。「ゲド」と「ハウル」のメッセージには同質のものがあるという意見や「ゲド」には未来を担う子どもに向けたメッセージがなかったという意見も出た。ぼくは、大人にも未来はあると思うし、大人を救うことも大切な仕事だと思うのだが……。いずれにしても、吾郎監督には、今後も期待したいと思う。
 。旧暦7月11日。
。旧暦7月11日。午前中、仕事に専念。午後、家族と待ち合わせて「ゲド戦記」を観る。前評判が悪かったので、あまり期待していなかったのだが、かなりよく出来ていると思う。絵が雑だとか、青空が薄っぺらいだとかという評価もあったが、ぼくの印象は、逆で、背景画を周到に用意している。クロード・ロランやブリューゲルの絵をモデルにしたらしい背景画は実に繊細でニュアンスに富んでいる。とくに空と雲の描写は音楽的で美しく、海に石段が消えていくところなど、見たこともないローマ帝国の都市は、こんな感じだったのではないかとさえ思った。また、アニメーションのダイナミズムは特筆していいと思う。スター・ウォーズの第1作で驚いたダイナミズムと同じ驚きをこの映画でも味わった。静と動が渾然となってアニメとしてはトップレベルの作品だと思う。
作中でテルーがアカペラで歌を歌いアレンが涙を流すシーンがあるのだが、これが非常に良かった。歌の力というものを一瞬感じることができた。吾郎監督の作詞、谷山浩子の作曲だが、詞も印象に残った。ただ、残念だったのは、歌うシーンの草のざわめきなどが、マンガチックな描写であったことだった。背景画が美しいだけに、もっと丁寧にリアルに描きこんで欲しかった。
物語は一見、勧善懲悪の枠組みになっているが、多様な解釈を許すもので、観終わって謎が残される。家族で観たので、後で、いろいろ話してみたのだが、3人が3人ともまったく違う解釈だった。影がキーワードになり、実際に、アレンの「影」も登場して、ユングの考え方が応用されているように感じるが、一方で、調和した世界とその調和の崩壊というモチーフがあり、これは、マルクスの疎外論の機制とも重なる。また、死による生の虚無感といったニヒリズムの問題が、アレンと魔女(男?)クモに共通の問題として提示され、2人はこの問題の解決のために永遠の生を求める。テルーは、アレンに、生命の連鎖に目を向けさせ、アレンは、死で一切が無に帰することを恐れているのではなく、人生を引き受けて生きることを恐れているのだと告げる。
ぼくの意見では、吾郎監督の処女作の方が「ハウル」より良かったし、メッセージも分かりやすかったように思う。「ゲド」と「ハウル」のメッセージには同質のものがあるという意見や「ゲド」には未来を担う子どもに向けたメッセージがなかったという意見も出た。ぼくは、大人にも未来はあると思うし、大人を救うことも大切な仕事だと思うのだが……。いずれにしても、吾郎監督には、今後も期待したいと思う。
 | ゲド戦記 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント |
コメント ( 4 ) | Trackback ( )
The wild blue yonder
2006-07-20 / 映画
木曜日、 。旧暦、6月25日。
。旧暦、6月25日。
午前中に仕事を済ませて、午後から、ドイツ映画祭に出かける。今日は、わりと若い人たちの姿もあった。ヴェルナー・ヘルツォーク監督の「ワイルド・ブルー・ヨンダー」というSF。
結論から言って、つまらない。どうしてつまらないのか。それは映画に広がりがないからである。宇宙の映像や太古の地球らしき映像はでてくるが、それが一向に広がりを持たない。俳句のように、微小な空間を描いていても広大な広がりを画面に感じることはある。この映画は、地球とアンドロメダの往還の物語(時間にして850年)なのに、実に窮屈な感じを受ける。手を抜いている感じさえある。低予算で作ったからというより、どこかに、監督の驕りがあるのではないか。
この窮屈さを、もっと掘り下げてみると、社会関係が描けていないことが大きいように思う。語り部は、なんと地球人そっくりのエイリアンである。彼は、故郷の惑星ワイルド・ブルー・ヨンダーから、多くの仲間とともに、惑星が死にかけているために、宇宙に逃げ出し、数百年間何世代にも渡って航行し、どうにか地球に辿り着いたという設定だ。この語りは、観客に向けられたモノローグという形を取る。
一方、地球は、このヨンダー氏らが使用した探査機を調査中に未知ウィルスに感染、人類存亡の危機になる(らしい)。これも全部、モノローグで語られるので、いっこうに切迫感がない(語り部のヨンダー氏の英語はやけにリズミカルで軽やかであるが)。そうこうするうち、人類移住計画が持ち上がり、先発隊を乗せた宇宙船が深宇宙に飛び出す。その向かった先は、なんと、死滅しかけているワイルド・ブルー・ヨンダーである。ここを植民地にするらしい。
ストーリーを書いていて、バカバカしくなってきた。この映画は、半分以上「お笑い系」である。ヘルツォークとしては笑いを取るつもりなのだろうが、ちっとも可笑しくない。宇宙船内の宇宙飛行士たちはまったく会話しないし、移住計画を考えた科学者も、革新的な宇宙旅行技術を開発した科学者も、すべてが、モノローグで語るばかりである。
つまり、この映画の中には、社会空間がない。一方的な社会空間が、映画と観客の間にあるだけである。だから、画面に広がりが出ないのである。窮屈なのである。いくら自然や宇宙を写しても、人間と対話しない自然や宇宙は、単なる非歴史的な物質でしかない。
偶然なのか、理由があるのか、わからないが、この映画の前に上映された短編「火曜日」も会話が一切なかった。登場人物は、引退間直の中高年夫婦。この短編は、会話がなくとも、そのことが返って、夫婦の日常に倦んだ感じ、人生に疲れた感じを出していて、効果があった。寝る前に毎日、別々の部屋で、自殺しようとしては止めるのである。妻は夫のピストルの音に耳をそばだて、自殺しないと分かると、洗面の奥に睡眠剤を戻す妻。二人は眠るときには、互いの方を向いて肩を寄せ合って眠る。言葉はないが、愛がないわけではないことが分かる。二人の外部の社会の何かが二人を自殺未遂に駆り立てるのかもしれない。
ドイツ語で理性を表す「die Vernunft」という言葉の原義は、「聴き取る」ことらしい。つまりVernunftには他者の存在が前提されている。ヘルツォークの映画に決定的に欠けているのは、他者(人間の他者も含む)の言葉を聴き取るVernunftの働きであるように思われる。
 。旧暦、6月25日。
。旧暦、6月25日。午前中に仕事を済ませて、午後から、ドイツ映画祭に出かける。今日は、わりと若い人たちの姿もあった。ヴェルナー・ヘルツォーク監督の「ワイルド・ブルー・ヨンダー」というSF。
結論から言って、つまらない。どうしてつまらないのか。それは映画に広がりがないからである。宇宙の映像や太古の地球らしき映像はでてくるが、それが一向に広がりを持たない。俳句のように、微小な空間を描いていても広大な広がりを画面に感じることはある。この映画は、地球とアンドロメダの往還の物語(時間にして850年)なのに、実に窮屈な感じを受ける。手を抜いている感じさえある。低予算で作ったからというより、どこかに、監督の驕りがあるのではないか。
この窮屈さを、もっと掘り下げてみると、社会関係が描けていないことが大きいように思う。語り部は、なんと地球人そっくりのエイリアンである。彼は、故郷の惑星ワイルド・ブルー・ヨンダーから、多くの仲間とともに、惑星が死にかけているために、宇宙に逃げ出し、数百年間何世代にも渡って航行し、どうにか地球に辿り着いたという設定だ。この語りは、観客に向けられたモノローグという形を取る。
一方、地球は、このヨンダー氏らが使用した探査機を調査中に未知ウィルスに感染、人類存亡の危機になる(らしい)。これも全部、モノローグで語られるので、いっこうに切迫感がない(語り部のヨンダー氏の英語はやけにリズミカルで軽やかであるが)。そうこうするうち、人類移住計画が持ち上がり、先発隊を乗せた宇宙船が深宇宙に飛び出す。その向かった先は、なんと、死滅しかけているワイルド・ブルー・ヨンダーである。ここを植民地にするらしい。
ストーリーを書いていて、バカバカしくなってきた。この映画は、半分以上「お笑い系」である。ヘルツォークとしては笑いを取るつもりなのだろうが、ちっとも可笑しくない。宇宙船内の宇宙飛行士たちはまったく会話しないし、移住計画を考えた科学者も、革新的な宇宙旅行技術を開発した科学者も、すべてが、モノローグで語るばかりである。
つまり、この映画の中には、社会空間がない。一方的な社会空間が、映画と観客の間にあるだけである。だから、画面に広がりが出ないのである。窮屈なのである。いくら自然や宇宙を写しても、人間と対話しない自然や宇宙は、単なる非歴史的な物質でしかない。
偶然なのか、理由があるのか、わからないが、この映画の前に上映された短編「火曜日」も会話が一切なかった。登場人物は、引退間直の中高年夫婦。この短編は、会話がなくとも、そのことが返って、夫婦の日常に倦んだ感じ、人生に疲れた感じを出していて、効果があった。寝る前に毎日、別々の部屋で、自殺しようとしては止めるのである。妻は夫のピストルの音に耳をそばだて、自殺しないと分かると、洗面の奥に睡眠剤を戻す妻。二人は眠るときには、互いの方を向いて肩を寄せ合って眠る。言葉はないが、愛がないわけではないことが分かる。二人の外部の社会の何かが二人を自殺未遂に駆り立てるのかもしれない。
ドイツ語で理性を表す「die Vernunft」という言葉の原義は、「聴き取る」ことらしい。つまりVernunftには他者の存在が前提されている。ヘルツォークの映画に決定的に欠けているのは、他者(人間の他者も含む)の言葉を聴き取るVernunftの働きであるように思われる。
 | Wild Blue Yonder [Import anglais] |
| クリエーター情報なし | |
| メーカー情報なし |
コメント ( 2 ) | Trackback ( )
Klang der Ewigkeit
2006-07-18 / 映画
火曜日、 。旧暦、6月23日。
。旧暦、6月23日。
昨日、遅くまで仕事しすぎて朝起きられず。11時ごろ起床。シャワーを浴びて、午後から、ドイツ映画祭にでかける。今日観たのは、バスチャン・クレーヴ監督の「Klang der Ewigkeit」(永遠の音)
解説によれば、映画のコンセプトは、バッハの「ロ短調ミサ曲」の27のパートを27本の短編映画に翻訳することであるらしい。107分間、ずっとロ短調ミサが流れ、そのパートごとに異なった映像が流れる。絵画の映像あり、自然の映像あり、宇宙の映像あり、誕生の映像あり、死の映像あり、婚礼の映像あり、巡礼の映像あり、戦争の映像あり、ドイツの壁の崩壊の映像あり、万華鏡あり、NHKの名曲アルバムみたいな映像あり...。共通するのは、一切科白がないことである。バッハのロ短調ミサだけが流れる。
この映画を観て、感じたのは、27本の短編はどれもバッハに敵わないということである。圧倒的にロ短調ミサ曲の方がいい。唯一、ロ短調ミサ曲に拮抗できたと感じたのは、宇宙の映像だった。バッハのロ短調ミサは、地球の風景では太刀打ちできない広がりと深さを持っているように感じた。
音楽を映像に変換しようという試みは、ぼくは他に知らない。ロ短調ミサも、きっと何かの映画のバックグラウンドに使われたことがあるだろう。だが、この映画のように、真正面から、映像に変換しようとした試みとは本質的に異なる。バックグランドミュージックは、それがどんなに効果的であっても、映像が主であり、計算された時間だけ、計算された場面に従属的に使われる。クレーヴは、音楽と映像の初期条件を対等にして、両者を真っ向からぶつけてみたのだ。トーキーとももちろん違う。初期条件を同じにするために、映像から言語をいっさい消し去った。言語が入れば、そこに意味のある物語が立ち上がり、たちまち、ロ短調ミサはバックグラウンドミュージックになるからだ。
映像はどこまで抽象化できるか。これが、この映画の隠れたテーマだったように思う。音楽をバックグラウンドにせず、その本質的な抽象性と拮抗するには、どうすべきか。結論から言えば、ここで使われた映像はどれも音楽に拮抗できていない。その結果、映画というよりも映像付きのコンサートになっている。監督の意図から外れるかどうかわからないが、この作品はバッハへの映像的オマージュだと思うのである。
 。旧暦、6月23日。
。旧暦、6月23日。昨日、遅くまで仕事しすぎて朝起きられず。11時ごろ起床。シャワーを浴びて、午後から、ドイツ映画祭にでかける。今日観たのは、バスチャン・クレーヴ監督の「Klang der Ewigkeit」(永遠の音)
解説によれば、映画のコンセプトは、バッハの「ロ短調ミサ曲」の27のパートを27本の短編映画に翻訳することであるらしい。107分間、ずっとロ短調ミサが流れ、そのパートごとに異なった映像が流れる。絵画の映像あり、自然の映像あり、宇宙の映像あり、誕生の映像あり、死の映像あり、婚礼の映像あり、巡礼の映像あり、戦争の映像あり、ドイツの壁の崩壊の映像あり、万華鏡あり、NHKの名曲アルバムみたいな映像あり...。共通するのは、一切科白がないことである。バッハのロ短調ミサだけが流れる。
この映画を観て、感じたのは、27本の短編はどれもバッハに敵わないということである。圧倒的にロ短調ミサ曲の方がいい。唯一、ロ短調ミサ曲に拮抗できたと感じたのは、宇宙の映像だった。バッハのロ短調ミサは、地球の風景では太刀打ちできない広がりと深さを持っているように感じた。
音楽を映像に変換しようという試みは、ぼくは他に知らない。ロ短調ミサも、きっと何かの映画のバックグラウンドに使われたことがあるだろう。だが、この映画のように、真正面から、映像に変換しようとした試みとは本質的に異なる。バックグランドミュージックは、それがどんなに効果的であっても、映像が主であり、計算された時間だけ、計算された場面に従属的に使われる。クレーヴは、音楽と映像の初期条件を対等にして、両者を真っ向からぶつけてみたのだ。トーキーとももちろん違う。初期条件を同じにするために、映像から言語をいっさい消し去った。言語が入れば、そこに意味のある物語が立ち上がり、たちまち、ロ短調ミサはバックグラウンドミュージックになるからだ。
映像はどこまで抽象化できるか。これが、この映画の隠れたテーマだったように思う。音楽をバックグラウンドにせず、その本質的な抽象性と拮抗するには、どうすべきか。結論から言えば、ここで使われた映像はどれも音楽に拮抗できていない。その結果、映画というよりも映像付きのコンサートになっている。監督の意図から外れるかどうかわからないが、この作品はバッハへの映像的オマージュだと思うのである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
Feel like going home
2006-06-25 / 映画
日曜日、 。旧暦、5月30日。
。旧暦、5月30日。
一日、ボーっとする。新聞を読んで、掃除して、ゴミを捨てて、DVDでFeel like going homeを観て終った。
マーチン・スコセッシ監督のブルース関連のドキュメンタリー映画である。たまにCDを聴くくらいで、ほとんど、その歴史やミュージシャンは知らないが、ブルースはロックのルーツの一つであり、奴隷制という出自やメロディとリズムの面白さに、興味はある。ブルースでよく歌われる、「悪い女」は実は綿花のプランテーションの農場主(ボス)のことだと、映画の中であるブルースマンは語っている。直接、ボスを非難すれば、翌朝にはあの木に首からぶら下がっているさ、ということらしい。アメリカのブルースの歴史をたどる中で、徐々に、隠れたプロテストソングだったブルースが、現実の「悪い女」を歌うようになっていく。つまり、ラブソングに変質していく。それと同時に、ブルースマンの意識も「俺は結婚は5回もしたぜ。その意味じゃ、経験者さ」というふうに女性が関心の中心になっていく。もちろん、仕事の辛さや差別の辛さも歌っているはずだが、ブルースがラブソングに変わっていくプロセスも確かにあり、それを一番喜んだのは、収奪する側の白人だったろう。
このドキュメンタリーでは、後半、現役ブルースマンのコリー・ハリスが「自分を知ることは自分の過去を知ることだ」という言葉に導かれて、西アフリカのマリまで、ブルースの起源をたどっていく。マリの文化は口承文化であり、マリでは音楽と歴史が結びついている。歌うことがそのまま己を知ることになる。マリの音楽は、一部、イスラム教の影響からか、メロディに中近東系の響があるように感じた。
このドキュメンタリーではじめて知ったのだが、奴隷として米国に連れてこられた黒人たちは、民族楽器として太鼓も持ち込んだが、白人達は、これで意思の伝達を行うと警戒して禁止してしまった。使用すると死刑になった(確かそう言っていた)。ブルースのギター奏法にリズムを取るような奏法があるのは、ドラムが禁止された名残なのかもしれない。今、思い立って、バディ・ガイの「A Man & The Blues」を聴いている。やはり、曲によっては、ドラムは使用されていても前面に出てこない(クリームやヤードバーズのようなホワイトブルースが遠慮なくドラムを鳴らしているのと対照的である)。ブルースもジャズもロックに比べれば、ドラムの使い方は控えめではないだろうか。
考えてみると、奴隷として米国に連れてこられた黒人たちは、母なるアフリカの大地から暴力的に引き離され、米国社会の最下層に暴力的に組み込まれたという意味で二重に収奪されている。マリの黒人が、自国の伝統に誇りを持ちそこに己のアイデンティティを見出して、植民地独立の根拠にできたのに対し、米国の黒人は、己のアイデンティティに否定的にしか関われない。ブルーなアイデンティティとして。そのせいか、マリのミュージシャンたちのフランス語は、その内容も含めて確信的に響くのに対して、コリー・ハリスの英語は、いかにも自信なさそうで、村から出て行ってよその町で傷心した若者が故郷に帰ってきた、という感じなのだ。二重の収奪は、米国の黒人たちに奥深いところで、「恥辱」に近いものを与えてきたのではないだろうか。
 。旧暦、5月30日。
。旧暦、5月30日。一日、ボーっとする。新聞を読んで、掃除して、ゴミを捨てて、DVDでFeel like going homeを観て終った。
マーチン・スコセッシ監督のブルース関連のドキュメンタリー映画である。たまにCDを聴くくらいで、ほとんど、その歴史やミュージシャンは知らないが、ブルースはロックのルーツの一つであり、奴隷制という出自やメロディとリズムの面白さに、興味はある。ブルースでよく歌われる、「悪い女」は実は綿花のプランテーションの農場主(ボス)のことだと、映画の中であるブルースマンは語っている。直接、ボスを非難すれば、翌朝にはあの木に首からぶら下がっているさ、ということらしい。アメリカのブルースの歴史をたどる中で、徐々に、隠れたプロテストソングだったブルースが、現実の「悪い女」を歌うようになっていく。つまり、ラブソングに変質していく。それと同時に、ブルースマンの意識も「俺は結婚は5回もしたぜ。その意味じゃ、経験者さ」というふうに女性が関心の中心になっていく。もちろん、仕事の辛さや差別の辛さも歌っているはずだが、ブルースがラブソングに変わっていくプロセスも確かにあり、それを一番喜んだのは、収奪する側の白人だったろう。
このドキュメンタリーでは、後半、現役ブルースマンのコリー・ハリスが「自分を知ることは自分の過去を知ることだ」という言葉に導かれて、西アフリカのマリまで、ブルースの起源をたどっていく。マリの文化は口承文化であり、マリでは音楽と歴史が結びついている。歌うことがそのまま己を知ることになる。マリの音楽は、一部、イスラム教の影響からか、メロディに中近東系の響があるように感じた。
このドキュメンタリーではじめて知ったのだが、奴隷として米国に連れてこられた黒人たちは、民族楽器として太鼓も持ち込んだが、白人達は、これで意思の伝達を行うと警戒して禁止してしまった。使用すると死刑になった(確かそう言っていた)。ブルースのギター奏法にリズムを取るような奏法があるのは、ドラムが禁止された名残なのかもしれない。今、思い立って、バディ・ガイの「A Man & The Blues」を聴いている。やはり、曲によっては、ドラムは使用されていても前面に出てこない(クリームやヤードバーズのようなホワイトブルースが遠慮なくドラムを鳴らしているのと対照的である)。ブルースもジャズもロックに比べれば、ドラムの使い方は控えめではないだろうか。
考えてみると、奴隷として米国に連れてこられた黒人たちは、母なるアフリカの大地から暴力的に引き離され、米国社会の最下層に暴力的に組み込まれたという意味で二重に収奪されている。マリの黒人が、自国の伝統に誇りを持ちそこに己のアイデンティティを見出して、植民地独立の根拠にできたのに対し、米国の黒人は、己のアイデンティティに否定的にしか関われない。ブルーなアイデンティティとして。そのせいか、マリのミュージシャンたちのフランス語は、その内容も含めて確信的に響くのに対して、コリー・ハリスの英語は、いかにも自信なさそうで、村から出て行ってよその町で傷心した若者が故郷に帰ってきた、という感じなのだ。二重の収奪は、米国の黒人たちに奥深いところで、「恥辱」に近いものを与えてきたのではないだろうか。
 | フィール・ライク・ゴーイング・ホーム [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| 日活 |
コメント ( 2 ) | Trackback ( )
| 次ページ » |





