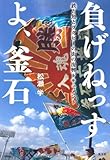先日、「ライムスター宇多丸のウィークエンドシャッフル」(長いね、通称タマフル)というラジオ番組で国語辞典特集をやってた。
なんのこっちゃ?と思うでしょ?
この番組は時に非常にコアな特集をすることで有名。
例えば「4、5映画特集」と言って映画の続編の4、5の話をずっとしたりとか「真のクラブミュージック特集」として中学校の吹奏楽部のCD(世の中にはそんなものがあるんです)を特集したりとか。「OKB48特集」はもちろん「お気に入りのボールペン特集」、律儀に48本集めてやってた。
その一環として国語辞典特集。
ゲストは僕が好きな芸人サンキュータツオ。この人は芸人活動の傍ら、大学で日本語学を教えている人で、東京ポッド許可局というポッドキャストをやっている。
さすがの僕も「国語辞典で1時間?」と思ったんだけどこれがこれが、ほんと1時間じゃ足りない話でした。
詳細はポッドキャストで聴けるのでぜひどうぞ。
「辞書特集feat.サンキュータツオ」(前編)
「辞書特集feat.サンキュータツオ」(後編)
ホントに開始10分くらいで「あ、このヒト、く、狂ってる(笑)」と実感しますよ(褒めてます)。
で、これ聴いたら僕も国語辞典が欲しくなった。
考えてみたら僕は一冊も持ってないし身の回りにもない。
一冊くらい持っていてもいいな、どれ買おうかな、と悩んでみました。
独特の語釈で有名な「新明解国語辞典」は魅力的なんだけどちょっとクセがありすぎる。
新明解がどれくらい独特かと言うと「動物園」の項だけで分かる。
【動物園】生態を公衆に見せ、かたわら保護を加えるためと称し、捕らえて来た多くの鳥獣・魚虫などに対し、狭い空間での生活を余儀なくし、飼い殺しにする、人間中心の施設。(第4版)
すごいでしょ。
こんなの何も知らない人が読んだら動物園に偏見を持ちかねない(今の版では変更されているそうです)。
「恋愛」の項目も面白い。
【恋愛】特定の異性に特別の愛情をいだいて、二人だけで一緒に居たい、出来るなら合体したいという気持ちを持ちながら、それが、常にはかなえられないで、ひどく心を苦しめる・(まれにかなえられて歓喜する)状態。(第4版)
で、「合体」をひくとこう出ている。
【合体】1,起源・由来の違うものが新しい理念の下に一体となって何かを運営すること。2,「性交」のこの辞書でのえんきょく表現。(第4版)
ちゃとオチがついている。
まぁ読み物としては面白いけど好みが分かれるところだね。
いろいろ悩んでみた結果、サンキュータツオ氏のお勧め「集英社国語辞典」を購入してみました。
この辞書の特徴はなんと言っても「横組み」であること。英和辞典に慣れた身としてはまったく違和感ない。
ネット、電子書籍隆盛の現代ですが紙の辞書はこれはこれでいいやね。
「ちゃんと勉強するなら絶対、紙」と言うのが僕の信条であります。特に辞書は紙がいい。
その理由をちょっと説明させてください。高校、大学と僕は英語を勉強していた。結構前の話ではあるけど、そのときだって電子辞書はあった。でも紙の辞書を使っていた。
紙の辞書の一番の利点は「たくさんの単語を1ページで見られる」ということです。
どういうことかと言うと、この頃の辞書の使い方というのは「調べる」ということよりも「調べて覚える」というほうが大事。そのために、例えば一度調べた単語には赤線を引く。そして僕は二回引いたら青線、三回引いたら黒線、四回引いたらもうぐるぐる丸で囲ってしまう、というルールにしていた。
そうしていると、他の単語を引いたときにも偶然なかなか覚えられない単語が目に入る。その「パッと目に入った」という記憶って結構残ってて、テストの時なんかに「あれなんだっけ?なんかあの単語の上のほうにあったなぁ」とふと思い出せたりする。
電子辞書にはなかなかアンダーラインを引けないし今はiPadなんかでそういう機能がついたのがあるんだろうけど、この一覧性はなかなか再現できない。
と、言うことで最近話題の「辞書作りの人々を描いた小説」(すごいな)、『舟を編む』も読んでみました。いい小説でしたよ。
言葉を愛する人々なんだけど、大事なことは言葉じゃない。言葉を大事にするからこそかも知れないけどね。
なんのこっちゃ?と思うでしょ?
この番組は時に非常にコアな特集をすることで有名。
例えば「4、5映画特集」と言って映画の続編の4、5の話をずっとしたりとか「真のクラブミュージック特集」として中学校の吹奏楽部のCD(世の中にはそんなものがあるんです)を特集したりとか。「OKB48特集」はもちろん「お気に入りのボールペン特集」、律儀に48本集めてやってた。
その一環として国語辞典特集。
ゲストは僕が好きな芸人サンキュータツオ。この人は芸人活動の傍ら、大学で日本語学を教えている人で、東京ポッド許可局というポッドキャストをやっている。
さすがの僕も「国語辞典で1時間?」と思ったんだけどこれがこれが、ほんと1時間じゃ足りない話でした。
詳細はポッドキャストで聴けるのでぜひどうぞ。
「辞書特集feat.サンキュータツオ」(前編)
「辞書特集feat.サンキュータツオ」(後編)
ホントに開始10分くらいで「あ、このヒト、く、狂ってる(笑)」と実感しますよ(褒めてます)。
で、これ聴いたら僕も国語辞典が欲しくなった。
考えてみたら僕は一冊も持ってないし身の回りにもない。
一冊くらい持っていてもいいな、どれ買おうかな、と悩んでみました。
独特の語釈で有名な「新明解国語辞典」は魅力的なんだけどちょっとクセがありすぎる。
新明解がどれくらい独特かと言うと「動物園」の項だけで分かる。
【動物園】生態を公衆に見せ、かたわら保護を加えるためと称し、捕らえて来た多くの鳥獣・魚虫などに対し、狭い空間での生活を余儀なくし、飼い殺しにする、人間中心の施設。(第4版)
すごいでしょ。
こんなの何も知らない人が読んだら動物園に偏見を持ちかねない(今の版では変更されているそうです)。
「恋愛」の項目も面白い。
【恋愛】特定の異性に特別の愛情をいだいて、二人だけで一緒に居たい、出来るなら合体したいという気持ちを持ちながら、それが、常にはかなえられないで、ひどく心を苦しめる・(まれにかなえられて歓喜する)状態。(第4版)
で、「合体」をひくとこう出ている。
【合体】1,起源・由来の違うものが新しい理念の下に一体となって何かを運営すること。2,「性交」のこの辞書でのえんきょく表現。(第4版)
ちゃとオチがついている。
まぁ読み物としては面白いけど好みが分かれるところだね。
いろいろ悩んでみた結果、サンキュータツオ氏のお勧め「集英社国語辞典」を購入してみました。
この辞書の特徴はなんと言っても「横組み」であること。英和辞典に慣れた身としてはまったく違和感ない。
ネット、電子書籍隆盛の現代ですが紙の辞書はこれはこれでいいやね。
「ちゃんと勉強するなら絶対、紙」と言うのが僕の信条であります。特に辞書は紙がいい。
その理由をちょっと説明させてください。高校、大学と僕は英語を勉強していた。結構前の話ではあるけど、そのときだって電子辞書はあった。でも紙の辞書を使っていた。
紙の辞書の一番の利点は「たくさんの単語を1ページで見られる」ということです。
どういうことかと言うと、この頃の辞書の使い方というのは「調べる」ということよりも「調べて覚える」というほうが大事。そのために、例えば一度調べた単語には赤線を引く。そして僕は二回引いたら青線、三回引いたら黒線、四回引いたらもうぐるぐる丸で囲ってしまう、というルールにしていた。
そうしていると、他の単語を引いたときにも偶然なかなか覚えられない単語が目に入る。その「パッと目に入った」という記憶って結構残ってて、テストの時なんかに「あれなんだっけ?なんかあの単語の上のほうにあったなぁ」とふと思い出せたりする。
電子辞書にはなかなかアンダーラインを引けないし今はiPadなんかでそういう機能がついたのがあるんだろうけど、この一覧性はなかなか再現できない。
と、言うことで最近話題の「辞書作りの人々を描いた小説」(すごいな)、『舟を編む』も読んでみました。いい小説でしたよ。
言葉を愛する人々なんだけど、大事なことは言葉じゃない。言葉を大事にするからこそかも知れないけどね。