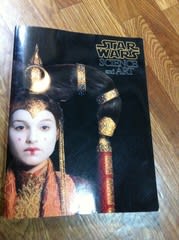昨日、トークライブに行ってきました。
何でもやっぱり生で見るといいね、と言う話は今度別にしたいと思ってます。
行ってきたのは「東京ポッド許可局」というポッドキャストで放送している番組のイベント。

東京ポッド許可局と言うのはマキタスポーツ、プチ鹿島、サンキュータツオ、という3人の芸人がいろんなこと(えーっとM-1とかビートたけしとかアイスとかキャベツとか…)について3人で話している、という音声だけの番組。
これがねー、面白いんだわ。
キャッチコピーは「屁理屈とはスポーツである」。
いいおっさんたち(だいたい30代後半から40歳)3人がジュースについて「あれ旨い!」だの、お笑いについて「手数の時代に入っている」だのを話し合っているのなんて、聞いてるこっちもずいぶん物好きだなぁと思うところはあるけども。
ぜひ騙されたと思ってポッドキャストを登録してみるか、iTunesとかもって無くてもパソコンでも聞けるので聞いてみてください。
(一番下に余計なおせっかいですが、現時点で聞けるデータのうちお勧めを書いておきます。)
ここからちょっと大仰な話になるけども、僕はこの東京ポッド許可局を応援しています。
なぜか、というとまず、コンテンツとして内容が非常に面白いから。聞いていて笑うし、「なるほどなぁ」と膝を打つところも多い。落語なんて僕はそんなに詳しくは無いけどそれでも「小朝論」という回で、三遊亭円朝という大落語家についての詳しい話なんかは非常に参考になった。
そしてこれが基本的には無料で聞ける、というのがすばらしい。システムとしては毎週日曜にネットを通じて配信されてそれをダウンロード、あるいは視聴するのは無料。配信後、数週間でネット上の掲載は終わり過去のものを聞きたければ5回分まとめて300円で購入できる、という仕組み。だからPodcastに登録して自動的にダウンロードされるようにしておけば基本的に無料。
こんなすばらしい話はないね。
そしてここからが僕が言うことじゃないけど今後のメディア論的視点からの応援理由。
僕はこれが新しい芸人の「売れる形」になって欲しいと思っています。
登場する3人とも現時点では失礼ながら決して世間的に有名、という人ではない。ダウンタウン、ナインティナイン、ブラマヨ、オードリーとか今テレビを付ければ見られる人とは比べ物にならないくらい知名度はない、大変失礼だけれども。
でもね、僕は思うんだけどテレビにいつも出ている人たちしか見たり聞いたり出来ない、という状態ってすごく淋しい。
出来れば面白い人も(そりゃもちろん面白くない人も)たくさんいて、そんな中で楽しめたほうがいい。
もちろんテレビだけが「世間」ではなくてテレビに出ていないけど面白い人は現時点ではたくさんいるだろう。僕が知らない面白い人、そして僕の知らないところで人気がある人だってまだまだたくさんいるんだろうと思う。だけどこれだけネットが発達した現代においてもその人たちを知ることが出来ない人、知っているけど触れるチャンスが無い人だってたくさんいる。たとえば地方に住んでいたりするとね。
あくまで素人意見だけど今のテレビはもうガチガチで、人気のある人(というか「人気があると思われている人」)しか出てこない。
そんな中、自分たちを面白いとちゃんと自信を持っているけど出るチャンスが無い人ってたくさんいるんだと思う。(その人たちがかけたチャンスがM-1であったと思うんだけど)
そしてそこにも入れない人がいて、残念ながらそういう人たちは今までどれだけコアなファンを得ていても残念ながら消えていくしかなかった。ファンがどれだけコアでも絶対数が少なければ商売にならない。
そんな状況をこの人たち、東京ポッド許可局は打破しようとしていると思う。
お金なんてほとんどかけずに3人で集まって1個のICレコーダーの前で話している。それをこれまたお金をかけずにPodcastとして配信する。ただそれだけ。それでもその話が面白ければ人は集まってくる。なんとまぁいまPodcast登録者数20万人ですって。
その20万人のうち何人がちゃんと聞いているかは誰にも分からないけど、場合によってはゴールデンタイムでも視聴率1%を切ってしまう現在においてもテレビよりもそれは大きな影響力なんじゃないだろうか。
僕はこういうパターンがどんどん出てくればいいと思っています。
こういう「話」の形だと二番煎じになってしまうけど、たとえば楽器を使わずめちゃくちゃすごいオリジナル曲を演奏できるよ、って人がいたとする。今までだったらこの人は単なるもの珍しい人で、うまく行ってもちょっとしたバラエティに出て終わり、ってくらいだろう。CD売ろうにもお金がかかるからそんなに作ってくれる人なんていない。自主制作しても限度がある。
でもこのパターンを踏襲すれば、まずはPodcast配信をする。いい物であれば聴取者が増える。その中で欲しい、という人にのみオリジナル音源をネット販売する、ということが可能かも知れない。直接的に販売出来なくてもそれが知名度を上げる要因になり、何かしらのチャンスが生まれることだってあるかも知れない。
Ustreamだって今は玉石混合だけどその中からきちっとお金を稼いでいく人が現れればもっともっと発展するだろう。
結果、テレビの視聴率が下がってテレビがつまらなくなってもそれは時代の流れだもの、仕方が無い。(ただあえて僕は言っときたいけど僕は典型的にテレビっ子でテレビとともに育ってきた人間だから「そーんなにテレビは弱くないだろ」と思っているけどね。お金無いならないでどうにかするよ、たぶんテレビは。)
この「東京ポッド許可局」も現時点では大きく儲かっている、というわけではない。(イベントでも本人たちがしきりに言っていた) でも僕はこういう人たちこそちゃんと儲かって欲しいと思う。ウハウハ、ってほどでなくても少なくとも本人たちがやりたいこと(つまりこの番組)を続けられる程度に。そうすれば何より聞いている僕が楽しめるもの。
なんとこの東京ポッド許可局、8月28日に日比谷公会堂で2,000人集めるイベントを行う。(→大東京ポッド許可局)
先日見てきたイベントはこの大イベントのオフレコトークもあった。聴いていると一言で「2,000人集める」と言ってもこれは大勝負なんだなぁということがよく分かる。スポンサーのいるイベントではないからイベント費用は本人たちが出している。現時点で2,000人の動員力のある人たちでは無い。もし不運が続けばお客さんが入らず大赤字ってこともありうるだろう。
この「行けるのか行けないのか」というドキドキ感がたまらない。本人たちが言っていた「僕ら失敗している余裕がある年齢でもないし、後戻りが出来る年齢でもないんです!」はかなりグッと来たなぁ。僕自身、この人たちとほぼ同世代、と言っていい世代だからこの気持ちはよく分かる。
僕は決してお笑いに関して先物買いをする人間ではない。たとえばお笑い番組を細かくチェックして「あ、この芸人がこれから来そうだな」なんてことをやる人間ではない。だから数年後に「あいつらは俺がずっと前から目をつけてたんだよ」と言いたくて応援しているわけじゃない。
ただ上記のような理由で、必ずこの人たちは脚光を浴びるはずだと思うし、ぜひ浴びて欲しいと願っている。そうすれば世界はもっと面白くなるはず。
というわけで僕は東京ポッド許可局を応援しています。
気になる方は本も出てますからぜひ手に取ってみてください。買うのが躊躇われるならお貸しします。
 東京ポッド許可局 ~文系芸人が行間を、裏を、未来を読む~
東京ポッド許可局 ~文系芸人が行間を、裏を、未来を読む~
【オマケ:2011年6月21日時点で聞ける東京ポッド許可局お勧め回】
上記でも書いたけど東京ポッド許可局のコンテンツは大体10~30分くらいの音声コンテンツ。形式としては3人(許可局員、という形式)がtだただしゃべっているだけ。プラスたまに謎の局長と言う人が入ってくる時もある。
テーマはかなりばらばら。
毎週日曜日更新、公開期間(つまり無料で聞ける期間)は数週間。ただPodcastに登録(あるいは自分でダウンロード)してパソコンに保存しておけばずっと聴ける。
どの回も面白いけど人によって好みがあると思うので(僕は全部好きだけど)お勧め回を余計なお世話ですが書いときます。
※このページ(→東京ポッド許可局)行って下にスクロールや「次のページ」とか行ってみてください。各回にあるリモコンマークの再生ボタンを押せばすぐ聴けるし、「DL」というところを押せばダウンロードできます。
【第180回“大好きなファーストフード”論 】
3人がただただ自分の好きな食べ物について語り合う、という許可局のお家芸的回。この人たちの特長はただ単に「あれ旨いよね」というだけに終わらず、なぜそれが旨いのか、その旨さは自分に取ってどういう意味があるのか、という屁理屈をひたすらこねくり回す点。それがよく分かる回。
【緊急特番“ラジオ”論】
TBSラジオ60周年記念番組に出たときの回。ラジオについて語っています。このときのマキタ局員の「しゃべりたかったんだよ!」という心の叫びは白眉。なぜか途中、インスタントラーメンの話に脱線していくのもすばらしい。
【第184回“この志ん朝がヤバい! 傑作三席”論】
許可局員の一人サンキュータツオ氏は落語に造詣が深い。そのタツオ局員が平成の名人古今亭志ん朝の魅力を余すところ無く語った回。「落語大嫌い!」という人でなければ必ず「へーちょっと志ん朝って聞いてみようかな」と思うはず。そうやって自分の触れたことの無かったものに触れてみる、ということって人生おいて幸せなことだと僕は思うんだよね。
もしこれで落語に興味を持ったら是非、東京ポッド許可局の「小朝論」そして「小朝論~その後~」の小朝シリーズを聞いていただきたい。どれだけ落語の世界が興味深いかを必ずご理解頂けるはず。
何でもやっぱり生で見るといいね、と言う話は今度別にしたいと思ってます。
行ってきたのは「東京ポッド許可局」というポッドキャストで放送している番組のイベント。

東京ポッド許可局と言うのはマキタスポーツ、プチ鹿島、サンキュータツオ、という3人の芸人がいろんなこと(えーっとM-1とかビートたけしとかアイスとかキャベツとか…)について3人で話している、という音声だけの番組。
これがねー、面白いんだわ。
キャッチコピーは「屁理屈とはスポーツである」。
いいおっさんたち(だいたい30代後半から40歳)3人がジュースについて「あれ旨い!」だの、お笑いについて「手数の時代に入っている」だのを話し合っているのなんて、聞いてるこっちもずいぶん物好きだなぁと思うところはあるけども。
ぜひ騙されたと思ってポッドキャストを登録してみるか、iTunesとかもって無くてもパソコンでも聞けるので聞いてみてください。
(一番下に余計なおせっかいですが、現時点で聞けるデータのうちお勧めを書いておきます。)
ここからちょっと大仰な話になるけども、僕はこの東京ポッド許可局を応援しています。
なぜか、というとまず、コンテンツとして内容が非常に面白いから。聞いていて笑うし、「なるほどなぁ」と膝を打つところも多い。落語なんて僕はそんなに詳しくは無いけどそれでも「小朝論」という回で、三遊亭円朝という大落語家についての詳しい話なんかは非常に参考になった。
そしてこれが基本的には無料で聞ける、というのがすばらしい。システムとしては毎週日曜にネットを通じて配信されてそれをダウンロード、あるいは視聴するのは無料。配信後、数週間でネット上の掲載は終わり過去のものを聞きたければ5回分まとめて300円で購入できる、という仕組み。だからPodcastに登録して自動的にダウンロードされるようにしておけば基本的に無料。
こんなすばらしい話はないね。
そしてここからが僕が言うことじゃないけど今後のメディア論的視点からの応援理由。
僕はこれが新しい芸人の「売れる形」になって欲しいと思っています。
登場する3人とも現時点では失礼ながら決して世間的に有名、という人ではない。ダウンタウン、ナインティナイン、ブラマヨ、オードリーとか今テレビを付ければ見られる人とは比べ物にならないくらい知名度はない、大変失礼だけれども。
でもね、僕は思うんだけどテレビにいつも出ている人たちしか見たり聞いたり出来ない、という状態ってすごく淋しい。
出来れば面白い人も(そりゃもちろん面白くない人も)たくさんいて、そんな中で楽しめたほうがいい。
もちろんテレビだけが「世間」ではなくてテレビに出ていないけど面白い人は現時点ではたくさんいるだろう。僕が知らない面白い人、そして僕の知らないところで人気がある人だってまだまだたくさんいるんだろうと思う。だけどこれだけネットが発達した現代においてもその人たちを知ることが出来ない人、知っているけど触れるチャンスが無い人だってたくさんいる。たとえば地方に住んでいたりするとね。
あくまで素人意見だけど今のテレビはもうガチガチで、人気のある人(というか「人気があると思われている人」)しか出てこない。
そんな中、自分たちを面白いとちゃんと自信を持っているけど出るチャンスが無い人ってたくさんいるんだと思う。(その人たちがかけたチャンスがM-1であったと思うんだけど)
そしてそこにも入れない人がいて、残念ながらそういう人たちは今までどれだけコアなファンを得ていても残念ながら消えていくしかなかった。ファンがどれだけコアでも絶対数が少なければ商売にならない。
そんな状況をこの人たち、東京ポッド許可局は打破しようとしていると思う。
お金なんてほとんどかけずに3人で集まって1個のICレコーダーの前で話している。それをこれまたお金をかけずにPodcastとして配信する。ただそれだけ。それでもその話が面白ければ人は集まってくる。なんとまぁいまPodcast登録者数20万人ですって。
その20万人のうち何人がちゃんと聞いているかは誰にも分からないけど、場合によってはゴールデンタイムでも視聴率1%を切ってしまう現在においてもテレビよりもそれは大きな影響力なんじゃないだろうか。
僕はこういうパターンがどんどん出てくればいいと思っています。
こういう「話」の形だと二番煎じになってしまうけど、たとえば楽器を使わずめちゃくちゃすごいオリジナル曲を演奏できるよ、って人がいたとする。今までだったらこの人は単なるもの珍しい人で、うまく行ってもちょっとしたバラエティに出て終わり、ってくらいだろう。CD売ろうにもお金がかかるからそんなに作ってくれる人なんていない。自主制作しても限度がある。
でもこのパターンを踏襲すれば、まずはPodcast配信をする。いい物であれば聴取者が増える。その中で欲しい、という人にのみオリジナル音源をネット販売する、ということが可能かも知れない。直接的に販売出来なくてもそれが知名度を上げる要因になり、何かしらのチャンスが生まれることだってあるかも知れない。
Ustreamだって今は玉石混合だけどその中からきちっとお金を稼いでいく人が現れればもっともっと発展するだろう。
結果、テレビの視聴率が下がってテレビがつまらなくなってもそれは時代の流れだもの、仕方が無い。(ただあえて僕は言っときたいけど僕は典型的にテレビっ子でテレビとともに育ってきた人間だから「そーんなにテレビは弱くないだろ」と思っているけどね。お金無いならないでどうにかするよ、たぶんテレビは。)
この「東京ポッド許可局」も現時点では大きく儲かっている、というわけではない。(イベントでも本人たちがしきりに言っていた) でも僕はこういう人たちこそちゃんと儲かって欲しいと思う。ウハウハ、ってほどでなくても少なくとも本人たちがやりたいこと(つまりこの番組)を続けられる程度に。そうすれば何より聞いている僕が楽しめるもの。
なんとこの東京ポッド許可局、8月28日に日比谷公会堂で2,000人集めるイベントを行う。(→大東京ポッド許可局)
先日見てきたイベントはこの大イベントのオフレコトークもあった。聴いていると一言で「2,000人集める」と言ってもこれは大勝負なんだなぁということがよく分かる。スポンサーのいるイベントではないからイベント費用は本人たちが出している。現時点で2,000人の動員力のある人たちでは無い。もし不運が続けばお客さんが入らず大赤字ってこともありうるだろう。
この「行けるのか行けないのか」というドキドキ感がたまらない。本人たちが言っていた「僕ら失敗している余裕がある年齢でもないし、後戻りが出来る年齢でもないんです!」はかなりグッと来たなぁ。僕自身、この人たちとほぼ同世代、と言っていい世代だからこの気持ちはよく分かる。
僕は決してお笑いに関して先物買いをする人間ではない。たとえばお笑い番組を細かくチェックして「あ、この芸人がこれから来そうだな」なんてことをやる人間ではない。だから数年後に「あいつらは俺がずっと前から目をつけてたんだよ」と言いたくて応援しているわけじゃない。
ただ上記のような理由で、必ずこの人たちは脚光を浴びるはずだと思うし、ぜひ浴びて欲しいと願っている。そうすれば世界はもっと面白くなるはず。
というわけで僕は東京ポッド許可局を応援しています。
気になる方は本も出てますからぜひ手に取ってみてください。買うのが躊躇われるならお貸しします。
 東京ポッド許可局 ~文系芸人が行間を、裏を、未来を読む~
東京ポッド許可局 ~文系芸人が行間を、裏を、未来を読む~【オマケ:2011年6月21日時点で聞ける東京ポッド許可局お勧め回】
上記でも書いたけど東京ポッド許可局のコンテンツは大体10~30分くらいの音声コンテンツ。形式としては3人(許可局員、という形式)がtだただしゃべっているだけ。プラスたまに謎の局長と言う人が入ってくる時もある。
テーマはかなりばらばら。
毎週日曜日更新、公開期間(つまり無料で聞ける期間)は数週間。ただPodcastに登録(あるいは自分でダウンロード)してパソコンに保存しておけばずっと聴ける。
どの回も面白いけど人によって好みがあると思うので(僕は全部好きだけど)お勧め回を余計なお世話ですが書いときます。
※このページ(→東京ポッド許可局)行って下にスクロールや「次のページ」とか行ってみてください。各回にあるリモコンマークの再生ボタンを押せばすぐ聴けるし、「DL」というところを押せばダウンロードできます。
【第180回“大好きなファーストフード”論 】
3人がただただ自分の好きな食べ物について語り合う、という許可局のお家芸的回。この人たちの特長はただ単に「あれ旨いよね」というだけに終わらず、なぜそれが旨いのか、その旨さは自分に取ってどういう意味があるのか、という屁理屈をひたすらこねくり回す点。それがよく分かる回。
【緊急特番“ラジオ”論】
TBSラジオ60周年記念番組に出たときの回。ラジオについて語っています。このときのマキタ局員の「しゃべりたかったんだよ!」という心の叫びは白眉。なぜか途中、インスタントラーメンの話に脱線していくのもすばらしい。
【第184回“この志ん朝がヤバい! 傑作三席”論】
許可局員の一人サンキュータツオ氏は落語に造詣が深い。そのタツオ局員が平成の名人古今亭志ん朝の魅力を余すところ無く語った回。「落語大嫌い!」という人でなければ必ず「へーちょっと志ん朝って聞いてみようかな」と思うはず。そうやって自分の触れたことの無かったものに触れてみる、ということって人生おいて幸せなことだと僕は思うんだよね。
もしこれで落語に興味を持ったら是非、東京ポッド許可局の「小朝論」そして「小朝論~その後~」の小朝シリーズを聞いていただきたい。どれだけ落語の世界が興味深いかを必ずご理解頂けるはず。