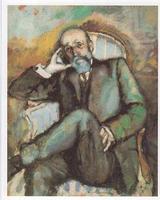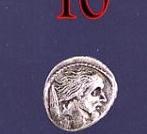(一応言っときますが「ローマ人の物語」のネタばればっかりです。しかも僕の理解なんで間違いもたくさんあると思う。)
先日も書いたけど
「ローマ人の物語」
先日書いた時点では10巻の3分の2を読み終えたところでちょうどクライマックスの「ルビコン渡河」までは行っていなかった。えがったよ、ルビコン。
詳しくはwikiっていただければいいけども
古来から軍装のままルビコン河を渡ってはいけない、という決まりがあった。ルビコン前で軍団を解散しなければいけない。
ガリアを制圧したカエサルに恐れをなしたローマ元老院はカエサルにローマ帰還を命じた。ガリアからローマに帰還するということはルビコンを渡らなければいけない、つまり「即時武装解除」を意味する。丸腰でカエサルが戻れば過去のいろいろなところ(金の使い道、軍団の私用化)にいいがかりをつけられ、ガリア制圧の英雄から一気に反逆者にさせられることは必至。
前にルビコン川、背に自分の軍団6万、というところでカエサルは悩む。ここで軍団を解散し元老院に降るか、あえて反逆者としてルビコンを渡り元老院を相手取り戦うか。戦うとなればローマ軍側の総大将は長年の盟友であり「ローマ最高の武人」ポンペイウス。
心酔しきった自分たちの将軍、自分たちの英雄、カエサルの背中を見つめながら何も言えない6万人の兵士たち。渡らなければ自分たちの戦功はすべて元老院のもの、渡ればローマ帝国への反逆者。
カエサルの目の前には渡ってはいけないルビコンの水面。ローマと属州を隔てるその河は小川と言ってもいいくらいの浅い川、水深は膝丈ぐらいしかない。その川の向こうには自分たちを利用するだけ利用して権力にしがみつくだけの元老院たち、そして祖国ローマ。
振り返ったカエサルが言う。
 「ここを渡れば人間世界の悲惨、渡らなければわが破滅。
「ここを渡れば人間世界の悲惨、渡らなければわが破滅。
進もう!神々の待つところへ!我々を侮辱した敵の待つところへ!
賽は投げられた!」
ひょえ~~なんだこのかっこよさ。歌舞伎なら「イヨっ!ユリウス屋!!」と掛け声が飛ぶところだね。
読んでる僕も兵士たちと同じく「カエサル!カエサル!我がカエサル!」とこぶしを振り上げたくなる。
マントを翻しカエサルがルビコン河に足を踏み入れる。それに続く屈強な軍団。6年にわたるガリア戦役を生き抜いた子飼いのローマ兵はもちろん、中にはガリアで調達した蛮族出身の果敢なものたちもいる。行く手を祝福するかのような北イタリアの旭日(このへん僕の脳内ムービー)。
…というところで「ローマ人の物語4 ユリウス・カエサル ルビコン以前」はいったん幕。
本来であれば一服する間も無く「ローマ人の物語5」に入るところだけど残念ながらまだ入手していないんだよね~。
うーむ、と仕方が無いので5を飛ばし「6 パクス・ロマーナ」にちょっと目を通してみる。どうやらこの巻の主役は暗殺されたカエサルのあとを継いだアウグストゥス。彼はカエサルの甥にあたり、カエサルの養子。
どうもね~、惹かれないね~。カエサルが面白すぎたってのもあるし、6のあとの「7 悪名高き皇帝たち」のほうが面白そうじゃないですか。なんとか名前だけは知っている暴君ネロも出てくるようだしね。
うーん、と思いつつぺらぺら読んでたら、
これが面白くてたまらない!すごいな、アウグストゥス。びっくりした。

著者も巻頭で言っている。「この巻にはハンニバル戦記のような血沸き肉踊る活劇もない、カエサルのような天才も出てこない。それでもアウグストゥスの生涯を追う間、私はまったく退屈しなかった。」
まだ3分の1程度しか読んでいないんだけどそれだけでも面白い。
「
パクス・ロマーナ」とはアウグストゥスが推し進めた「ローマ世界の平和」のこと。この頃にはローマはほぼ世界一の勢力となっており蛮族との戦いなど、戦争はほぼない。アウグストゥスがやったのはいろいろな内政改革といかに自分に権力を集中させていくか、ということのみ。
(自分に権力を集中させることが野心からなのか、それともローマのことを考えてなのかはまだこの巻の途中なのでわからない)
戦争シーンが無く政治シーンだけなんだけど、アウグストゥスのやり方というのは元老院たちの思考、民衆の思考を先読みしてまったくそつが無く素晴らしい。
あの天才カエサル(この巻の頃には「神君」という呼び名さえ与えられ神とされている)のやったことでさえ、アウグストゥスに比べてしまうとちょこちょことほころびが目立つ。
もちろんゼロから作り上げたカエサルとカエサルの残したものを最大限に利用できるアウグストゥスではスタートラインが違うので一概には言えないけど。
そしてほころびが目立つからと言ってカエサルの評価はまったく下がらない。むしろ「あの天才カエサルもなかなか人間らしいところがあるじゃないか」と更にカエサルを好きになる。
対して(あくまで今の段階では)アウグストゥスから「人間臭さ」というのはまったく感じない。非常に冷血に合理的に、物事を進めていく。
元老院たちに対して、「これは我慢するからこの権利はくれ」「そのかわりあなたたちにはこの権力をやる」と交渉していく。またこの交渉内容がうまい。元老院が「イエス」「イエス」「喜んで」と返事をしているうちに気づいたらアウグストゥスに権力が集中している。そして元老院はどんどん弱体化している。
「ひとつひとつの交渉は合法なのにすべてが合わさると非合法になっている」と著者も書いている。
たとえば元老院が大喜びした共和制の復古。カエサルの跡継ぎということでアウグストゥスは皇帝になるのではないか、と元老院が心配していた。そこでアウグストゥスは「すべての特権を元老院とローマ市民に返す」と宣言する。元老院大喜び。でもよくよく考えてみるとそのときアウグストゥスが持っていた特権というのは名誉職だったり戦乱の時代でなければ役に立たないもの、持っていても手間だけかかるもの、ばかり。特権を放棄する代わりにアウグストゥスが求めたもののひとつが、「アウグストゥス(英語で言うとオーガスタス。Augustの語源)」という呼び名。
アウグストゥスの本名はオクタヴィアヌス(英語Octoberの語源)。アフリカヌス(=アフリカ王)、マーニュス(=偉大な)と言った権力のニオイがする呼び名と違い、アウグストゥスは単に「神聖な」という意味。元老院はどうぞどうぞと与えた。実はこれが後々おおきな意味を持つことになる。権力に権力で戦うのではなくまったく別次元から、むしろ神職的な立場から力を及ぼせるようになる。
他にもガリア全土の統治権(元老院は愚かしくも、狭いけど統治が簡単な北イタリアあたりの統治権を求め、広大なガリアの統治は大変なので、アウグストゥスに
お願いした。)も得る。これでガリア(いまで言うドイツ、フランスあたり)からの税収、兵を手に入れることになる。
更にアウグストゥスはこれまで連続で担当してきた執政官を辞職し、執政官選挙を行う、とした。選挙で選ばれる執政官こそがローマ共和制の象徴なので元老院大喜び。
そしてアウグストゥスは謙虚に「執政官を降りる代わりに護民官の特権を一年期限でくれないか」と頼む。元老院は快くOK。
しかし護民官特権の中には「拒否権」というのがあって元老院や執政官が何を決めようが護民官(つまりアウグストゥス)がダメと言ったらダメ。
更に護民官の特権のもうひとつが「身体不可侵権」。護民官の身体を誰も傷つけられない。どんな理由があろうとも護民官と戦ったり、ましてや殺したりしたらその時点で犯罪者。
この権利を持ったことでアウグストゥスに逆らえるものは誰もいなくなった。
もちろんアウグストゥスは狡猾に「一年期限の特権は誰かから異議が発せられない限り自動更新とする」という条文を盛り込むのを忘れていない。実質、最高権力者になったアウグストゥスが何も悪いことをやっていないのに「異議あり」といえる人などいるわけない。つまりほぼ終身の特権を元老院ともめることなく(むしろ喜ばせて)得たことになる。
アウグストゥスがすごいところは元老院がこだわっているけども実質的には役に立たない古くからの役職や権力を気前良く与えて元老院を喜ばせ、その代価として誰も気にも留めないような小さなものを「くれ」とお願いする。そしてその小さなものが後々、大きな決め手になる。
将棋で言うと使いどころが無いと思ったら気前良く飛車や角を取らせておいて、そのうちにためておいた歩で追い込んでいくような将棋。
もし今の時代にカエサルやアウグストゥスがいたら、と夢想する。
たぶんカエサルにとっては今の世界はこじんまりしすぎていてつまらないのではないか。戦争も無いしね。いっぽうアウグストゥスはどうか。ビジネスマンとしてもあるいは政治家としてもやはりトップに立っていたんじゃないかと思う。
カエサルがすべてのものを巻き込んで行く竜巻だとしたらアウグストゥスは冷たい雨。降っていることさえ気づかないくらいなのに着実に大河になっていく。