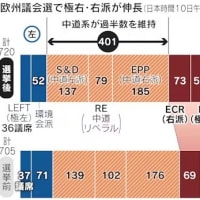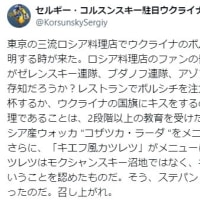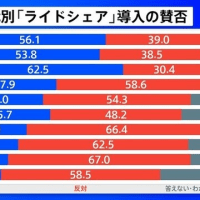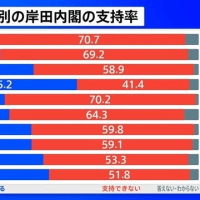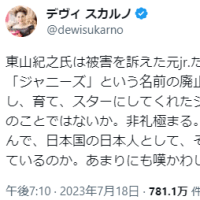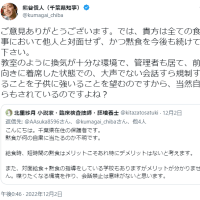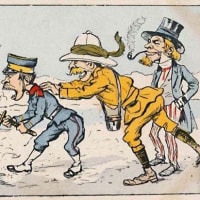戻し税 -どこか腑に落ちない輸出企業への消費税の還付(プレジデントオンライン)
前回の消費税増税の際には、税率が高くなった分、大手メーカーが下請けに値引きを要求したケースも多いといわれている。先の例では80万円の商品にかかる4万円の消費税分だけ本体価格を値下げさせ、消費税込み80万円で納入させる形だ。
当然、下請け企業はコストカットを迫られ、利益も圧迫されることになる。しかも「80万円-(80万円÷1.05)=3万8095円」だけ預ったという形の消費税を納税しなくてはならない。赤字なら法人税はかからないが、消費税はあくまで預かったものであり、業績に関係なく納める義務がある。下請け企業にとってはまさに“泣きっ面に蜂”だろう。
問題はこれだけではない。大手メーカーは形としては仕入れの際に消費税を払っていることになり、海外販売分については、4万円分の輸出戻し税の還付を受けることができるのだ。
的中率50%の予報と的中率10%の予報、信頼を置けるのはどちらでしょうか? もちろん「外れ方」には複数のパターンがあるわけで、AでなければBになるとは限りません。ただそれでも、当たるか外れるかは当日になるまで分からない的中率50%の予報よりも、何の可能性をほぼ消去しても良いかを教えてくれる的中率10%の予報の方が、だいたいの場面では当てになるように思います。そうした面から私が絶対の信頼を置いているメディアとして週刊ダイヤモンド(ダイヤモンド・オンライン)が挙げられるところですけれど、ここで引用したプレジデントはどれほどのものでしょう。今回の記事は社風に合っていないのではないかな、と思わないでもありません。
参考、消費税についてのまとめ
消費税特有の諸問題については上記リンク先で詳しく扱いましたが、プレジデントの記事が「腑に落ちない」としているのは、まとめで言うと4番目「立場の強い企業、とりわけ輸出企業にとっては益税になりがち」で指摘したものであり、その原因が3番目「負担者が曖昧」にあるわけです。詳細はリンク先でお読みいただければと思いますが、要するに上流のメーカーは「仕入れ」にかかった消費税を「還付」として受け取ることができる、しかるに「仕入れ」の費用に消費税がしかるべく転嫁されているかと言えば、大いに怪しいものであり上流メーカーが消費税によって余分に得をしている疑いがあるというわけです。
例えば大手A社が下請けのB社から総額1,623,569円で「仕入れ」た場合、A社は仕入れにかかった消費税分として77,312円の還付金を受け取ります。そしてB社は消費税分として77,312円を国と地方に納めることになっています。建前上、消費税を負担しているのは支払った側、この場合で言えばA社であり、還付金を懐に収めることには何の問題もないと、そう強弁して憚らない人も少なくありません。本当にそうなのでしょうか? 手続きとして消費税を納めるのはどちらか、還付金を受け取るのはどちらか、その両者は鮮明です。しかし、実際に負担しているのはどちらなのかは、ある種の人々からの「定義」があるだけで現実は靄のかかったままです。
産経新聞の購読料は月額2,950円ですが、これにかかる消費税140円は誰が払っているのでしょうか? 吉野家の牛丼並盛り380円に課される消費税18円は、客が払っているのか、それとも店舗側が負担しているのか、自販機のジュース120円にかかる消費税6円は、客とメーカー(ベンダー)のどちらが払っているのでしょうか、もしかしたら折半になっているのでしょうか、あるいはもっと別の何かでしょうか? 結局のところ消費税は実際の負担者が判然としない、公正性の面で著しく欠陥がある税制なわけです(とりわけインボイス制度を省いた日本のシンプルな消費税はこの欠陥が強く出ています)。ただし、財界筋でも小売りは消費税増税反対の声が強く、メーカーの中でも輸出が多いところほど消費税増税を歓迎する向きが目立つ、法人税や社会保障費の雇用者負担には難癖を付ける一方で、消費税だけは大歓迎している企業経営層も多いわけです。消費税が誰にとって得な税制なのかは、概ね類推できるところでしょう。
消費増税 転嫁カルテル容認 自民、特別措置法素案まとめ(産経新聞)
自民党は22日、平成26年4月からの消費税率の引き上げを前に、大企業の下請けの中小企業が、増税分を適切に価格転嫁できるようにする特別措置法案の素案をまとめた。複数の企業で増税分の製品価格への上乗せを取り決める「転嫁カルテル」を条件付きで容認する。大企業の「下請けいじめ」を防ぐ狙い。自民党は3月をめどに最終的な法案をとりまとめ、29年3月末までの時限立法として今国会に提出する。
(中略)
中小企業にとって、商品価格に消費税の増税分を上乗せできるかは大きな課題だ。優越的な地位にある大企業から価格の据え置きなどを迫られた場合、立場の弱い中小企業はこういった要求を断れない恐れがあるからだ。
「消費税還元セール」は駄目=増税転嫁対策で―自民方針(時事通信)
自民党は8日、2014年4月の消費税率引き上げに合わせて、小売店が「消費税還元」と銘打ったセールを行うことを認めない方針を固めた。消費税の引き上げ分の還元や値引きを連想させる表示が、価格転嫁に悪影響を与えることを懸念。結果的に、大手スーパーなどの大規模小売店に比べて体力の弱い中小小売店の経営を圧迫する恐れがあると判断した。
民主党と「愛の結晶」を育んだ自民党ですが、当初に比べれば多少は問題に立ち向かう姿勢も見せているようです。建前とは違って現実には消費税分を転嫁することは難しく、仕入れ(購入)側ではなく納入(販売)側が消費税を負担することも多いだけに、上で引用したような対策が求められるのは当然です。しかし、そこまでして消費税を上げるくらいなら他のもっと透明性のある税を考えた方が賢明でしょうね。軽減税率云々も逆進性の緩和措置としてはともかく、では奢侈品を対象とした物品税を廃止して一律の消費税に移行したのは何だったのか、総額表示(税込み価格での表示)の義務づけを緩和するなんて動きもありますけれど、そもそも総額表示の導入が誤りだったのではないか等々と疑問は尽きません。誤りを塗り隠す努力をするより先に、誤った道から引き返す決断をすべきと言えます。