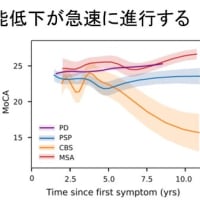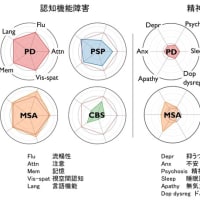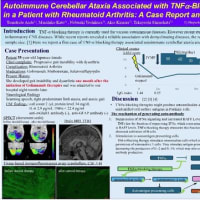アカデミア(大学)における基礎研究の成果が具体的な事業化に結びつかないことは極めて多い.このため,研究開発と事業化の間にあるギャップは「死の谷」と呼ばれてきた.私は,これまでの体験から,アカデミア研究者が,「死の谷」を克服するためには,①動物実験の質の改善,②知的財産権の確保,③トランスレーショナル・リサーチ(translational research; TR)の考え方を理解することが重要であると考えた(リンク先のブログを参照).ちなみにトランスレーショナル・リサーチとは「基礎医学の成果を臨床に生かすための研究」を指す.
今回,マンスフィールド財団 – PhRMA(米国研究製薬工業協会) Research Scholars Program 2015に参加することができ,2週間をかけて,ワシントンDC,フィラデルフィア,ボストンを訪れ,米国におけるTRのシステムを学んだ.具体的には,米国政府の医療政策部署(下院の専門委員会,NIHの創薬部門,FDA),米国研究製薬工業協会(PhRMA),シンクタンク(Brooking institution),民間製薬会社(ファイザー,ヤンセン,ノバルティス,Biogenなど),大学研究機関(ペンシルバニア大学,MGH,マサチューセッツ工科大学,ハーバード大学,タフツ大学),患者会,投資家などを訪問した.薬剤シーズの段階から製品化に至るまでの過程でどのようにそれぞれが連携しているかというシステム(エコシステム)について学ぶことができた.本プログラムで学んだこと,5つにまとめてみたい.
1) 創薬の実現にはTRを学ぶ必要がある!
当たり前のことであるが,TRは日本では必ずしも浸透していない.アカデミア研究者が行う研究には「基礎生物学としての医学研究」と「臨床応用を明確に目指す医学研究」があるが,日本では後者に取り組むアカデミア研究者が圧倒的に少ない.日本には昔から「医は仁術」と,医学において,金儲けをすることを好ましいこととしない風潮があるが,アカデミア研究者は,患者さんに新薬を届けるためには,知的財産確保や産学連携が不可欠であることを認識する必要がある.分子標的を見つけるなど,途中まで研究を行ったら,後は誰かがやってくれるという考えでは,創薬には到達しない.むしろ本気で創薬を目指している者の妨げにもなりうることを認識する必要がある(その研究のため,新規性が認められない事態になり,知財が確保できない).
2) 2つの重大な選択を慎重に考える!
アカデミア研究者は,臨床応用への具体的な道筋を考えて研究を行う必要がある.この道筋を創薬領域では「パイプライン(図)」と呼び,通常,アイデアを見出してから承認されるまで,12~15年もかかる長い道のりである.このパイプラインにおいて,自身の創薬シーズの置かれている場所が,研究開発(research & development;R & D)のどの段階にあるかを常に意識する必要がある.
そしてそのパイプラインのなかで,2つの重大な選択がある.1つ目は何を標的分子として選択するか?2つ目は治験の際,どのような患者さんを選択するか?である.前者では,効果判定と毒性の評価を効率的に行う努力をすることが大事である(例:ロボットによるハイスループットスクリーニング,げっ歯類からイヌ・ネコモデルへの変更,組織チップなど).後者では,治験の際に,どのような患者さんを選ぶかによって結果が大きく変わるため,治療が効果を示す患者さんを見出すことができるバイオマーカーの発見も必要である.
3) アカデミアにおけるTRのサポートする仕組みをつくる!
アカデミアはTRのサポートをより積極的にする必要がある.まずイノベーションを可能にするcollaboration,つまりアカデミア研究者とその周囲を結びつけるネットワークづくりをサポートする必要がある.米国では,基礎研究者,臨床医,製薬企業,投資家,患者などと結びつける仕組みがすでに確立していた.
またTR教育も積極的に行う必要がある.米国におけるTRを学んだ我々スカラーが中心となり,各アカデミアにおけるTRの教育を強化・充実させることが大切である.医学部の場合,卒前,卒後といった,それぞれのステージごとに教育を行う必要がある.またTRの先駆者は,自身の成功体験を伝えていくことも大切である.
4) 患者さんの視点で考える!
近年,unmet medical needs(まだ治療法が見つかっていない疾患に対し,患者さんから強く求められている医療ニーズを指す)を意識した,患者さんを中心とする創薬アプローチの重要性が指摘されている(patient-centric approach).このほかにも患者の治療効果の判定を患者さんの視点から行うpatient-reported outcome(PRO)や,患者団体とともに創薬開発の研究費を求めていくなども考えられる.とくに患者さんが少ない希少疾患Rare diseaseにおいては,患者団体との連携が必要である.
5) レギュラトリー・サイエンスの重要性を認識する!
創薬開発は,法律に則って実践する必要がある.すなわち薬事法と創薬の関係を理解しない限り,創薬開発は先に進まないというレギュラトリー・サイエンスの考え方を理解する必要がある.具体的には,アカデミア研究者は,医薬品の有効性および安全性の確保のために必要な規制が行われていることと,研究開発の促進のために必要な措置が講じられていることを理解する必要がある.
おわりに
今回のプログラムでは財団関係者を始め,米国の多くの方々にお世話になった.自身のTRを推進し,アカデミア研究者にTRを行う重要性を伝えることで恩返しをしたい.

今回,マンスフィールド財団 – PhRMA(米国研究製薬工業協会) Research Scholars Program 2015に参加することができ,2週間をかけて,ワシントンDC,フィラデルフィア,ボストンを訪れ,米国におけるTRのシステムを学んだ.具体的には,米国政府の医療政策部署(下院の専門委員会,NIHの創薬部門,FDA),米国研究製薬工業協会(PhRMA),シンクタンク(Brooking institution),民間製薬会社(ファイザー,ヤンセン,ノバルティス,Biogenなど),大学研究機関(ペンシルバニア大学,MGH,マサチューセッツ工科大学,ハーバード大学,タフツ大学),患者会,投資家などを訪問した.薬剤シーズの段階から製品化に至るまでの過程でどのようにそれぞれが連携しているかというシステム(エコシステム)について学ぶことができた.本プログラムで学んだこと,5つにまとめてみたい.
1) 創薬の実現にはTRを学ぶ必要がある!
当たり前のことであるが,TRは日本では必ずしも浸透していない.アカデミア研究者が行う研究には「基礎生物学としての医学研究」と「臨床応用を明確に目指す医学研究」があるが,日本では後者に取り組むアカデミア研究者が圧倒的に少ない.日本には昔から「医は仁術」と,医学において,金儲けをすることを好ましいこととしない風潮があるが,アカデミア研究者は,患者さんに新薬を届けるためには,知的財産確保や産学連携が不可欠であることを認識する必要がある.分子標的を見つけるなど,途中まで研究を行ったら,後は誰かがやってくれるという考えでは,創薬には到達しない.むしろ本気で創薬を目指している者の妨げにもなりうることを認識する必要がある(その研究のため,新規性が認められない事態になり,知財が確保できない).
2) 2つの重大な選択を慎重に考える!
アカデミア研究者は,臨床応用への具体的な道筋を考えて研究を行う必要がある.この道筋を創薬領域では「パイプライン(図)」と呼び,通常,アイデアを見出してから承認されるまで,12~15年もかかる長い道のりである.このパイプラインにおいて,自身の創薬シーズの置かれている場所が,研究開発(research & development;R & D)のどの段階にあるかを常に意識する必要がある.
そしてそのパイプラインのなかで,2つの重大な選択がある.1つ目は何を標的分子として選択するか?2つ目は治験の際,どのような患者さんを選択するか?である.前者では,効果判定と毒性の評価を効率的に行う努力をすることが大事である(例:ロボットによるハイスループットスクリーニング,げっ歯類からイヌ・ネコモデルへの変更,組織チップなど).後者では,治験の際に,どのような患者さんを選ぶかによって結果が大きく変わるため,治療が効果を示す患者さんを見出すことができるバイオマーカーの発見も必要である.
3) アカデミアにおけるTRのサポートする仕組みをつくる!
アカデミアはTRのサポートをより積極的にする必要がある.まずイノベーションを可能にするcollaboration,つまりアカデミア研究者とその周囲を結びつけるネットワークづくりをサポートする必要がある.米国では,基礎研究者,臨床医,製薬企業,投資家,患者などと結びつける仕組みがすでに確立していた.
またTR教育も積極的に行う必要がある.米国におけるTRを学んだ我々スカラーが中心となり,各アカデミアにおけるTRの教育を強化・充実させることが大切である.医学部の場合,卒前,卒後といった,それぞれのステージごとに教育を行う必要がある.またTRの先駆者は,自身の成功体験を伝えていくことも大切である.
4) 患者さんの視点で考える!
近年,unmet medical needs(まだ治療法が見つかっていない疾患に対し,患者さんから強く求められている医療ニーズを指す)を意識した,患者さんを中心とする創薬アプローチの重要性が指摘されている(patient-centric approach).このほかにも患者の治療効果の判定を患者さんの視点から行うpatient-reported outcome(PRO)や,患者団体とともに創薬開発の研究費を求めていくなども考えられる.とくに患者さんが少ない希少疾患Rare diseaseにおいては,患者団体との連携が必要である.
5) レギュラトリー・サイエンスの重要性を認識する!
創薬開発は,法律に則って実践する必要がある.すなわち薬事法と創薬の関係を理解しない限り,創薬開発は先に進まないというレギュラトリー・サイエンスの考え方を理解する必要がある.具体的には,アカデミア研究者は,医薬品の有効性および安全性の確保のために必要な規制が行われていることと,研究開発の促進のために必要な措置が講じられていることを理解する必要がある.
おわりに
今回のプログラムでは財団関係者を始め,米国の多くの方々にお世話になった.自身のTRを推進し,アカデミア研究者にTRを行う重要性を伝えることで恩返しをしたい.