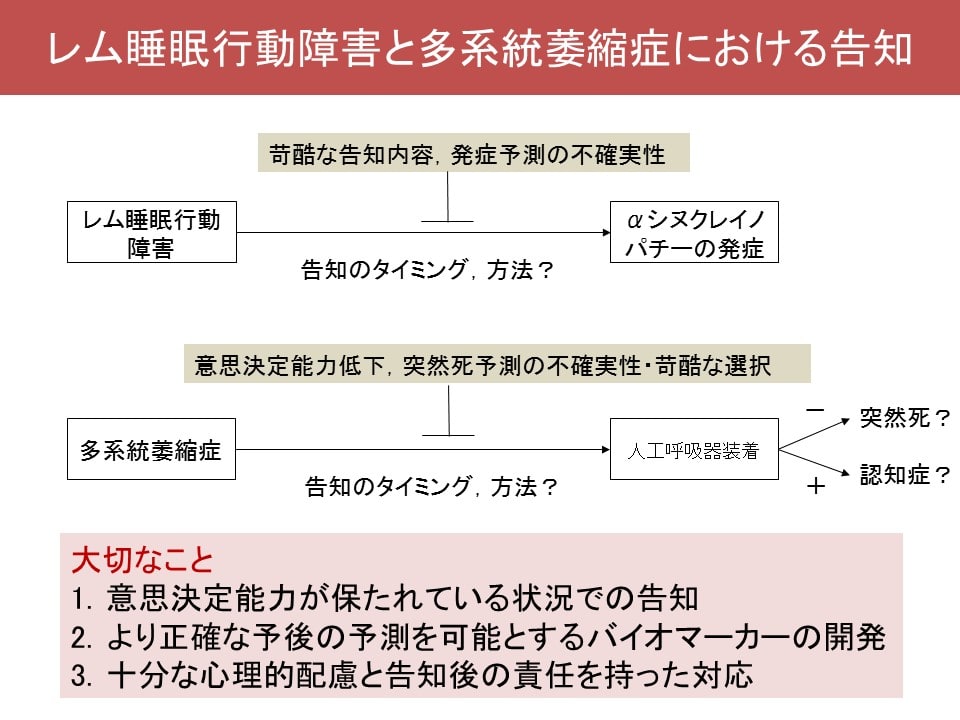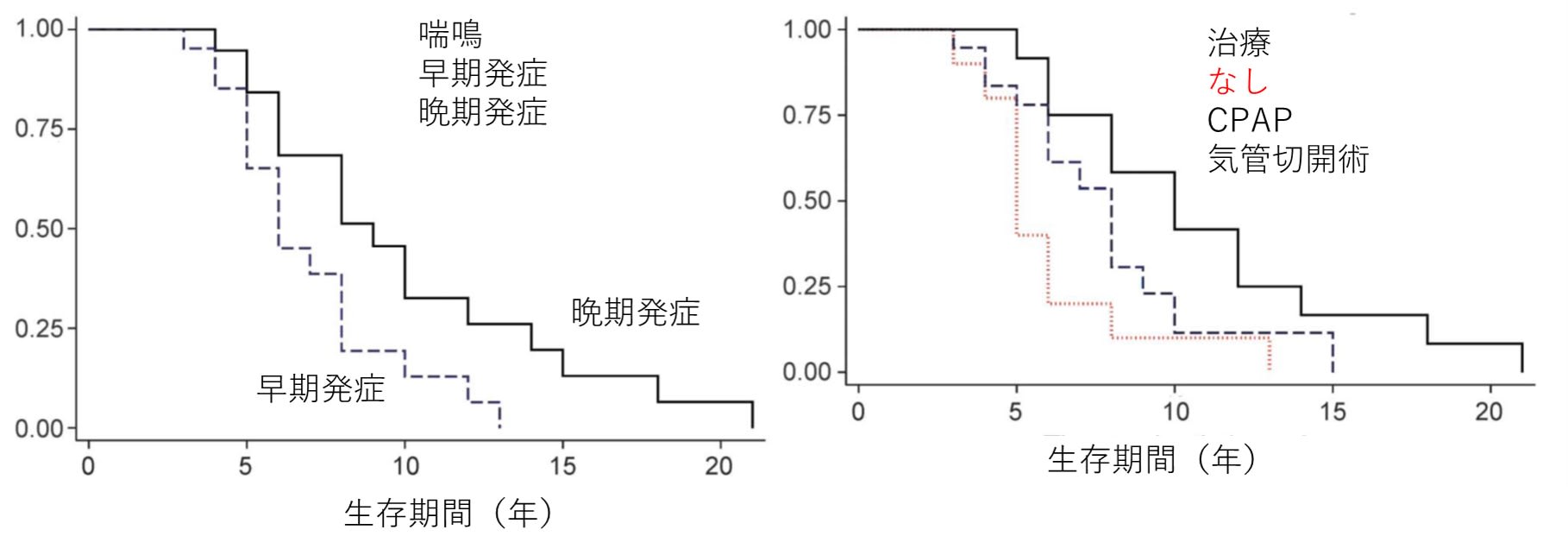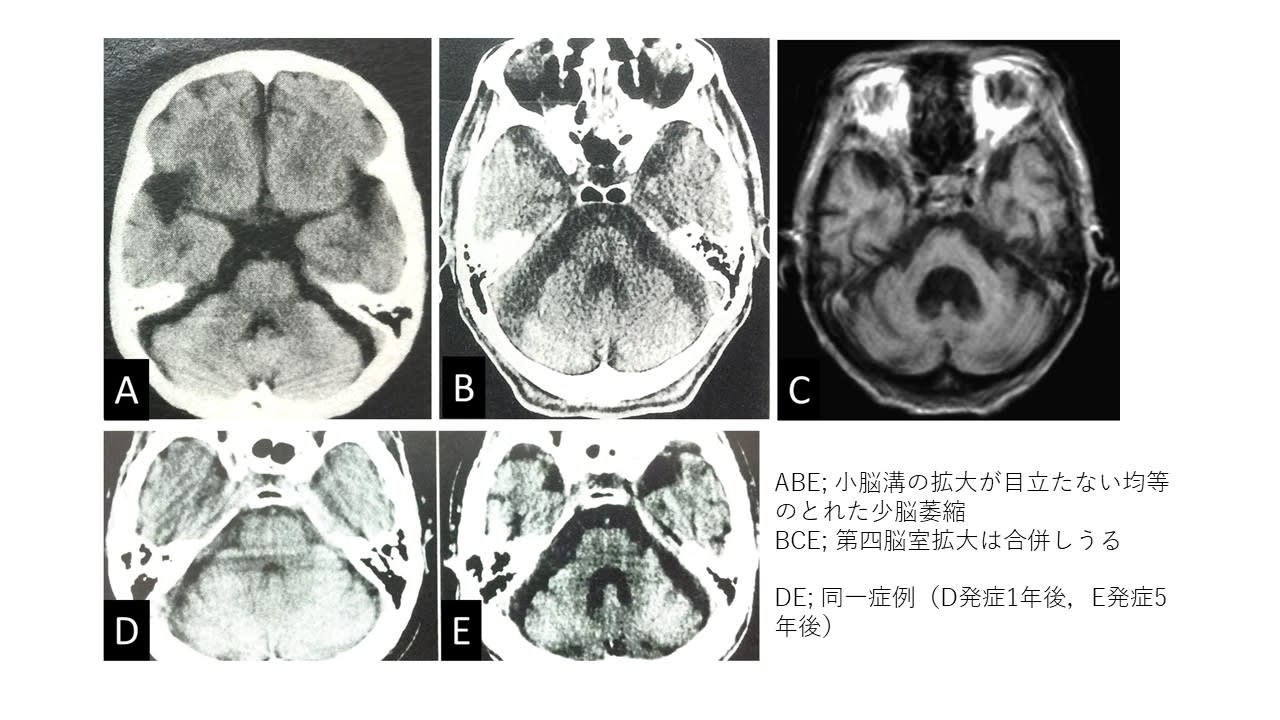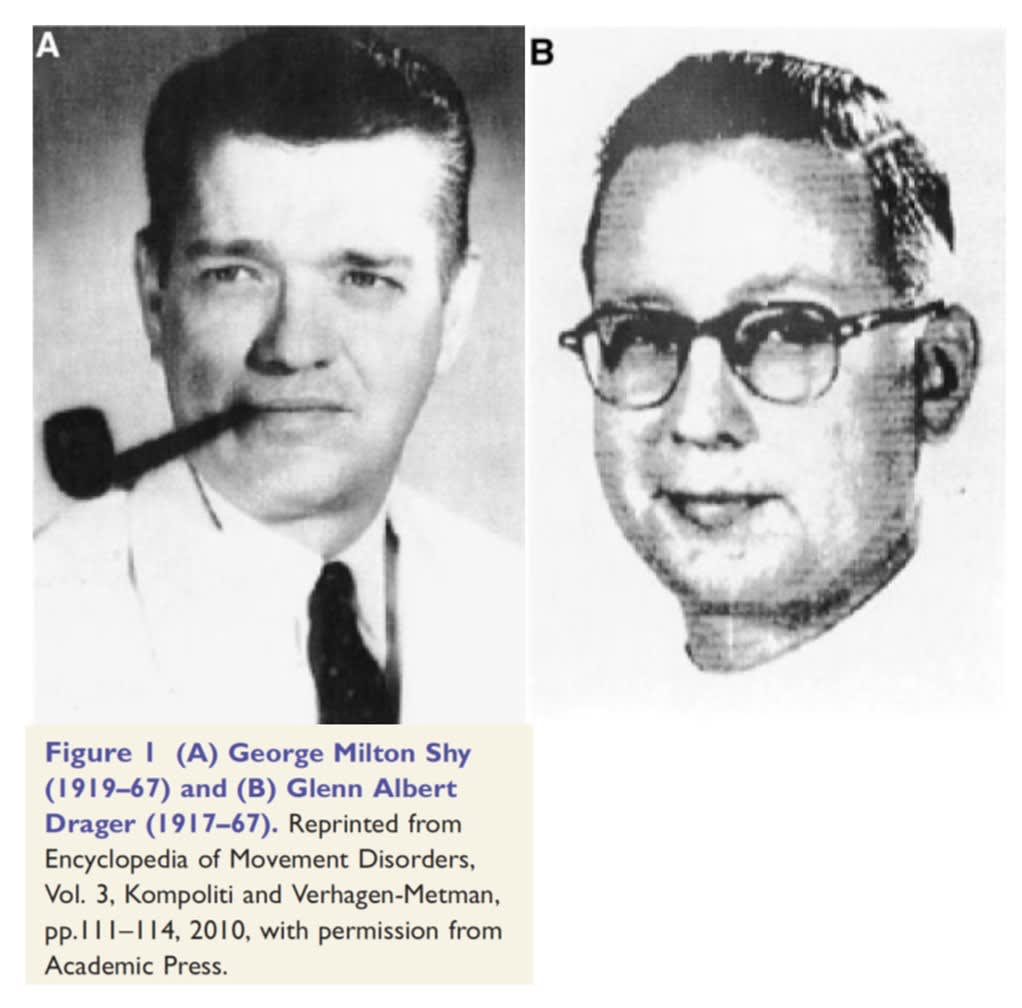近年,神経変性疾患の
臨床診断と病理診断の区別が厳密に行われるようになった.例として,臨床診断-大脳皮質基底核症候群(CBS)と病理診断-大脳皮質基底核変性症,そして臨床診断-リチャードソン症候群と病理診断-進行性核上性麻痺が挙げられる.では脊髄小脳変性症はどうだろうか?実はこのような区別が曖昧なままにある.具体的には,臨床診断・遺伝子診断に基づく疾患群の総称が脊髄小脳
「変性症」(SCD)で,その中の孤発例は皮質性小脳
「萎縮症」および多系統
「萎縮症」で,遺伝性は脊髄小脳
「失調症」1型,2型・・・・(SCA)となる.つまり変性・萎縮といった病理学的概念と,失調といった臨床的概念が,厳密に区別されることなく混在しているのだ.
Brain Nerve誌に掲載された古賀俊輔先生(メイヨークリニック)による「
孤発性脊髄小脳変性症の分類を再考する」という総説は,この問題を明快に議論した論文であり,一読して唸ってしまった.要旨を簡潔に述べると,まず孤発性脊髄小脳変性症の疾患概念の変遷を概説し,そして本邦と諸外国で用いられている疾患名の指す概念に相違があることを指摘している.その上で,これまで提唱された概念の中では
「原因不明の孤発性成人発症型失調症(sporadic adult-onset ataxia of unknown etiology:SAOA)」が一番,孤発性脊髄小脳変性症の臨床診断として相応しいのではないかと提案している.
本論文の内容は下図に集約される.一番上の段は,本邦の現在の分類で,特定疾患の分類に基づくものである.つぎに
「晩発性皮質性小脳萎縮症(late cortical cerebellar atrophy; LCCA)」という概念が出てくるが,これは欧米では異なる2つの定義で使用され混乱が生じうるため使用されなくなっている.具体的に,「狭義のLCCA」は下オリーブ核―小脳虫部に病変が限局する疾患を指す病理診断名で,「広義のLCCA」は二次性を含む孤発性脊髄小脳変性症を指している.一方,本邦では特定疾患において,LCCAのlateを外した「皮質性小脳萎縮症(cortical cerebellar atrophy; CCA)が使われているが,これは孤発性脊髄小脳変性症からMSAを差し引いたもので,欧米のいずれのLCCAとも合致しないという問題がある.事実,PubMedの検索で,CCAを使用している論文の65%は本邦の論文だそうだ.
次の
「特発性晩発性小脳性運動失調症(idiopathic late-onset cerebellar ataxia; ILOCA)」はかつてよく目にしたものだ.これは有名なAnita Hardingが1981年に提唱したもので,3型に分類される.つまり1.オリーブ橋小脳萎縮症(OPCA),2.小脳と下オリーブ核に限局するMarie-Foix-Alajouanine(マリー・フォア・アラジュアニーヌ)症候群,3.上肢の静止時および動作時振戦の目立つ群である.OPCAは現在のMSA-Cに相当し,病理学的に独立した疾患として確立されているため,OPCAを含むILOCAは本邦のCCAとは一致しない.
最後が
「原因不明の孤発性成人発症型失調症(sporadic adult-onset ataxia of unknown etiology:SAOA)」で,2002年Abeleらが提唱したものである.20歳以降発症の孤発性進行性小脳失調症のなかで,MSAと遺伝性疾患を除いたもの,つまり原因を特定できなかったものである.古賀はこのSAOAが,MSAをのぞく孤発性脊髄小脳変性症の臨床診断名として,無難な選択なのではないかと考えている.そしてこのなかに病理診断名としてのCCAが含まれるが,必ずしも純粋小脳型ではなく,振動覚低下やアキレス腱反射の低下・消失などの小脳症状以外の神経所見も見られる.
ちなみにSAOAの診断基準は以下のとおりである(
Abele M et al. J Neurol 254;1384-9, 2007).
1.進行性の小脳性運動失調
2.20歳以降の発症
3.家族歴なし(第一,ニ世代の親族になし.両親は50歳以上とし,すでに死亡している場合は50歳以上の場合家族歴を否定できる.血族近なし)
4.その他の原因を認めない(髄液異常,後頭蓋窩の梗塞・出血・腫瘍病変,アルコール依存,抗てんかん薬の長期内服,中毒,傍腫瘍症候群,抗GAD抗体陽性,ビタミンB12,E欠乏,梅毒,脳炎,甲状腺異常など)
5.亜急性発症ではない
6.遺伝子診断で陰性(SCA1,2,3,6,17,fMR1 premutation,FRDA)
7.Gilman分類のprobable, possible MSAではない
本論文を拝見し,MSAを除く孤発性脊髄小脳変性症の臨床診断名として,SAOAを使用することは妥当と思われる.ただしSAOAにしてもILOCAにしても,世界的に見て,現在,頻用されているわけではない.この件に関して古賀先生と議論させていただいたが,メイヨークリニック神経内科のWszolek教授とその周辺は「まずSAOAをいう診断をつけ,そこから遺伝子診断をはじめ各種検査を行い,鑑別診断を進める」というように暫定的な診断名として用いているとのことである.しかし「SAOAを使うことが世界的な流れになっているとまでは言えない」そうだ.
今後,SAOAが使われていくのか,別の名称が用いられるのか,もしくは従来のまま混沌とした状態が続くのかわからないが,少なくとも現在の問題点を認識し,議論を行っていくことが必要である.ぜひオリジナルの論文をご一読されることをお勧めする.
古賀俊輔.孤発性脊髄小脳変性症の分類を再考する.Brain Nerve 68;1453-7, 2016