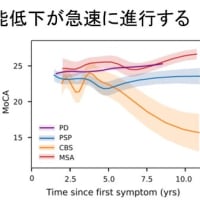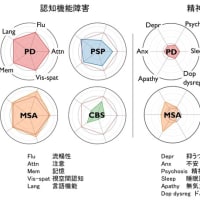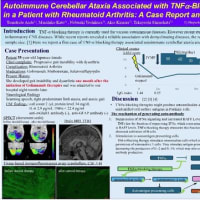新潟大学では,多系統萎縮症(MSA)における突然死の問題に2001年より取り組み,その機序や予防について多くのことを明らかにしてきた.しかし最終的にたどり着いたのは臨床倫理的な問題であり,そのなかでも「いつ,どのように患者さんに突然死のリスクを伝えるか?」はとくに難しい問題である.患者さんの知る権利は尊重すべきものであるが,突然死に対する不安は,患者さんに大きなマイナスの影響を与えることは容易に想像がつく.この問題を議論するために,「てんかん患者に起きる予期せぬ突然死(Sudden unexpected death in eplepsy;SUDEP)」に対する病状説明の現状を理解することは役に立つ可能性がある.
まずSUDEPは,てんかん患者さんに起きた,死因を特定できない突然死を指す.発生率は1,000人・年当たり0.9~2.3件で,一般人口における突然死の20倍以上である.危険因子としては,全般性強直間代発作の発生頻度が高いことが重要で,そのほか,男性,若い発症年齢,長い罹病期間,抗てんかん薬の多剤療法が知られている.てんかんにおける突然死のリスクを,患者さんや家族は知りたがっているのか,また医師はどのように伝えるべきかという問題を検討した論文を3つみつけるけることができたのでご紹介したい.
(文献1)Brodie MJ, Holmes GL. Should all patients be told about sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)? Pros and Cons. Epilepsia 2008;49 (Suppl 9):99–101.
症例報告を元にした問題提起の論文.SUDEPの危険性は知らせるべきであるが,その危険性は症例ごとに異なること,かつ適切な治療介入が行われた場合,その頻度は極めて稀であることから,必ずしも全例に伝える必要はなく,とくに危険因子を有する患者さんを対象とすべきではないかという考えを2名の著者が議論している.とくに患者さんの年齢,病歴,教育レベル,性格を考慮して,個々の症例ごとに判断すべきと指摘している.
(文献2)Gayatri NA, Morrall MC, Jain V, et al. Parental and physician beliefs regarding the provision and content of written sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) information. Epilepsia. 2010;51(5):777-82.
SUDEPに関する情報提供について,小児神経内科医と両親にアンケートした論文.74%の医師は一部の症例にのみ情報提供を行い,その告知の及ぼす影響についてはよく分からない状況であった.逆に両親の91%は医師にSUDEPの情報提供を希望し,その情報は短期的・長期的にマイナスの影響を与えるものではなかった.対面による説明を行った後,説明資料を手渡すことが良いと述べている.
(文献3)RamachandranNair R, Jack SM, Strohm S. SUDEP: To discuss or not? Recommendations from bereaved relatives. Epilepsy Behav. 2016;56:20–25.
SUDEPで身内をなくした27名の遺族に対して行ったインタビューの結果から,突然死のリスクをどのように伝えるべきか議論した論文.遺族は,突然死の情報(頻度,危険因子,予防法)を患者本人に説明すべきという希望を持っていること,医師は突然死の危険性について,個々の症例の感情や認知機能を考慮のうえ,最適な時期と状況を選んで伝えるべきと述べている.
以上より,SUDEPでは,多くの患者さん・家族は突然死のリスクを知りたいと考えていること,医師はその危険因子や患者さんの状況を考えて,個々の症例ごとに適切に判断する必要があることが論じられている.MSAにおけるこのような調査は知る限りにおいてないが,おそらくあまり説明はなされていないのではないだろうか.個人的には,患者さんや家族が突然死の危険性をどの程度知りたいかを明らかにすること,個々の症例ごとに,突然死の危険性を判断し,最適な時期・方法で説明を行うことが必要であるように思う.MSAでの突然死は,自律神経症状が高度であることや,声帯開大不全が高度であることが報告されているが,突然死のリスクをより正確に予見する症候の同定も必要である.
まずSUDEPは,てんかん患者さんに起きた,死因を特定できない突然死を指す.発生率は1,000人・年当たり0.9~2.3件で,一般人口における突然死の20倍以上である.危険因子としては,全般性強直間代発作の発生頻度が高いことが重要で,そのほか,男性,若い発症年齢,長い罹病期間,抗てんかん薬の多剤療法が知られている.てんかんにおける突然死のリスクを,患者さんや家族は知りたがっているのか,また医師はどのように伝えるべきかという問題を検討した論文を3つみつけるけることができたのでご紹介したい.
(文献1)Brodie MJ, Holmes GL. Should all patients be told about sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)? Pros and Cons. Epilepsia 2008;49 (Suppl 9):99–101.
症例報告を元にした問題提起の論文.SUDEPの危険性は知らせるべきであるが,その危険性は症例ごとに異なること,かつ適切な治療介入が行われた場合,その頻度は極めて稀であることから,必ずしも全例に伝える必要はなく,とくに危険因子を有する患者さんを対象とすべきではないかという考えを2名の著者が議論している.とくに患者さんの年齢,病歴,教育レベル,性格を考慮して,個々の症例ごとに判断すべきと指摘している.
(文献2)Gayatri NA, Morrall MC, Jain V, et al. Parental and physician beliefs regarding the provision and content of written sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) information. Epilepsia. 2010;51(5):777-82.
SUDEPに関する情報提供について,小児神経内科医と両親にアンケートした論文.74%の医師は一部の症例にのみ情報提供を行い,その告知の及ぼす影響についてはよく分からない状況であった.逆に両親の91%は医師にSUDEPの情報提供を希望し,その情報は短期的・長期的にマイナスの影響を与えるものではなかった.対面による説明を行った後,説明資料を手渡すことが良いと述べている.
(文献3)RamachandranNair R, Jack SM, Strohm S. SUDEP: To discuss or not? Recommendations from bereaved relatives. Epilepsy Behav. 2016;56:20–25.
SUDEPで身内をなくした27名の遺族に対して行ったインタビューの結果から,突然死のリスクをどのように伝えるべきか議論した論文.遺族は,突然死の情報(頻度,危険因子,予防法)を患者本人に説明すべきという希望を持っていること,医師は突然死の危険性について,個々の症例の感情や認知機能を考慮のうえ,最適な時期と状況を選んで伝えるべきと述べている.
以上より,SUDEPでは,多くの患者さん・家族は突然死のリスクを知りたいと考えていること,医師はその危険因子や患者さんの状況を考えて,個々の症例ごとに適切に判断する必要があることが論じられている.MSAにおけるこのような調査は知る限りにおいてないが,おそらくあまり説明はなされていないのではないだろうか.個人的には,患者さんや家族が突然死の危険性をどの程度知りたいかを明らかにすること,個々の症例ごとに,突然死の危険性を判断し,最適な時期・方法で説明を行うことが必要であるように思う.MSAでの突然死は,自律神経症状が高度であることや,声帯開大不全が高度であることが報告されているが,突然死のリスクをより正確に予見する症候の同定も必要である.