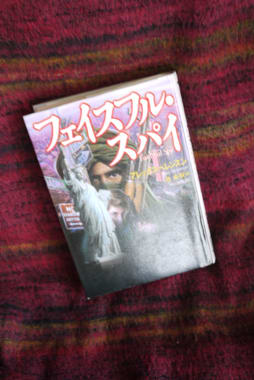先週末に、二つの建築誌連載のゲラ修正をして送ったばかり、次の締め切りは云々と念を押される新春、でも戴いた年賀状を拝見してホッとし、好いお正月になったと思えた添え書きがある。
内田祥哉先生からの一言、「昨年はご苦労をおかけしました」。
「建築家模様」で内田先生のお話をお聞きして掲載、ゲラ修正を戴いたが確認の電話を差し上げた時にはご不在。FAXでお礼の一言をお送りしたがそれでよかったのかと気になっていたからだ。戴いた御本には筆でサインを戴いたが、賀状にはその味わい深い文字が万年筆で書かれている。
そして一緒に保存運動をした、東京女子大学の哲学者・森一郎教授が東北大学に転進される最講義を受講した昨日(1月17日)、久し振りに東女を訪れた。忙中閑あり。
ところが「閑あり」どころか、聴いたこともなかった「ホッブス」というデカルトと同時代の近代哲学者の存在に心打たれることになった。新年、それもまた良しだと開き直る。
この最終講義も、先生の教え子、可愛い!院生からの賀状の添え書きの「来ていただけると先生が喜んで下さる」という案内によるものだ。
社会活動を終焉するので賀状は今年限りにします、という添え書きのされた賀状がある。母校建築学科の1年先輩からだ。功あり名を遂げた人の、にこやかな風貌が浮かび上がり、それもありなんと思ったりする。
もう一通、賀状は今年限りにして下さいとの添え書き。数年前にも一度戴いたが、僕が数十年前に設計した建築のオーナーの奥様からだ。竣工後にご主人が亡くなり、その後その建築も人手に渡ったがお元気でお過ごしされてきたことは知っているものの、長い間お会いしていない。いつまでもお健やかにと一言申し上げたくなった。
同じように、東大病院に家族以外では僕だけがお見舞いを許されたご主人が本社竣工直後に亡くなり、お葬式の時にその建築の周辺を一緒に車で回って斎場に向かったその奥様からは、「つくっていただいた建築も25年を経ましたが丁寧に使い続けており、仕事も順調です」という涙がでそうな添え書きの賀状を戴いた。この小ぶりな建築は僕の代表作の一つである。
身が引き締まるのは、A・レーモンドの設計した東京女子大学の東寮と旧体育館の保存活動でご一緒し、2010年5月15日に日本記者クラブに於いて行った有識者の会による緊急記者会見でも同席・ご意見をいただいた、平野健一郎(早稲田大学名誉教授・東京大学名誉教授)先生からの賀状の添え書きである。
「日本社会がグラグラと崩れていくようです。新しい設計図が欲しいです」。
<写真 久し振りに訪れた東京女子大学>