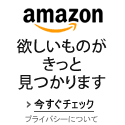今日は午後からリピーターさん教室。それまでの間にしながわ水族館ディスプレイ用作品を彫って9匹彫り終わったのね。更に夜間の部で切り抜いて、後はペーパー掛けとペンキ塗り。ではラインナップのご紹介。まずはフクロウナギ。

お次は世界で一番ブサイクとされるブロブフィッシュ。

更にクリオネが餌を食べる時に、恐ろしい変化をするんだけれど、それをバッカルコーンって言うのね。

お次は深海魚の中ではトップのメンダコ。

お次はオニイソメ。

お次はメンダコに負けない人気のダイオウグソクムシ。

そしてダンボオクトパス。

お次はデメニギス。

そして最後がミズウオ。

この間に来月分のデイ・サービスのサンプル。

白い部分をピンクにして、バレンタインなのね。そんなこんなでお教室。そうね、昨日とほぼ同じ話になるんだけれど、要するにもうタイルを切るって行為に大きく困る人では無くなった・・・そんな人がただ色を選んで張るってだけになると、モザイクって本当に詰まんないのね。
例えば、絵画だとする。ここはこんな色だよな・・・って事を、自分の感じる色を混ぜて作る。それが中々上手く作れなくて、それが技術なのね。所がモザイクってタイルの会社の作った色しか無いのね。つまり世界一の作家でも、素人でも、同じ色数を揃えたら一緒なのね。
勿論、絵の具だって同じ数を揃えれば一緒だけれど、混ぜて作れるから、技術は大きく変わって来る。当然、モザイクだって混ぜられないから、混ざったように見えるテクニックみたいな事はあるが、実際は本当に混ざっている訳じゃ無いのね。つまり、何々のように・・・って比喩的感覚な話。
例えば柔らかな布団って言うのを、まるで雲の上みたいな・・・とか、比喩を使って表現するみたいな感じにね。そうかと思うと、とろけるような舌触りとか、舌は溶けないよっ・・・。比喩だから。こうした感覚って言うのは、感じるって五感の話なのね。だから感じない人は全く用事無し。
つまり絵画なら混ぜないとならない意識を持たずに、無意識に混ぜて作ろうとするが、モザイクの場合、知れば知るほど、混ぜられないし、これしか色は無いって意識になる。つまりいくらタイルが切れても、そっくりにするには限界があるのね。だって混ぜられないのに色が無いから。
つまり色がここはある。ここは無い。じゃこれで良いや、ここはある。ここは無いからこれかぁ・・・って言う選択を、どんなに切る事が上手くなっても続ける事になるのね。面白いかな?こんな事をし続けて・・・。所が意識を、折角色が無いんじゃん。みんな条件一緒じゃんってなると、大きく
変わって来る。要するに折角無いのだから、いかに工夫をするか?なのね。その工夫こそが考えるって事に繋がって行くものなのね。つまり、どーする?って気持ちと、こう見えないかな?意識を持つって、意識に変化を持たないと、永遠に上手くはならないのね。
その五感を鍛えないと、食べちゃえば一緒だよ・・・とか、誰も見ていないからそんなカッコでも大丈夫とか、こんな感覚では感性や感受性は育たないのね。俺の場合は、その五感の美に関しては、知覚過敏のようにチクチク感じるのね。何か違う・・・ん・・・って感じにね。
そんな練習の初歩が、お風呂で何処から洗う?なんて質問なのね。まさかの2日連続になるとはね。所がこの話がとても大事な話になるのね。昨日の方は、顔から・・・って言ったのね。そこで何で?と聞くと、一番キレイにしたい所から・・・って言うのだけど、じゃ髪の毛洗って台無しだね。って
事になるから、自分の掲げた理由が、自分のする行為で台無しになる。所が今日の方も顔からって言うのね。じゃ何で?同じ質問に、化粧を真っ先に落としたいから・・・って。それなら大正解なのね。ちなみに昨日は男性、今日は女性なんだけれど、同じ顔からなのに、大きく違うのは、昨日は、
綺麗にしたいからと言って、また汚れてしまうって言う話と、人前に出る為の化粧を自宅でくつろぐ、服を脱ぐように顔を洗いたい・・・って言う比喩的感覚。つまり二度手間になったとしても、くつろぐ事を重視って言うのなら、趣旨がぶれていないから間違いが無いって話なのね。
こうした違いが説得力に繋がって行くのね。ほらここも力。リョクなのね。目に見えない力を養わないと、モザイクなんて単なる硬い切り絵。能力なんてもんで、目に見える能力は誰にでも判りやすいのね。それが学力、運動能力・・・点数やタイムと言った数字になるから、誰でも判りやすい。
しかし、洞察力、観察力、想像力・・・ここでの説得力。どれもこれも目に見えず、何が正解か?判りづらい。ただ今の話、どっちも顔なら、どっちも正解って言える?恐らく、きちんと向き合える人なら、恐らく同じ答えなのに、正解と不正解がある事に気が付くはずなのね。
これが判るようになると、感受性、感性に繋がって来るのね。何しろ同じ言葉なのに、違いが感じられるようになるのだから。つまり同じ言葉でも、誰が言ったか?どのシュチエーションなのか?どんな言い方だったか?強く言ったか?弱かったか?・・・ありとあらゆる想像が出来る。
これが出来ると、別にそっくりだけが仕上がりじゃ無くなる。つまり自分だけのオリジナルが作れるようになるものなのね。ただ、こんなくだらない事・・・って感じる人は、モザイクを習いに来たのに、くだらない話をしてモザイクを教えてくれない先生って事になるのね。あははは。
つまりその人は、先生katsuって言う人に習いたい人で、この方は永遠に次は何処をやれば良いんですか?と言い続ける人になるのね。つまり伝統芸能や古典落語、能や歌舞伎のようにね。でも別にくだらない話をしているつもりは無く、がっちり指導しているつもりなのね。
それを素直にとは行かないまでも、戸惑いながらも答えられるようになると、自分の考えを伝えようとする練習になるのね。ただつじつまが合わないと、容赦無く却下になるんだけれどね。そのやり取りが上手く行くようになると、自分がこう見せたいんだけれど、こう見えますか?の相談が出来るようになる。
そこに説得力ってものが養われるし、だからこそ、そう見えるよ・・・って確認をすれば、後はタイルをそのように切れば良いだけになる。では具体的にモザイク指導となると、オウムの頭の赤。赤なんて言うのは、タイルにはほぼ1つしか無い。それをこの幅で、こうしてって切ってしまうのね。
何故?簡単な理由なのね。それは切る事に余り困らなくなったからなのね。つまり幅を合わせる事が出来るようになったから。出来なきゃ拾って入れちゃうから。それをラッキーと呼んでね。そして入らないからアンラッキーになり、仕方無く切る。上手く切れないから、まっ良いか・・・。
これこそが人生になる。そもそも上手くなった人は拾っては入れない。全て切る事になる。それどころか、自分の切ったパーツが気に入らない事が多々ある。剥がしたい事もある。1枚1枚にこだわりがあるから。でも最初は進みたいだけ。終わらせたいだけ。だから手間を惜しむ。
つまりラッキーが沢山欲しくなる。でも仮にラッキーが合ったとしたら、逆を返せば、アンラッキーを生む事になるのね。そもそも上手くなった人は、拾わないからラッキーは無いのね。しかもラッキーが無いから、休めない。休まないから、上手くなる。上手くなるからアンラッキーを防げる。
でもラッキーな人は、ラッキーによって、1回サボったのね。つまり練習しなかった。だから練習をサボれば、次に入らなければ、アンラッキーが生まれる。当然の話なのね。つまり、それが人生であって、ラッキーって得すれば、ラッキーは続かないから、アンラッキーはやって来る。
所がコツコツとやる人は、ラッキーもアンラッキーも無く、どんな時もいつも通りなのね。それこそが上手くなったって人なのね。この説明を踏まえて、オウムの頭を意識の無い人は、岩石みたいなパーツを切ってしまうのね。迷わずに目地幅を揃えて・・・。それでオウムの頭に見えるかな?
もっと良く見て・・・オウムの頭ってどんな感じに見える?・・・言葉を捨てて両手で表現して見て。えっ?って大抵の人はそうなる。そもそも初めての人に丸を切って・・・って言うと、ヘタッピだったりする。当たり前だよね、初めてなんだから。じゃ大正解。でもね、先生ぃぃ丸って何ですか?
って質問された事は無いのね。何故?・・・それは初めてじゃ無いから知っているんだよね。そうつまり丸の意識は全員持っていて、ニッパーの使い方がぶきっちょなだけなのね。つまり道具の使い方だけ教えれば良いのね。じゃ道具を使ってタイルを切れるようになった人への指導は?
意識を持て・・・って話でしょ?つまり赤いタイルを切るな・・・なのね。赤いタイルをどうやって切って、オウムの頭に見せる?って言う話で、それが判れば切れるって話。つまりどう切れば頭に見えるか?考えないと・・・。それを考える練習に付き合うのがオリジナル作りの先生なのね。
例えば岩石の様なパーツだとする。いわゆるクラッシュ。目地幅も均等なら凄く綺麗だと思う。さっきは目の前で表現して貰う為に、口禁止にしたんだけど、ここで言葉禁止にすると、何も伝わらないから、画像無しで言葉のみ表現にすると、岩石のようなパーツはどんなに綺麗に張ってもゴツゴツ。
何せ岩石なのだから。でももしオウムの頭だから・・・ときちんと写真を見たら?フサフサって見えないかな?だとしたら、ゴツゴツじゃ無いよね。だからフサフサに見えるパーツを考えれば良いのね。ただね、俺ごときに言われるとイラッと来る人もいるでしょ?だったら、一流の人を使うかぁ。
じゃ映画も始まるし、中島みゆきさんの銀の龍の背に乗ってって歌を聴いて見て。まずは己の無能さを恥じる状況の歌詞に合う音は何?何か悲壮感とか、どんよりとか、絶望とか、がっかりとか・・・なんでも良いけれど、そう言ったニュアンスを感じる事が出来る音を探すんだろうね。きっと。
所が夢が・・・と始まる小節になると、一転転調になる。何故?そこからの歌詞が、夢が迎えに来てくれるまで、震えて待っているだけの昨日・・・つまり僕は変わる・・・って言う状況になったからなのね。例えば、これが運動会くらいの話ならこんなに壮大なスケールの音の厚みは要らない。
しかし命を預かるお医者さんの話。人の生き死にが掛かっている。そりゃ転調の仕方も、音の壮大さを表すスケール感も欲しくなる。つまりこうしたきちんとした理由を持って作られているものなのね。それを運動会で子供が頑張る姿を表現するのに、あんなに壮大さは鬱陶しい。
もっと可愛いタッチで・・・みたいになる。じゃこのオウムは?そうやってオリジナルを作るって話なのね。最悪でしょ?必要無い人には、こんな教室嫌でしょ?俺もそう思うね。ただ必要な人には必要らしいのね。お陰様でね。勿論、必要な人がいつ来ても良いように、いつも準備はしているけれどね。