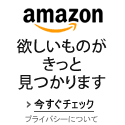今日は午後から外用流しのリピータ―さん教室。それまでは昨日の見積もりの続き・・・何しろ形が複雑だったんで、この位掛かるのかな?・・・みたいな事を考えて見たり、やり方とか・・・それによって掛かる時間も大きく変わるだろうし・・
そんなこんなで午前中はそんな感じでおしまい・・・そんなこんなのリピータ―さん教室。まずは牛の絵馬の目地から。

右の水色が俺のサンプルなんだけれど、自宅で張って来たのだけれど、とても良く見ているなぁ・・・って話があって、俺の足の付け根なんだけれど、リピータ―さんは、俺の付け根の色違いにした所が、何処までがお腹で何処が足なのか?
って・・・そこを踏まえてしっかりお腹と足を区切って来たのね。同じ下地なのに全く表情も違うし、昨日のデイ・サービスもそうなんだけれど、眼の位置1つでいくらでも表情を変える事が出来るって事が見られたんだけれど、今日は更に
その上を行く切る事に関して、この作品の中ではどちらが俺のか?言わないと判らない位、上手くなっていて、更にそんな細かい事まで意識すれば、当然結果も付いて来るって話で・・・この下地の面白さを理解して貰ったようで何より。
そう言う意味では、流しの場合、デザインを決めたらそれをきちんと目地幅を揃えて均等に張る・・・つまり配列のオリジナル性はあるけれど、張る事に関しては個性は出しずらいのね。しかもきちんと目地幅を揃えて均等にすればするほど
きちんとするのだけれど、そこまで行くと、上手い所で誰がやっても揃う事になるのね。所が目地幅が安定しなかったり、ずれたりすると、折角のデザインも台無しになる。ただデザインと言っても、配列の話だからそれ程大きく悩む事では無いと思うのね。
比較をすればすぐ判るけれど、これからシンクの中に鯉を描く事になるのだけれど、絵を作るって言うのは、鯉に見える?・・・って事になるのね。配列は出来ない事は無いけれど、鯉に見えるモザイクを作るって言うのは、鯉の絵が必要。
ここをリピータ―さんは絵葉書の絵を使うみたいなんで、後は見える様に切るって技術の問題になって来るのね。これを完全オリジナルとするのなら、自分で鯉の絵を描く事になるのね。つまり絵を描く事と配列の場合と比較すれば、
どれだけ難易度が増すか判って頂けると思うのね。そう考えると、下絵を描かない事を選んだので、牛の下地と考え方は一緒で、下絵を描かない事で後は切る・・・って事になると、タイルの厚みの難易度は上がるけれど、大体の仕上がりは
想像出来るので、相当期待出来るのね。そんなこんな後は、鬼滅の刃の主人公の炭治郎のモザイク。

段々と判って貰える形になって来た・・・。