鼻だけで呼吸し、深呼吸の要領で大きく息を吸い、出来るだけ長くゆっくりと吐き、吐く息を体の中へ吐き、下腹の臍下丹田(どこにあるかは分からないとは思いますが)へ向けて吐きます。
吸った息が、喉から気管支を通って、胸を通り下腹の臍下丹田に入って行くのを追うようにして、そのことだけに意識を集中します。
吐く息は、全て吐き切るつもりで吐きます。 全て吐き切ってしまうと、苦しくなって後が続きません。 したがって、全て吐き切る寸前に軽く息を止め、また大きく息を吸います。
無理をしながらも、あくまでも吸う、吐くのリズムは、自然の流れが大切なのです。 数ある呼吸法の中には、途中で息を止めるやり方もありますが、ここでは自然である(無理はしますが)ということが大切です。
自然の流れに任せ、自然の摂理に従うという考え方が、とても大切であると思うからです。
上記の呼吸法は、我流の逆腹式呼吸です。 一般的な逆腹式呼吸はいわゆる禅宗の腹式呼吸が前提になっていて、その逆の呼吸法ということで、逆腹式呼吸と呼ばれています。 ここでの逆腹式呼吸は、肺の生理と臍下丹田の生理は同期しないという考え方から成っています。
肺で息を吸う時には、臍下丹田では気を吐きます。 肺で息を吐く時には、臍下丹田では気を吸うのです。 これが人間の体の生理であると感じるからです。
一般的な腹式呼吸(禅宗)では、はじめに肺からと臍下丹田からと、同時に吐き出すことから始めます。 禅宗での空の理念は、立派な考え方だとは思ってはいるのですが、残念ながら人間の体の生理には、合ってはいないと思っています。
ここでの逆腹式呼吸を続けていくと、生来、眠っていた経絡(気の通る道)を刺激し、その通りを良くしていきます。 経絡は神経の腺に沿って流れていると云われていて、経絡の通りが良くなることによって、神経も刺激していきます。
特に微細な神経細胞がある脳を、顕著な形で刺激していきます。 この逆腹式呼吸を、肩の力を抜いて胡坐を組み、上半身を頭のてっぺんから引っ張られているような感じで維持します。 姿勢を良くしようとして胸を反らすと、筋力が働きますのでよくはありません。
逆腹式呼吸を行いながら1時間毎日、座禅を行っていけば、何かを感じてくるはずです。 私自身は、微妙な体の変化を楽しみながら、毎日、深夜に1時間の座禅を行っています。 楽しいから続くのかも知れません。 30分ではなく1時間続けることが、とても大切なことなのです。










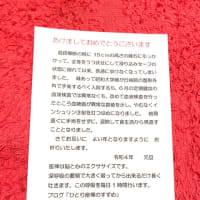

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます