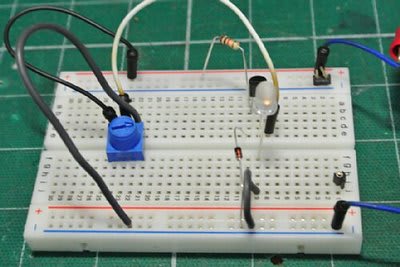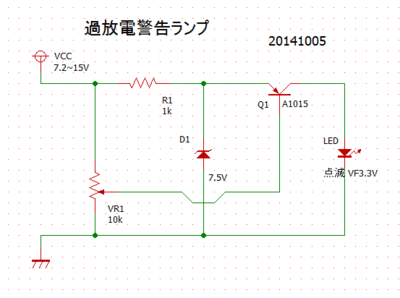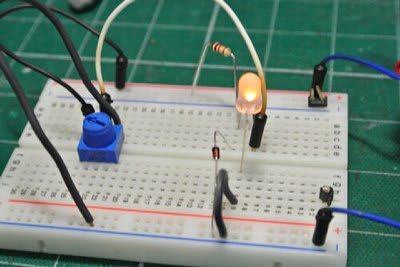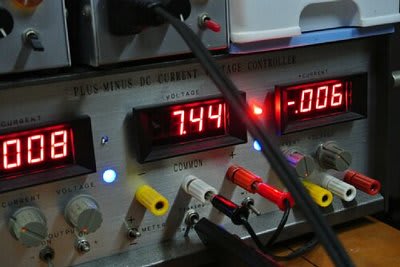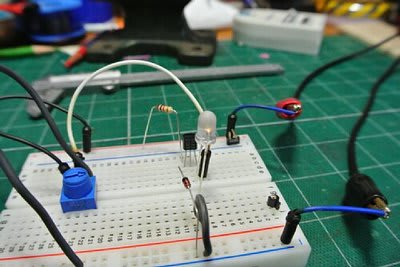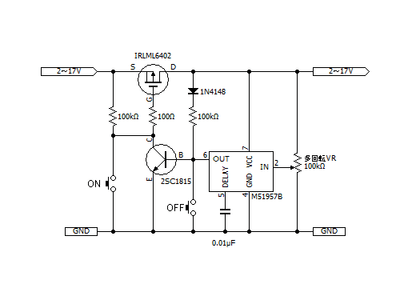組み立て完了。コアキシャルですので,ネットワークの工作はなしです。
この間いろいろトラブルがありました。
まず,,,

この養生のテープの下ですが,,やはり・・・・

細かな割れ目がありましたので,そこを伝わって黒がバッフルににじんでしまいました。
さて,どうするか・・・・①バッフルもみんな黒く塗ってしまう。②にじんだところをえぐる。
ずっと悩んでました。
で,結論は,板の厚みが21mm強あるので,3mm程度の溝を掘っても強度には影響ないであろうと考え,

こんなものと

こんなものを取り出して,,,6mmのビットで3mmの溝を掘りました。
雪がまだ残る寒い庭先で,,ウィ~ン!
トリマーの音が懐かしい! でも,木くずを全身に浴びてしまいました,,,

結構バリが出ます。
溝のところのニスがけが必要なので,バッフル全体にサンダーをかけて,もう一度ウレタンニスを塗りました。


結構ツルツルにできましたね。


ターミナルの処理をして,ポリエステル・ウールを入れて,,,
ところが,またトラブル。スピーカーユニットを取り付けようとしたら,ネジ受けに爪付きナットで固定するはずだったんですが,木が古いせいか空回りはじめて,今度は抜けない。締めもできず,緩めもできず・・・難儀しました。結局,ステンレスのボルトを金引き鋸でカットするという荒療治。こういうところはけちけちしないで,鬼目ナットを使うべきですね。2カ所に,鬼毛ナットを突っ込んで,やっと試聴できる状態までこぎ着けました。


これで草臥れて,今日はお仕舞い。
とりあえず測定はしないで,楽音を聞いて見ました。まあ,バランスは悪くないです。ただ,バスレフダクトからもっと激しく空気が出入りするかなと思ったんですが,あまり風圧を感じない。心配していたとおり,ダクトの径がちょっと細すぎた嫌いがあります。
測定後,対策は検討します。ただ,測定では意外と良かったりして,,,