
先月図書館でこんな本を見つけた。
第4巻ということはすでに3巻は発刊済みなのだろうがそれについては知らない。
今回見つけた第4巻は主として明治4年(1871年)の廃藩置県から昭和62年(1987年)の市制施行までの期間が対象になっている。
目次を見ると
一、幕末・維新期の狭山
二、村の状況と生活
三、小学校の設置
四、高野鉄道の開通
・
・
・
など近現代について860ページに及ぶ記述、資料が示されている。
飛ばし飛ばしではあるが興味のあるところを読んだ。
その中の一つ、現在の大阪狭山市に至るまでの合併併合の流れを見ると、
明治の初め狭山には池尻村・半田村・東野村・今熊村・岩室村・山本新田・茱茰木新田・西山新田・大野新田など9ツの村があった。
明治22年市制・町村制の施行により9ツの村が狭山村と三都村2ケ村に統合され丹南郡に属し、明治29年に南河内郡となった、とある。
その後昭和6年(1931年)狭山村と三都村合併により狭山村になり、昭和26年(1951年)町制施行による狭山町、昭和62年(1987年)大阪狭山市の誕生となりました。

戦後吉田内閣が「弱小町村の解消」「行政制度の合理化」を進めるべく、昭和28年(1953年)3年間の時限立法として町村合併促進法が成立、「昭和の大合併」が全国各地で進められた。
狭山町で検討されていた合併案は、上の図にある南河内郡の9カ町村(狭山町、登美丘町、平尾村、黒山村、丹南村、丹比村、日置荘町、南八下村、北八下村)が合併し市か町を作る構想であった。
狭山町はこの案を積極的に進めたが市庁舎の設置場所(狭山は北野田付近を挙げていた)で合意できず、南北に長い狭山では南端の大野地区が隣接する河内長野との合併を希望し、狭山町の望む合併案は、市域を東西に拡げるべく生徒を狭山町内の小中学校に通学させている富田林市の山西地区、泉が丘町との合併を希望していたそうだ。
その後登美丘町、日置荘町は堺市に編入、黒山村、平尾村、丹南が合併して美原町となり、平成の大合併で堺市と合併した。
狭山町内部の分裂を避けるため合併は進まず、9カ町村の中で狭山町以外は全て堺市域になってしまった。
この合併に際して狭山町は「将来堺市が泉が丘町まで伸びる場合には堺市に編入を希望します」と返答していたそうだ。













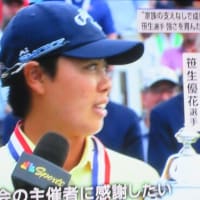



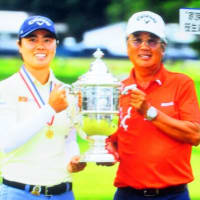

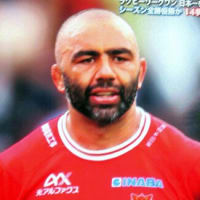





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます