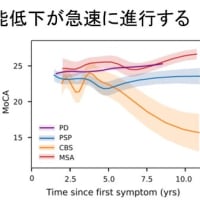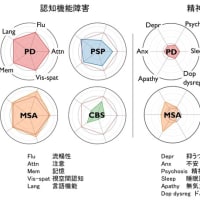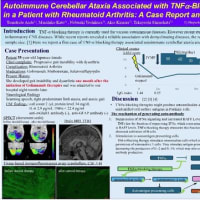感染性心内膜炎(IE)は,弁膜や心内膜に細菌などの病原微生物を含む疣腫が形成され,心臓弁膜症やうっ血性心不全のほか,塞栓症や感染性脳動脈瘤破裂による中枢神経合併症をきたす.IEに伴う脳塞栓症に対するtPAによる血栓溶解療法は,「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法適正治療指針第二版」によると「慎重投与」になっている.指針内にはこの判断の基準についての記載はないが,脳出血合併の危険性が高くなるためと考えられる.しかし既報の症例集積研究を見ると,IEに伴う脳塞栓症に対する血栓溶解療法の是非については必ずしも意見が一定していない.
今回,フランスからの症例報告で,発症3時間以内にtPA療法を行った後に,症候性の多発脳出血を合併した症例の報告があったので紹介したい.この症例は,発症前2ヶ月間の食欲低下と体重減少を認めていた68才男性で,突然の右片麻痺と失語症を呈した.NIHSSは12点で,発熱はなく,心雑音もなし.心電図は洞調律で不整脈なし.頭部MRIでは左中大脳動脈領域のDWI高信号と,1.5テスラ-MRAにおけるM2での閉塞を認めた.T2*でのmicrobleedsは認めなかった.発症135分後にtPA静注(0.9 mg/kg)が行われたが,翌日,神経症状の増悪がみられ(NIHSS=22),CT上,多発脳出血を認めた.CRPが76 mg/lと上昇し,心エコーを行ったところ,M弁に疣腫を2つ認めたためIEと診断し,抗生剤を開始した.発症後行った3テスラ-MRAと血管造影では感染性動脈瘤を認め,閉塞していたM2は再開通していた.
この症例報告から分かることは以下の2点である.
1) tPAを使用するかどうかの判断を行う超急性期におけるIEの診断は難しい
この症例ではIEを疑う発熱,心雑音,T2*でのmicrobleedsが見られなかった.感染性動脈瘤の発見も1.5T-MRAでは難しく,今も,血管造影が診断のgold standardであるといえる.
2) IEに伴う脳塞栓症は症候性の脳出血を合併しうる
この論文では既報として,5論文7例についてレビューしている.7例のうち脳出血合併は3例,症候性脳出血合併は0例である(ただし1例は詳細不明).つまりこの症例報告が,症状の増悪をきたした症候性脳出血としては初めての報告となる.また出血合併の機序として,血管壁のびらんを伴う感染性血管炎や感染性動脈瘤の破裂などの関与を挙げている.
IEに伴う脳塞栓症に対しtPAを行うべきかの判断はなおエビデンスが乏しいが,今回のような症例が存在することを認識する必要がある.
J Neurol 260;1339-1342, 2013
今回,フランスからの症例報告で,発症3時間以内にtPA療法を行った後に,症候性の多発脳出血を合併した症例の報告があったので紹介したい.この症例は,発症前2ヶ月間の食欲低下と体重減少を認めていた68才男性で,突然の右片麻痺と失語症を呈した.NIHSSは12点で,発熱はなく,心雑音もなし.心電図は洞調律で不整脈なし.頭部MRIでは左中大脳動脈領域のDWI高信号と,1.5テスラ-MRAにおけるM2での閉塞を認めた.T2*でのmicrobleedsは認めなかった.発症135分後にtPA静注(0.9 mg/kg)が行われたが,翌日,神経症状の増悪がみられ(NIHSS=22),CT上,多発脳出血を認めた.CRPが76 mg/lと上昇し,心エコーを行ったところ,M弁に疣腫を2つ認めたためIEと診断し,抗生剤を開始した.発症後行った3テスラ-MRAと血管造影では感染性動脈瘤を認め,閉塞していたM2は再開通していた.
この症例報告から分かることは以下の2点である.
1) tPAを使用するかどうかの判断を行う超急性期におけるIEの診断は難しい
この症例ではIEを疑う発熱,心雑音,T2*でのmicrobleedsが見られなかった.感染性動脈瘤の発見も1.5T-MRAでは難しく,今も,血管造影が診断のgold standardであるといえる.
2) IEに伴う脳塞栓症は症候性の脳出血を合併しうる
この論文では既報として,5論文7例についてレビューしている.7例のうち脳出血合併は3例,症候性脳出血合併は0例である(ただし1例は詳細不明).つまりこの症例報告が,症状の増悪をきたした症候性脳出血としては初めての報告となる.また出血合併の機序として,血管壁のびらんを伴う感染性血管炎や感染性動脈瘤の破裂などの関与を挙げている.
IEに伴う脳塞栓症に対しtPAを行うべきかの判断はなおエビデンスが乏しいが,今回のような症例が存在することを認識する必要がある.
J Neurol 260;1339-1342, 2013