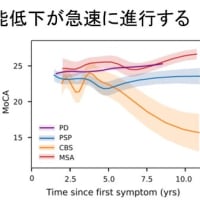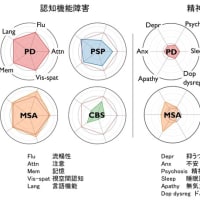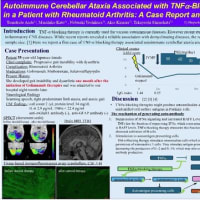第35回日本死の臨床研究会「いのちの支え ―生と死,その苦悩と癒し―」@幕張に初めて参加した.どうしてそのような学会に?と我ながら思うのだが,最近,病棟でがん患者さんの神経障害を診療する機会がいくつかあり,思うことが多かったことや,ブログにも記載したプリオン病の病状告知の問題,ALS患者さんの臓器移植と死の選択の論文などがきっかけかもしれない.加えて柳田邦男さんの集大成「僕は9歳のときから死と向きあってきた 」を読んだ影響も大きかった(そのなかでこの学会についても知った).死を考えるということは自身の残りの人生のあり方(=生き方)を考えることにほかならないと思っているが,多くの人の話を聞いてみたいという気持ちを持っていた.
」を読んだ影響も大きかった(そのなかでこの学会についても知った).死を考えるということは自身の残りの人生のあり方(=生き方)を考えることにほかならないと思っているが,多くの人の話を聞いてみたいという気持ちを持っていた.
さて,そうは言うものの学会に参加したのは目当てがある.柳田邦男先生,鳥越俊太郎先生,清水哲郎先生のご講演と,そして日野原重明先生!!最近,出版された「日野原重明 一〇〇歳 」を読んでいたので分かっていたつもりであったが,あまりのエネルギーあふれるご講演に驚いてしまった.講演前,演題脇にちょこんと腰をかけておられたが,座長に紹介されるやいなや,すたすた登壇し,演題の中央で両手を高々と掲げてガッツポーズ・拍手の嵐!ご講演が始まると演壇を所狭しと動きまわる.ユーモアにあふれる話術に感嘆!Steve Jobsのプレゼン術関係の本は結構読んだが,負けず劣らず日野原先生のプレゼン術からも学ぶことが多々ありそう.とにかく人を惹きつける.90分をまったく長く感じなかった.さてご講演の中で心に残った言葉を列挙する.
」を読んでいたので分かっていたつもりであったが,あまりのエネルギーあふれるご講演に驚いてしまった.講演前,演題脇にちょこんと腰をかけておられたが,座長に紹介されるやいなや,すたすた登壇し,演題の中央で両手を高々と掲げてガッツポーズ・拍手の嵐!ご講演が始まると演壇を所狭しと動きまわる.ユーモアにあふれる話術に感嘆!Steve Jobsのプレゼン術関係の本は結構読んだが,負けず劣らず日野原先生のプレゼン術からも学ぶことが多々ありそう.とにかく人を惹きつける.90分をまったく長く感じなかった.さてご講演の中で心に残った言葉を列挙する.
こころの言葉が生きていなければならない.そのためには医療者は死なない程度の病気になったほうが良い.病むということはどういうことか分かる.
東日本大震災の津波,間違った情報は命に直結することを示した.われわれは命を失う事件にいつでも直面しうる.つまり「死の刻印」を押されたのが人間.自分の命にいつどんなことがあるか分からない.人間は寿命のある有限の生き物であり,朽ちるもの,朽ちる種として生まれた.
生きていることは生かされていること.これを理解しているのは人間以外にない.与えられて生きている.途中いろいろなことがあっても,命を与えられたことに感謝をできて,人生を終えることが出来れば「終わりよければすべてよし」と思う.
年をとるとシワができるが,笑顔のシワを作って欲しい.
子供たちが大きくなったら,自分の使える時間を人のために使えるようになるよう「命の授業」を行なっている.
日本人の平均寿命は伸び続けている.女性は長生き.夫婦同じ年に死にたいなら8歳年下の夫と結婚すれば良い(笑).
いのちとは,目には見えないが,人間に一番大切なもの.それは自分が持っている自分の時間.いのちも時間も見えないもの.その自分の時間をどう使うか,自分の命の使い方,人への命の使い方が大切.
いのちとケア.いのちには長さと質(深さ)がある.ケアにも冷たいケアと慈悲深いケアがある(dispassionateなケアvs compassionateなケア).Tender loving care(TLC)という言葉がある.テンダーとは愛を形容する最高の表現.その実現のためには自分に何ができるかまず考えること.ホスピスの最高のケアも同じTLC,being with the patients(患者と共にいる)という気持ちが大切.
医療はサイエンスに基づいたアート(技)である(オスラー先生).「理論・知識」「テクノロジー」「患者へのタッチ(技)」という三角形からできていて,とくに最後が大切.
いつくるかもしれない「いのちの喪失」に備えなければならない.日本はスペインについで自殺の多い国.戦争は人の命を奪うものであることを子供に対してよく教育する.「10歳の君へ」伝えたいことは「いのち,時,平和」の3つ.平和への道は,命を大切に思うこと,戦争を防ぐこと,核兵器ほか武装廃止の運動への出発(武器を持たない自衛隊)により達成できる.戦争にNOと言えるこどもを育てたい.
「寿命は神様から戴いた時間だ」.どういうふうに,いつ,だれのために使うかという権利を持っている.勇気ある行動を実践してほしい.
最後にみんなでハッピーバースデイを合唱した.なんとも穏やかな,暖かい気持ちになれるご講演だった.
さて,そうは言うものの学会に参加したのは目当てがある.柳田邦男先生,鳥越俊太郎先生,清水哲郎先生のご講演と,そして日野原重明先生!!最近,出版された「日野原重明 一〇〇歳
こころの言葉が生きていなければならない.そのためには医療者は死なない程度の病気になったほうが良い.病むということはどういうことか分かる.
東日本大震災の津波,間違った情報は命に直結することを示した.われわれは命を失う事件にいつでも直面しうる.つまり「死の刻印」を押されたのが人間.自分の命にいつどんなことがあるか分からない.人間は寿命のある有限の生き物であり,朽ちるもの,朽ちる種として生まれた.
生きていることは生かされていること.これを理解しているのは人間以外にない.与えられて生きている.途中いろいろなことがあっても,命を与えられたことに感謝をできて,人生を終えることが出来れば「終わりよければすべてよし」と思う.
年をとるとシワができるが,笑顔のシワを作って欲しい.
子供たちが大きくなったら,自分の使える時間を人のために使えるようになるよう「命の授業」を行なっている.
日本人の平均寿命は伸び続けている.女性は長生き.夫婦同じ年に死にたいなら8歳年下の夫と結婚すれば良い(笑).
いのちとは,目には見えないが,人間に一番大切なもの.それは自分が持っている自分の時間.いのちも時間も見えないもの.その自分の時間をどう使うか,自分の命の使い方,人への命の使い方が大切.
いのちとケア.いのちには長さと質(深さ)がある.ケアにも冷たいケアと慈悲深いケアがある(dispassionateなケアvs compassionateなケア).Tender loving care(TLC)という言葉がある.テンダーとは愛を形容する最高の表現.その実現のためには自分に何ができるかまず考えること.ホスピスの最高のケアも同じTLC,being with the patients(患者と共にいる)という気持ちが大切.
医療はサイエンスに基づいたアート(技)である(オスラー先生).「理論・知識」「テクノロジー」「患者へのタッチ(技)」という三角形からできていて,とくに最後が大切.
いつくるかもしれない「いのちの喪失」に備えなければならない.日本はスペインについで自殺の多い国.戦争は人の命を奪うものであることを子供に対してよく教育する.「10歳の君へ」伝えたいことは「いのち,時,平和」の3つ.平和への道は,命を大切に思うこと,戦争を防ぐこと,核兵器ほか武装廃止の運動への出発(武器を持たない自衛隊)により達成できる.戦争にNOと言えるこどもを育てたい.
「寿命は神様から戴いた時間だ」.どういうふうに,いつ,だれのために使うかという権利を持っている.勇気ある行動を実践してほしい.
最後にみんなでハッピーバースデイを合唱した.なんとも穏やかな,暖かい気持ちになれるご講演だった.