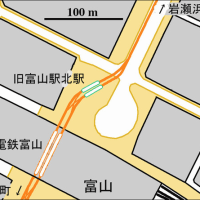1991年モンタナ州の訪問 その29
Visit to Montana for digging, 1991. Part 29
1991年7月9日ロスアンジェルス郡立自然史博物館のレプリカ作製場所で、ある標本の観察をお願いしている。

116 レプリカ作成中の鯨類頭骨 1991.7.9 Casting a skull of whale
この写真も、手順の説明のため出してみた。標本の表面で固化させたシリコンラバーとその外側で全体の形状を保持するガラス繊維強化プラスチック製の外型があることがよくわかる。上側(背側)にもこの両者をつくり、ボルトなどで締めつける。


117・118 型をはずす 1991.7.9 Remove outer case of the cast

119 出てきた実物 1991.7.9 Real specimen of Aetiocetus
不幸にして吻の一部が割れてしまったが、取り出すことに成功。この鯨(エティオケタス)が一番見たかった標本である。Aetiocetus cotylalveus のホロタイプで、1966年にD. Emlongが提唱した種類。現在「歯のあるヒゲ鯨」に含められているが、新種提唱の時点では原鯨類(Archaeoceti)に含められていた。それも当然で、1966年時点では分類上歯のあるヒゲ鯨という概念はなく、Zoological Recordでもそういう区分はなかった。その後Z.R.でも「所属不明」とされたりして扱いが転々としたものだ。現在ではヒゲ鯨の最も古い種類には歯があったことが概念的にも、実例としてもはっきりして、そのようなものを「歯のあるヒゲ鯨」(toothed mysticete)と位置づけている。記載論文はオレゴン大学の自然史博物館研究報告に掲載されたが、あまり日本では手に入らなかった。ネットが自由に使える時代ではなかったから、入手に苦労し、1985年8月に現・群馬のH先生の御好意でコピーを入手できたので、この旅行前に読んであった。「歯のあるヒゲ鯨」のうち、初期に報告された種類としては、これと南極セイムール島のヤノケタスの報告(Mitchell, 1989)が重要なのだが、どちらも比較的入手しにくいジャーナルに掲載された。ミッチェルの論文コピーは当時下関水産大学におられたNさんの御好意で、1999年になって入手した。
(つづく)
Visit to Montana for digging, 1991. Part 29
1991年7月9日ロスアンジェルス郡立自然史博物館のレプリカ作製場所で、ある標本の観察をお願いしている。

116 レプリカ作成中の鯨類頭骨 1991.7.9 Casting a skull of whale
この写真も、手順の説明のため出してみた。標本の表面で固化させたシリコンラバーとその外側で全体の形状を保持するガラス繊維強化プラスチック製の外型があることがよくわかる。上側(背側)にもこの両者をつくり、ボルトなどで締めつける。


117・118 型をはずす 1991.7.9 Remove outer case of the cast

119 出てきた実物 1991.7.9 Real specimen of Aetiocetus
不幸にして吻の一部が割れてしまったが、取り出すことに成功。この鯨(エティオケタス)が一番見たかった標本である。Aetiocetus cotylalveus のホロタイプで、1966年にD. Emlongが提唱した種類。現在「歯のあるヒゲ鯨」に含められているが、新種提唱の時点では原鯨類(Archaeoceti)に含められていた。それも当然で、1966年時点では分類上歯のあるヒゲ鯨という概念はなく、Zoological Recordでもそういう区分はなかった。その後Z.R.でも「所属不明」とされたりして扱いが転々としたものだ。現在ではヒゲ鯨の最も古い種類には歯があったことが概念的にも、実例としてもはっきりして、そのようなものを「歯のあるヒゲ鯨」(toothed mysticete)と位置づけている。記載論文はオレゴン大学の自然史博物館研究報告に掲載されたが、あまり日本では手に入らなかった。ネットが自由に使える時代ではなかったから、入手に苦労し、1985年8月に現・群馬のH先生の御好意でコピーを入手できたので、この旅行前に読んであった。「歯のあるヒゲ鯨」のうち、初期に報告された種類としては、これと南極セイムール島のヤノケタスの報告(Mitchell, 1989)が重要なのだが、どちらも比較的入手しにくいジャーナルに掲載された。ミッチェルの論文コピーは当時下関水産大学におられたNさんの御好意で、1999年になって入手した。
(つづく)