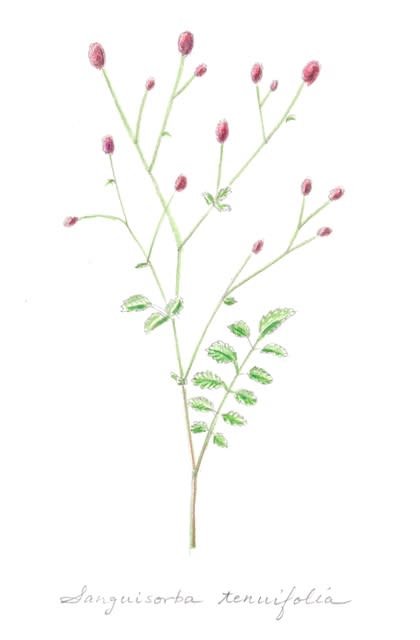11月22日まで9月の乙女高原を紹介していて、そのほかのことを挿入したのですが、挿入が長引いて月を越してしまいました。それで、乙女高原に戻ります。
調査というのは根気のいるもので、最初のうちは色々新しい発見もありますが、だんだんに同じようなことの繰り返しにうんざりしてくるものです。私はそういうことを長年して来たので身についていますが、そうでない人には辛いことだったのではないかと察します。でも、今回の皆さんはそういうそぶりは全くみせず、楽しく手伝ってもらいました。時々、名前の怪しい小さな草があったりすると、周りに同じものがないか探して、同じもののもう少し大きいのと見比べて確認したりしました。大いに助けられました。
こうして調査を終え、ロッジの前のテーブルでお茶にしました。いつもながら、植原先生がガスコンロとか、色々行き届いたものを出してくれます。アレコレと会話も弾みました。

シカが入らないようになって3年、間違いなく花々が戻って来ました。そのことをデータで記録しておくことが大切です。そのためにこうした地道な調査が必ず役に立つはずです。

調査というのは根気のいるもので、最初のうちは色々新しい発見もありますが、だんだんに同じようなことの繰り返しにうんざりしてくるものです。私はそういうことを長年して来たので身についていますが、そうでない人には辛いことだったのではないかと察します。でも、今回の皆さんはそういうそぶりは全くみせず、楽しく手伝ってもらいました。時々、名前の怪しい小さな草があったりすると、周りに同じものがないか探して、同じもののもう少し大きいのと見比べて確認したりしました。大いに助けられました。
こうして調査を終え、ロッジの前のテーブルでお茶にしました。いつもながら、植原先生がガスコンロとか、色々行き届いたものを出してくれます。アレコレと会話も弾みました。

シカが入らないようになって3年、間違いなく花々が戻って来ました。そのことをデータで記録しておくことが大切です。そのためにこうした地道な調査が必ず役に立つはずです。