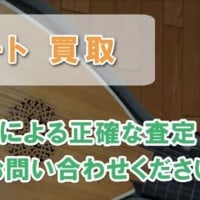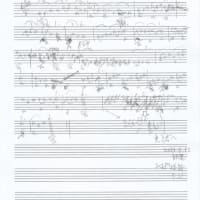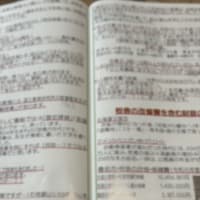このように現代のプロ達のバス弦の選択は多様であり、このことを裏返して言えば現在販売されているガット系のバス弦の性能に満足していないということです。もちろん昔ながらの金属巻き弦にも満足してはいません。バス弦の多様化はここがスタートですから。
プロは調弦が面倒だからガット系は使わないのではなく、性能に満足していないから使わないのです。もしシリーズ(1)(2)で挙げたどの選択よりも音が前にでるガット系のバス弦(おそらくヴァイスはそういうレベルの弦を使っていたでしょう)が登場したなら、少々調弦に手間がかかろうがどのプロもそれを使うはずです。
このようにバス弦の選択に関して現在は戦国時代のような様相を呈している時期です。こういった事実を踏まえて、弦の選択をしたいものです。ヴァイスの時代はガット弦だったからというだけで、そのへんで売っているガット弦を誰かのお薦めで張っている、というのは余りに素朴すぎる方法論です。現在入手可能な新作リュートやその弦の製作方法はヴァイスの時代からずっと続いているものではありません。実質的に約200年途絶え、1970年代から始まった古楽復興運動の始まりからせいぜい50年しか経っておらず、まだ発展途上であるという認識が必要です。