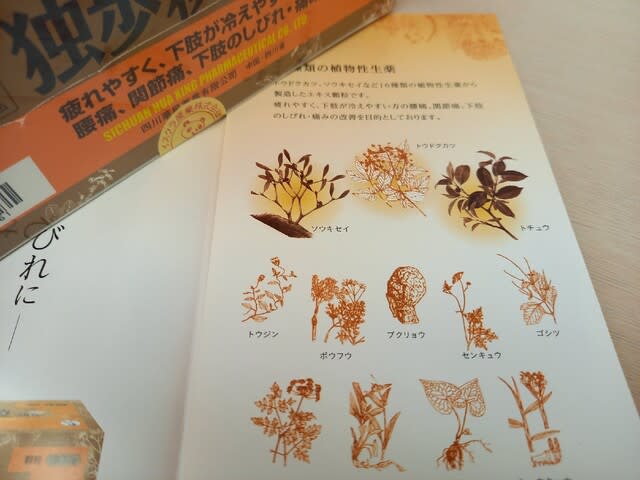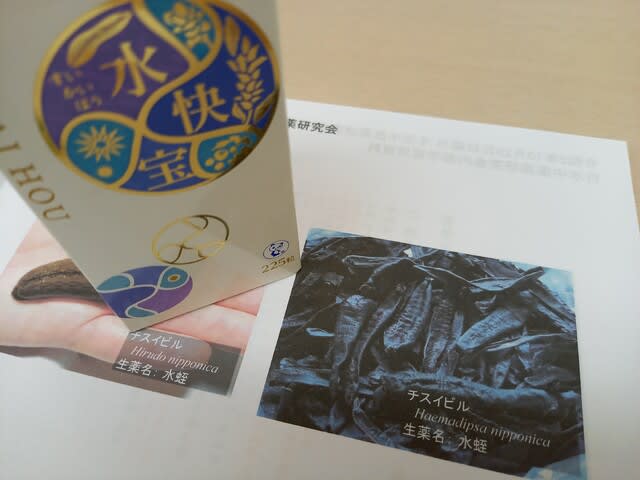米も生薬のひとつ。
意外な気がするかもしれませんが、素晴らしい薬効をもっているがゆえに「主食」なのです。
生薬名を「粳米(こうべい)」
火を通したものを食す
・脾胃と肺、つまりエネルギーを取り込む臓器(食べて呼吸する)を元気にする
・元気を増し、心を落ち着け、渇きを潤し、下痢を止める
・食欲減退、気持ちが落ち着かない、口が渇く、下痢しやすい、胎動不安、咳や喘息などによく
・長く食べれば、血を養い、骨髄が充実し、肌も張りが出る
おおよそ世界の主食になっている食べ物は、同じような働きをもっている。
人類は経験から理にかなった食物を主食として選んでいるのはすごいですね。
ちゃんとごはん食べなきゃね。

近所の田んぼも稲穂がたわわになり、今週末ごろから稲刈りが始まりそうです
 漢方家ファインエンドー薬局HP
漢方家ファインエンドー薬局HP 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいねクリックどうぞよろしく