今日はあちこちでgoogleのモーグシンセの話題で持ちきりです。私はシンセ好きなのですが、なにぶんにも自分ではまともなシンセを使ったことがないので、専門的なことは詳しくありません。なので限定的に考えてみましょう。何かというと、日本のアイドル歌謡でどのあたりからシンセが登場したかと。
調べてみるとミニモーグが製品化されたのが1970年ということですが、その時点では日本では持ってる人がいなかったような。で、アイドル歌謡の歴史を辿るってもあんまり範囲が広すぎて知るわきゃないでしょうということで、私がシングル盤の歴史をじっくり考えずともわかるアーティストのみを例にとってやります。というと、その時代は南沙織さんとキャンディーズだけなのですが(笑)
南沙織さんはデビューが1971年でデビュー曲はお馴染み「17才」。シングルをずっと思い浮かべてもシンセが使われてる曲がないなぁ…と思ったら、ついに思い当たったのが第15弾シングルの「想い出通り」。これのイントロはシンセではないかと思うのですがどうでしょう? 詳しい人がいたらどっかで探して聞いてみて下さい。
一方キャンディーズはというと1973年9月デビュー。どのあたりからシンセを使ってるかというと…なんかデビュー曲の「あなたに夢中」のイントロとか間奏とかシンセではないでしょうか? 間奏がわかりやすいですけど。ついでに第二弾シングルの「そよ風の口づけ」でもシンセ使われてるような…。これはどうでしょうか?
これらがシンセで、なおかつ時代から推察するにミニ・モーグであろうと考えると73年頃からたまに使われだしたと考えられます。で、上記の人たちとは別に思い浮かぶのが桜田淳子さんの「はじめての出来事」。これは1974年12月の発売ですが、私が聞くにシンセのように思います。さらにこの次のシングルの「ひとり歩き」という曲のイントロもシンセではないかと。これも興味のある人はどっかで探して聞いてみて下さい。
ということで知ってる曲だけでごく限定的にアイドル歌謡におけるシンセサイザーの役割を考えてみました。(って、そんなたいそうな…) 時代を考えると、レコードでシンセを使ったとしても歌番組では再現できず、当時のシンセは単音しか出ないので用途が限られ、なおかつレコーディングでもレンタル代が高かったりしたんじゃないかなぁとか想像しますが、その辺はよくわかりません。
ただ、国産シンセということではコルグの800DVというのが1974年に出てるんですね。なので上記の曲でもこっちが使われてるものがあるかもしれません。さらに70年代も後半になると普通にコルグのMS-10とか20とかが発売されてるし、オーバーハイムも4ボイスが出たりで一気にメジャーになりますので、考えてみたいのはあくまでも70年代前半までと。
さて今日のgoogleの画面で皆さん何を弾きましたか? オフコースの「眠れぬ夜」のイントロを弾いたという声もありましたが、私は尾崎亜美師匠の「気紛れ予報」のイントロを弾いてみました。実際はかなりダビングされてるので印象はちょっと違いますが「あ、これがモーグの音か」とか思うと結構嬉しかったりします。「パーフェクトゲーム」の方がそれっぽいかなぁ…。(と、さらに限定的な話)











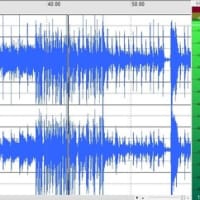

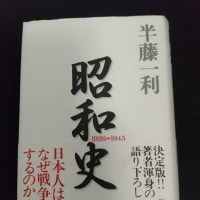

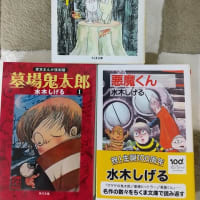




「ひなげしの花」(1972)と「妖精の詩」(1973)のイントロもそうじゃないですか?
ぴよんぴよんと可愛い音で、それが歌番組の時は管楽器の音になってしまいガッカリしたのを覚えています。
で、「妖精の詩」持ってないので某所で聞きました。こっちは微妙。これもオルガンとシロフォンをユニゾンで演奏してるようにも聞こえますが、音の切れ際がチュンとなってるのでシンセのような気もします。難しいですね。こっちは可能性あると思います。あとはオブリガートで入ってるリコーダーっぽい音もちょっと怪しいですし。
「ひなげしの花」は1972年11月の発売ですから、録音がその数ヶ月前と考えると日本でミニムーグを持ってたのはまだ富田勲先生だけだったかも…。
「妖精の詩」の頃にはその技術?も少し進歩(よりシンセっぽくなった?)したのかもしれませんね。
ちなみにアグネスチャンの曲ではこれが1番好きです。ドーナツ盤持ってますw。
で、私はアイドルは丸ぽちゃでちょっとセクシー系も入ってないとだめなので、アグネスはさっぱりヒットしませんでした。レコードももちろん持ってません。今も好きじゃないのですが、ポケット一杯の秘密くらいならなんとなくいい感じですけど。
アナログシンセの音こそがいわゆる「シンセっぽい音」ですもんねぇ。