横浜・関内の「横浜公園」内にある日本庭園
「彼我(ひが)庭園」
「彼我」は 外国人と日本人の双方が利用できるという意味で、古くから
そう呼ばれたようです。 いかにも 港町ヨコハマらしい呼称☆
雪見燈籠がある池周辺の紅葉が ちょうど見頃です。



穏やかな陽を受けて 思い思いに休日を楽しむ人たちの姿が。
(続)
三渓園
「本牧山頂公園」から もう少し足を伸ばして・・
暫くぶりの「三渓園」
明治末から大正時代にかけて製糸・生糸貿易で財を成した 横浜の実業家
原富太郎(号は三渓)が造りあげた 広さ約17,5haの日本庭園。 国指定名勝
各地から移築された 貴重な歴史的建築17棟が保存・展示されています。
これまで建物公開日を狙って何度か来ているけれど、今日は お花見がメイン
園内の桜が、かなり咲いてきています。(でも逆光・・・ )
)
一応 定番の撮影スポットから 

桜以外の花も探しながら、久しぶりに園内をぐるりと巡ってみましょうか。
「臨春閣」
紀州徳川家初代 徳川頼宣が紀ノ川沿いに建てた数寄屋風
書院造りの別荘建築。1649(慶安2)年 築 国重要文化財
シャガ スミレ

「天授院」
鎌倉・建長寺近く心平寺跡にあった 禅宗様の地蔵堂。
1651(慶安4)年 築 国重要文化財
「聴秋閣」
京都・二条城内にあったといわれる 徳川家光・春日局
ゆかりの楼閣建築。 1623(元和9)年 築 国重要文化財
カタクリ
ヤマブキ
アセビ トサミズキ

「蓮華院」
原 三渓の構想による茶室建築。
1917(大正6)年 築
ボケ
ショカツサイ レンギョウ

フキノトウ 
ツクシ アオキ

「旧燈明寺本堂」
京都・木津川市の燈明寺(廃寺)にあった建物。
1457(康正3)年 築 国重要文化財
「旧燈明寺三重塔」と薄墨桜
三重塔は、上記の本堂と同じ 旧燈明寺から1914(大正3)年 移築
現在 関東にある最古の木造の塔。 国重要文化財
薄墨桜は、原三溪が岐阜県出身という縁で 岐阜から移植したもので、
岐阜・旧根尾村(現在の本巣市)にある樹齢1500年以上といわれる桜の2世。
桜を訪ねて、今日はちょっと欲張って歩きました~
23,897歩 
着々と
「Garden Necklace YOKOHAMA 2017」
(第33回全国都市緑化よこはまフェア)まで あと一週間ほど。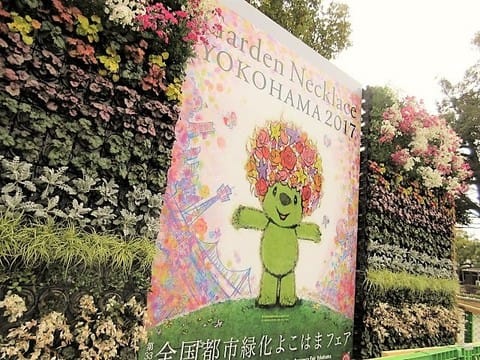
日本大通りや横浜公園でも、
着々と準備が進められています。






今人気のラナンキュラスも☆
花びらに光沢があるラックスシリーズ ‘ミノアン’

開催は、3月25日(土)~6月4日(日)
長~く楽しめそうですね。 楽しみ~
やっと青空が見えたので、港の景色を見に♪
「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」
2002(平成14)年に完成した 国内最大級の大型客船ターミナル。
接岸する船からの眺望を考慮して、地上2階・地下1階という
比較的低層構造の建物になっています。
店舗やカフェなどもあります。
「くじらのせなか」
屋上のフリースペースは、一般公募で選ばれたこの愛称で親しまれていて
港の眺望をぐるりと楽しめる 気持ちのいい場所になっています。
みなとみらい地区のビル群を背景に、白い船体。
JAPAN COAST GUARDの文字が見えます。
反対側は、氷川丸・山下公園・マリンタワー
先端まで行ってみると、

横浜ベイブリッジ・鶴見つばさ橋を一望。 ここでは1日に何隻もの
客船や輸送船が往来し、横浜港の賑わいを感じることができます。
(説明板の文章)
ふり返ると、こんな場所も☆
県庁(キング)・横浜税関(クイーン)・開港記念会館(ジャック)の
三塔を一度に見渡せるビューポイントのひとつ。
同時に三塔が見られるスポットは3箇所あるそうで、1日で
全ての場所をめぐると願いが叶うという伝説(?)があるとか。
花嫁さんの姿が見えます。 写真撮影でしょうか。
寒そう・・・あ、寒さなんて感じないんでしょうね(笑)
お幸せに
大さん橋の袂に ひっそりと・・
1894(明治27)年~1995(平成7)年の101年間
旧大さん橋を支えた螺旋杭が展示されています。
長さ21m 螺旋状円盤の直径1.8m 重量約6t
螺旋の形状を利用して、人力で海底にねじ込まれました。
(説明板より)
晴れていたと思ったら 急に暗くなったり、時々小雨がぱらついたり
定まらない天候で、撮った写真も 空の色がいろいろに・・・
遺跡公園内に、移築復元された古民家が公開されています。
丘陵の南裾にあった旧長沢家住宅は 18世紀中頃~後半に
建てられたもので、その主屋・馬屋を江戸時代の部材を
使用して建築当初の姿に復元しています。
かまど

水屋
主屋も馬屋も、いっぱいの雛飾りで華やいでいました。

大正時代の内裏雛
明治時代の内裏雛




展示は 3月6日まで
建物裏手に、みごとに花をつけた山茱萸☆
16,254歩 
横浜・都筑区港北ニュータウン内にある 弥生時代中期の遺跡。
この地域で稲作を始めた人々の集落(大塚遺跡)とその人達の墓地
(歳勝土遺跡)といわれ、ムラと墓が一体として分かる貴重な遺跡として
国の史跡に指定され その3分の1が公園として一般公開されています。
発掘当時の様子
(パネルより)
★大塚遺跡★
1972(昭和47)年の発掘調査で 85軒の竪穴式住居、10軒の高床式建物が
発見され、現在そのうちの住居7軒 高床倉庫1軒が復元展示されています。
ムラの外周600mに 幅4m・深さ2mほどの空堀を巡らし、外側に
築いた土塁の上に柵を設けて ムラを守っていました。(環壕)

稲作が広まり定住性が増すにつれて、他集落との
争いなども 増えていったのでしょうね。
住宅跡に特殊処理・加工を施し保存しています。
大型住宅
ムラの長(おさ)の住居で、集会にも使われました。
高床式倉庫
収穫物などを収めておく建物。 数軒の住居群が
1~2軒の倉庫を共有していたと考えられています。
ねずみ返し
★歳勝土(さいかちど)遺跡★
大塚遺跡から約80m離れた一帯から発見された方形周溝墓群で、
大塚遺跡の住人の墳墓と考えられています。 現在25基が確認
されていますが、未調査部分も含め 30基余かと推測されます。

住居と墓地を結んで墓道があり、方形周溝墓の間の隙間は 墓地内の通路と思われます。
(パネルより)
発見された墓のうち5基を復元しています。
墓の中央辺りにある四角い穴には、棺を納めた痕跡が確認されています。
復元されない方形周溝墓は、石でその位置を表示。
芝生の上で駆けまわる幼児や ボールを蹴り合って遊ぶ親子の姿
なども見られて、住宅地の中の公園といった雰囲気です。
「京急富岡」駅の西側出口から 道を隔てて
小さな流れに沿って 遊歩道が続いています。
(市HPより拝借)
「富岡川せせらぎ緑道」
もともとあった「富岡川」を暗渠化し、その上を遊歩道に。
緑道約1kmのうち、400mほどがせせらぎになっています。
上流の公園付近の湧水が、1日当たり数千㎥注ぎ込み
小さな水路ですが、水の流れは結構豊か☆

メダカや金魚、鯉も泳いでいたり・・
遊歩道沿いに草木が植えられていたり、花鉢が置かれてあったり
近隣にお住まいの方たちに 親しまれているのが感じられます。

小さな滝?もあったりして

せせらぎが途切れて 車道に出てきました。
左手に暫く行くと、「富岡西公園」があります。
長い階段を上って
高台からの眺め
9,953歩 
紅葉が見頃と聞いて、何年かぶりに 富岡にある
故川合玉堂画伯の別邸「二松庵」を訪ねました。
「京急富岡」駅からものの数分、坂を上って
紅葉がちょうど見頃です

茅葺の表門をくぐって 傾斜の小道を上っていくと・・
ガ、ガ~~ン!!
無いんです、茅葺のあの建物が・・・

3年前に 原因不明の火災で焼失してしまったんだそうです。
全然知らなかった・・・楽しみにして来たのに
ウェ~~~ン 
が、
庭園は 綺麗に整備されてありました。
紅葉を眺めながら、ぐるりとひと回りしてみましょう☆
画伯の指導の下、地元の庭師 植周2代目・大胡隆治氏が、斜面を活かし
作庭した野趣あふれる庭園は、この秋 横浜市の名勝に指定されました。


此処にあったあずまやから、 当時は海がよく見えたといいます。
沖行く船や房総の山々を眺めながら、画想を練られたのでしょうか。
でも、嗚呼・・
粋を凝らしたあの庵の建物が 無くなってしまったなんて
何て 勿体ないこと・・・ショックです 

(公開日をご確認のうえ お出かけください)
先月末、博物館講座「三浦半島の民族探訪」で「神楽」に関する講義がありました。
「神楽」とは・・
場を清め神霊を迎え、時には芸能を披露しながら鎮魂・飲食・神託を得て
神霊を送る神事。大まかに4つに分類され、複合して行われることもある。
「採物神楽」・・鈴・扇・榊・剣・弓などを持って舞う神楽。
出雲・佐陀神能が有名で「出雲系神楽」ともいう。
「湯立神楽」・・釜で沸かした湯を神に献上し、参拝者にもふりかけて
穢れを払う神楽。 自然や神が衰弱する霜月に魂振の
儀式を行い、魂を再生して新年に備えるというもの。
秋田・横手市保呂羽(ほろわ)山の「霜月神楽」が有名。
「獅子神楽」・・獅子頭に神を招き舞う神楽。多くは家々を回って厄除・
火伏の祈祷を行うもの。岩手の「早池峰神楽」が有名。
「巫女神楽」・・巫女が鈴や榊を持って舞う神楽。「浦安の舞」が代表的。
鎌倉・鶴岡八幡宮で職掌八家(しきしょうはちけ)と呼ばれる神楽奉仕の神職8家に
よって今に伝えられている湯立神楽を「鎌倉神楽」といい、これは、800年以上前に
京都・石清水八幡宮から伝えられたとされているが詳細は不明。 三浦半島では、
藤沢・白旗神社や葉山・森戸神社の神職が 各地に出向いて奉納することもあり
細かい所作や演目など多少異なる点もある。 湯花神楽、潮神楽とも呼ばれる。
でもって 今回は、実際に湯立神楽の見学に行きました。
「手子神社」
普段は無住なので、今日は横浜・瀬戸神社の
神官が出向いて神事が行われるようです。
社殿内では既に神事が始まっており、境内の釜も湯気を上げています。
私たちは外から見学。 祝詞や笛・太鼓のお囃子は聞こえますが・・
時々あちらこちらから社殿内を窺う形で、神楽の進行を見学しました。
やがて 神官が外へ。 釜場の御祓い。
中の祭壇の御祓い。
釜場で「掻湯」
御幣で湯を掻き混ぜます。
次第に激しく掻き回し、熱湯が渦を巻きます。
「射祓(いはらい)」

四方に矢を放って 邪気を払います。
いよいよクライマックスです☆
「笹舞」
釜の湯に笹を浸し、参拝者の頭上に湯を振りまきます。
湯玉を浴びると、災厄が清められるといいます。
「剣舞」
天狗の面をつけて舞います。
今回は山神(猿面)の登場はありませんでした。
最後に、参拝者に釜湯のお振舞。
頂いた白湯を飲み、活力再生・健康を祈念します。
これで「湯立神楽」は 滞りなく終了しました。
数年前 鎌倉で、五所神社の「潮神楽」を見学したことがありました。
その時は 殆ど神楽の知識はありませんでしたが、今回講座に参加して
いろいろ教えて頂いたおかげで、多少理解が深まったように思います。
博物館の瀬川先生 ありがとうございました 
「山下公園」から 港の風景を楽しみながらぶら~り☆
「横浜港大桟橋」

帆船が見えます
「海王丸」でした~


「赤レンガパーク」
ギンナンがいっぱい!
ネコノヒゲ (シソ科)

キンモクセイ (モクセイ科)
もう そんな季節なんですね
晴れたり 曇ったり
曇ったり の一日でした
の一日でした
14,299歩 
あじさいの季節ですね。
我が家のあじさいも、そろそろ色づき始めました。
さて、先週のことですが・・
横浜・金沢区の観光ガイドさんの案内で、‘金沢四石’と呼ばれる
石のひとつ、「飛石」のあるお寺を訪ねました。
江戸・文化文政の頃、庶民の間では 鎌倉・江の島・大山といった観光地への
旅が盛んに行われるようになり、金沢八景も多くの観光客で賑わいました。
そうした旅人たちを呼び込む目玉として、金沢八景の他にも‘金沢八名木’や
‘金沢七井’などと 地元では知恵を絞って宣伝に努めたのでしょう。
‘金沢四石’も、そうした中で観光スポットとして生まれたもののようです。
※金沢四石=称名寺の「美女石」と「姥石」・琵琶島弁財天の「福石」・金龍院の「飛石」
京急「金沢八景」駅前から R16を下って行くと、左側に
「八景一見之地 飛石」の碑

ここからお寺へ向かって 参道を歩いて行きます。
門を入ると
「昇天山 金龍禅院」
臨済宗のお寺です。
山号は、昔 当院にあった硯から龍が昇天したことに由来するとか。
創建: 永徳年間(1381年~1384年)
開山: 方崖元圭(建長寺第47代住職)
本尊: 宝冠釈迦如来
本堂右手塀内の庭園に「飛石」があります。
「飛石(とびいし)」
手前にある高さ3mほどの大きな石が、それ。
もとは この後行く「九覧亭」の崖上にあった「高さ一丈余 広さ九尺余」の巨石
でしたが、1812(文化9)年の地震で現在の地に落下したのだそうです。
緑に覆われたてっぺんに、「飛石明神」が祀られた石祠が乗っています。
古来 我が国には巨岩・奇石を「神宿る石」とする磐座(いわくら)信仰がありますが
この石も 嘗ては海に突き出した姿で、人々の信仰の対象となっていたのでしょうか。
『新編鎌倉誌』によると、昔 「瀬戸神社」のご祭神大山祇命(おおやまつみのみこと)が
伊豆・三島から飛び来たって、この石の上に降り立ったと伝わっているそうです。
庭園を出た所にある小さな門から、石段を上って行きます。

石段の途中に、小さな石仏があったりして・・
急な石段を上りきると、小じんまりした平場に着きます。
「九覧亭(きゅうらんてい)」跡
金龍院裏山の展望台で、「金沢八景」や富士山も見渡せたところから「九覧亭」。
(藤棚は、1916年 大正天皇行幸の記念に設けられたそうです)
朱塗りの「聖徳太子堂」
1957(昭和32)年 建立
金沢の内海が泥亀(でいき)新田開発で埋立てられ、「金沢八景」眺望の中心は
能見堂から次第にこの「九覧亭」に移っていき、多くの文人墨客や高官貴人、
外国人なども訪れたそうで、絵画・写真・紀行文が残っているようです。
が、この季節は木々が鬱蒼と生い茂っていて眺望は望めず、樹間から
わずかに街とその向こうに海や野島などがチラリと見えるばかり・・・
往時の面影を偲ぶというわけにはいきませんでした。 残念!
でも、個人ではなかなか見られない所に上れたのは 良かったデス☆
京急「金沢八景」駅近くにある「瀬戸神社」の前に、人だかりがしています。
毎年5月15日の例大祭に伴って行われる 御神幸が始まるようです。
神社の主祭神 大山祇命(おおやまつみのみこと)が神輿に乗り、神社前の国道16号を
横切って、向かい側の平潟湾に浮かぶ琵琶島の「琵琶島神社」へお渡りになります。
「瀬戸神社」は源頼朝が、「琵琶島神社」は北条政子が勧請 建立した神社。
頼朝さんが、年に一度政子さんに会いに? なんて、ロマンチックな妄想 をしていると
をしていると
本殿から、厳かに神様がお出ましになり
神輿へ遷されると、いよいよ御神幸が始まります。
雅楽が演奏されるなか、氏子さん達に担がれた神輿は 神社をあとに
交通が一時遮断された国道を渡って、静々と琵琶島へ向かいます。

神輿の行列は 参道を進み、「琵琶島神社」に到着。
神輿が下され、社殿の前で 祝詞奏上と神楽奉納 が執り行われたあと
神輿は 再び担がれて国道を横切り、瀬戸神社へと還幸されました。
「臨港プロムナード」を 港を眺めながら歩いて

「山下公園」へ
園内のしだれ桜も ソメイヨシノも

重要文化財になった「氷川丸」

「マリンタワー」も桜越しに

大勢の人たちが 桜を楽しんでいました☆
東京や横浜のあちらこちらから、ソメイヨシノが満開とのニュース☆
一気に 春が来た~!
うららかな陽射しに誘われて、ぶら~りハマ散歩に出かけました。
まずは「横浜公園」から。
目をひく濃紅色の桜は「横浜緋桜」。

チューリップも だいぶ咲いてきました。

春の風物詩「チューリップまつり」は、4月15日(金)~17日(日)だそうです。
花いっぱいの「日本大通り」を通って
「山下公園」の方へ 行ってみることにしましょうか☆
(続)
横溝屋敷
東急線「大倉山」駅から、地図を頼りに探しながら歩くこと25分。
みその公園「横溝屋敷」
鶴見区獅子ヶ谷の畑と住宅が混在する風景の中に、 茅葺屋根の
建物が建ち並んでいて、独特の空間を醸し出しています。
代々この地で名主を務めた横溝家の旧住宅で、寄贈を受けた市が
建物の修復・整備を行って 1989(平成元)年に一般公開されました。
江戸時代の農村生活の原風景をとどめる文化財として、また当時の
資料の展示や年中行事など 生活体験の場として利用されています。
(リーフレットの説明より)
では、立派な表門から入って行きましょう☆
「表門」
長屋門の内部は、板床の上長屋と土間床の下長屋、
同じく土間床の薪置場になっていました。
門を入ると
正面にあるのが「主屋」、向かって右の建物は「蚕小屋」。
蚕小屋は公開されていませんが、主屋は内部を見学できます。
「蚕小屋」
1896(明治29)年頃 築 茅葺寄棟造り櫓付
1階は土間で 桑置場とミソ置場の2部屋。2階と小屋裏が蚕室。
「小屋」ですか? 我が家より立派かも!(笑)
江戸時代の横溝家は、村人と協力して鶴見川周辺を開墾して造った水田で米を作り、
明治時代になると、横浜港から輸出される生糸や お茶の生産を始めました。
養蚕は年に春・秋の2回で、蚕は孵化から繭になるまで約35日を要し、横浜の
大半の農家では、繭そのものを八王子や長後の糸屋へ出荷していたそうです。
養蚕の準備と作業の様子(説明パネルより)

「穀蔵」
1841(天保12)年 築 茅葺両妻兜造り
収穫した米・麦などを貯蔵した建物で、約21cm厚の壁で湿気を防ぎます。
「文庫蔵」
1857(安政4)年 築 茅葺両妻兜造り
年貢の帳面など重要書類や晴れ着などを入れた長持・葛籠(つづら)を保管。
「主屋」
中に入ってみました。
1階にはたくさんの雛飾り、2階にはいろいろな資料や生活用具などが展示されています。



主屋を横から
梅林と古民家の見学、今日はちょっと欲張ってしまいました~ 
14,932歩 









