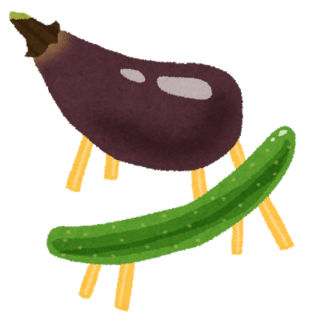所用で 久しぶりに 都内へ
何年ぶりだろ?・・・コロナ禍以来 初めてかも
懐かしくなって 用事を済ませてから ちょっと 上野公園へ 寄り道♪
あまり 時間の余裕がないので 美術館や博物館には寄らず
深い緑の中を のんびり ぶら~り
ん~ 気持ちい~~!
「お化け燈籠」も 変わりなく☆
高さ 6.06m 笠周り 3.63mの 巨大燈籠
日本三大燈籠のひとつと いわれています
1631(寛永8)年 創建間もない 東照宮に 寄進されたもの
不忍池(しのばずのいけ)
蓮池
公園の南端にある 天然の池 周囲 2km 総面積 約 11万㎡
蓮池・ボート池・鵜の池に 分かれています
江戸期 天海僧正が この池を琵琶湖に見立て 竹生島に
なぞらえて 中島(弁天島)を築造
池畔に 「駅伝の碑」
「 我が国最初の駅伝は、首都五十周年記念大博覧会『東海道駅伝
徒歩競走』が 大正六(1917)年四月 二十七日、二十八日、二十九日の
三日間にわたり 開催された。スタートは 京都・三条大橋、
ゴールは ここ東京・上野不忍池の 博覧会正面玄関であった。」と
「 五條天神社 」

祭神:大己貴命
少彦名命
相殿:菅原道真
第12代 景行天皇の頃(1900年前ごろ) 日本武尊が 東征のため
上野忍が岡を通った折に 薬祖神二柱を祀ったと 伝わります
健康祈願・病気平癒・学業成就の 御利益があるとか
しっかり お詣りしていきましょう!
短い時間だったけれど 森林浴がてら 若かりし頃のあれやこれやを
懐かしく 思い出したりしながら ちょっとしみじみ・・










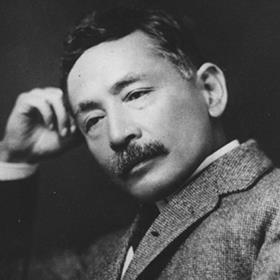 1867-1916
1867-1916














 は 遠慮しました。
は 遠慮しました。