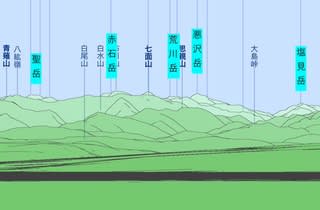大乗仏教という仏教のバリエーション化(変容)において、阿弥陀如来という、
実在した釈尊ではない仏陀を立てて、それを信仰する浄土教(阿弥陀信仰)に違和感を抱き続けていた。
神を措定せずに自己の変容によって死の問題を解決させる、人類史的に特異な教えだった仏教が、
絶対的他者を立てて、それを信仰することで天国に行ける、というありきたりな”宗教”に堕してしまった感があったからだ。
言い換えれば、それだったら”仏教”でなくてもいいんじゃないの?という感じ。
このような浄土教の存在理由を、あくまで仏教の内なる変容の論理として、
すなわち仏教の1つのあり得る方向性として、考えてみようと思った。
なぜそう思ったかというと、自分自身の中で感じた仏教の本来的困難さ(不可能性)の壁を越えたかったから。
仏教の本質は、菩提心を動機として修行に励み、煩悩を克服して、悟りの境地に達して、
生物として存在すること(生老病死)の苦から脱することにある(らしい)。
実践的ポイントとなるのは、修行による煩悩の克服にある。
すなわち、煩悩だらけの「欲界」に生きている状態から抜け出すことが求められる。
欲界は生存本能に由来する生物の生きる世界そのものであるから、
いわば自己に内在する生物性を否定することである。
性欲はもちろん、食欲も睡眠欲も制限し、そして裕福になりたいための経済活動も否定される。
身体をいたずらに痛めることを自己目的化した”苦行”こそ否定されるが、
リラックスした気楽な生活も否定され、
出家すなわち、家族を中心とした社会関係を頭髪とともに断ち切り、
ストイックな集団生活(サンガ)での瞑想(禅定)修行が求められる。
仏教における悟りの道は、この出家が唯一とされる。
経済活動も子孫の再生産も否定された出家集団は、そうでない欲界にどっぷり浸かって生産・家庭生活をしている人たちの存在(資源の供給元)を前提しないと、
そこからの布施で生きる彼ら自身の生活の維持が成り立たない。
仏教の唯一の道である出家主義はいわば依存的エリート主義である。
この結果、普通に家庭を持って経済活動をしている人たちは、出家を援助する功徳しか積めず、
仏の道は閉ざされる。
市井の(経済活動に従事せざるをえない)一人としての私自身が感じた仏教の壁(困難さ)がこれだ。
仏教にそれなりの救いを求めていながら、どうしても出家生活に踏み込むことはできない。
正直いって、そこまでしたくない(出家したくなるほど在家の生活に”苦”を感じない)。
こう思うのは私だけでなかったわけで、仏教は在家を見捨てない方向に進まざるをえなくなった。
それが大乗(大勢乗せる)仏教であり、菩薩道である。
菩薩道は、自分が悟って仏になる菩提心がありながら、その自分より先に迷える衆生を救済することを優先することを決意した修行者(菩薩)のあり方をいう。
大乗仏教ではまずは菩薩になることが目標化されたことになり、
その結果、菩薩自身の到達目標である仏(如来)の道が遠のき、
仏になるには三劫という無限に等しい時間(人間としての存命中は不可能)が必要とされることになった。
釈尊の時代は生身の人間の弟子たちも悟り(=仏)に達したのだが、
大乗仏教では仏はより深遠な絶対神のような超絶的存在に高められてしまった。
こうなるとまさに仏教の壁がさらに強固になって、人が仏になることの不可能性に陥る(仏教は不可能なのだ)。
この不可能性をうちやるぶるために、大乗仏教の次なる段階において、
誰でもが仏になる可能性を本来内在しているという如来蔵思想が誕生し、
さらに特定の修行法を実践すればその場で仏になれるという即身成仏思想も誕生した。
ただこうなると逆に、煩悩即菩提よろしく、仏になるのに何も特別なことは必要なくなり、今のままでいいじゃん(現状肯定)となってしまい(本覚思想)、そうなると仏教そのものが必要なくなってしまう。
つまり、仏教は「不可能か不必要か」というどちらに転んでも不都合な”回避・回避のジレンマ”に陥る。
結局、人間の思考のバイアス傾向である”極論化”が、そのバイアスを戒めて「中道を歩め」とした釈尊の教えの元でも発生を抑えることができなかったわけだ。
仏の道を歩みたい(自分を高めたい)が、在家の生活を捨てることができない、社会の大多数の人たちは、出家以上に困難な菩薩の道を歩むことはできない。
では自分たちは永遠に救われないのか。
待てよ、菩薩の道を歩んでいる人たちが存在してきたなら、彼らは自分が仏になる前に衆生を救おうとしてきたのだから、
菩薩の道を自ら歩めない我々は、その菩薩の慈悲(救済)の対象になるはず。
我々は衆生のまま、すなわち現在の社会生活を維持したままでいるからこそ、慈悲(救済)の対象になれる。
すなわち自分の努力(自力)によって悟りの境地に達するのではなく(不可能か不必要)、他者である菩薩・仏の力(他力)によって、自分たちが救済される道があった。
この立ち位置の転換は、大乗仏教における救済する側からされる側への、まさにコペルニクス的転回だ。
経典によると、そう誓った菩薩は法蔵菩薩であり、この菩薩はすでに悟りに達して阿弥陀如来という仏になっている(という)。
ということは、我々衆生は、阿弥陀如来の慈悲によって救済が約束されているのだ。
その救済とは、苦に満ちたこの世から、阿弥陀如来が管轄する「極楽浄土」に往かせてくれることで、その浄土で我々は阿弥陀如来に見守られながら快適に悟りへの修行に励むことができるのだ(往生=浄土に往くこと、が本来目標ではない)。
なので、今の世で出家してストイックな修行に打ち込む必要はなく、
この世(欲界)での真っ当な社会生活が終了したら、極楽浄土に往ってそこであくせく欲界的活動に追われることなく、すこぶる快適な環境下で瞑想修行に専念すればいい。
唯一必要なのは、我々をそのようにしてくれる阿弥陀如来の慈悲にひたすら感謝して、人の道を踏み外さなければいい。
踏み外すと、業(カルマ)という自己責任メカニズムによって極楽ではなく、地獄に往ってしまう。
こういう教えが、例えば法然上人から説かれることで、出家することも寺に寄進(という功徳)もできない、日々の活動にいそしむ一般庶民の間に阿弥陀信仰が広まった。
如来蔵思想に甘えず、欲界に生きる凡夫であることを自覚しながらも、現世ではなく来世まで視野に入れて仏の道をより快適に歩むことができると確信することで、(悟りを目指す)仏教徒であることが維持される。
確かに、この自力から他力への転回によって仏教徒であることのハードルは下がった。
ただし、この教えは、阿弥陀如来と極楽浄土の存在が前提となっており、その前提の存在証明は科学的にはなされない。
ということは実証的根拠なしに信じるしかないという意味で、既存の宗教と同趣の神話(物語)に依存していることになる。
そもそも阿弥陀信仰も含めた仏教全体が前提としている”六道輪廻”自体が物語(空想的構成物)といえる。
この部分を解決しないと、現代人にとっての仏教は、他の宗教と同じく、
人間の心(システム2)によって構築された物語(神話的宗教)の1つにすぎなくなる。
真の問題は解決していない。










 、少なくともその軽いシミュレーションとみなせる。
、少なくともその軽いシミュレーションとみなせる。